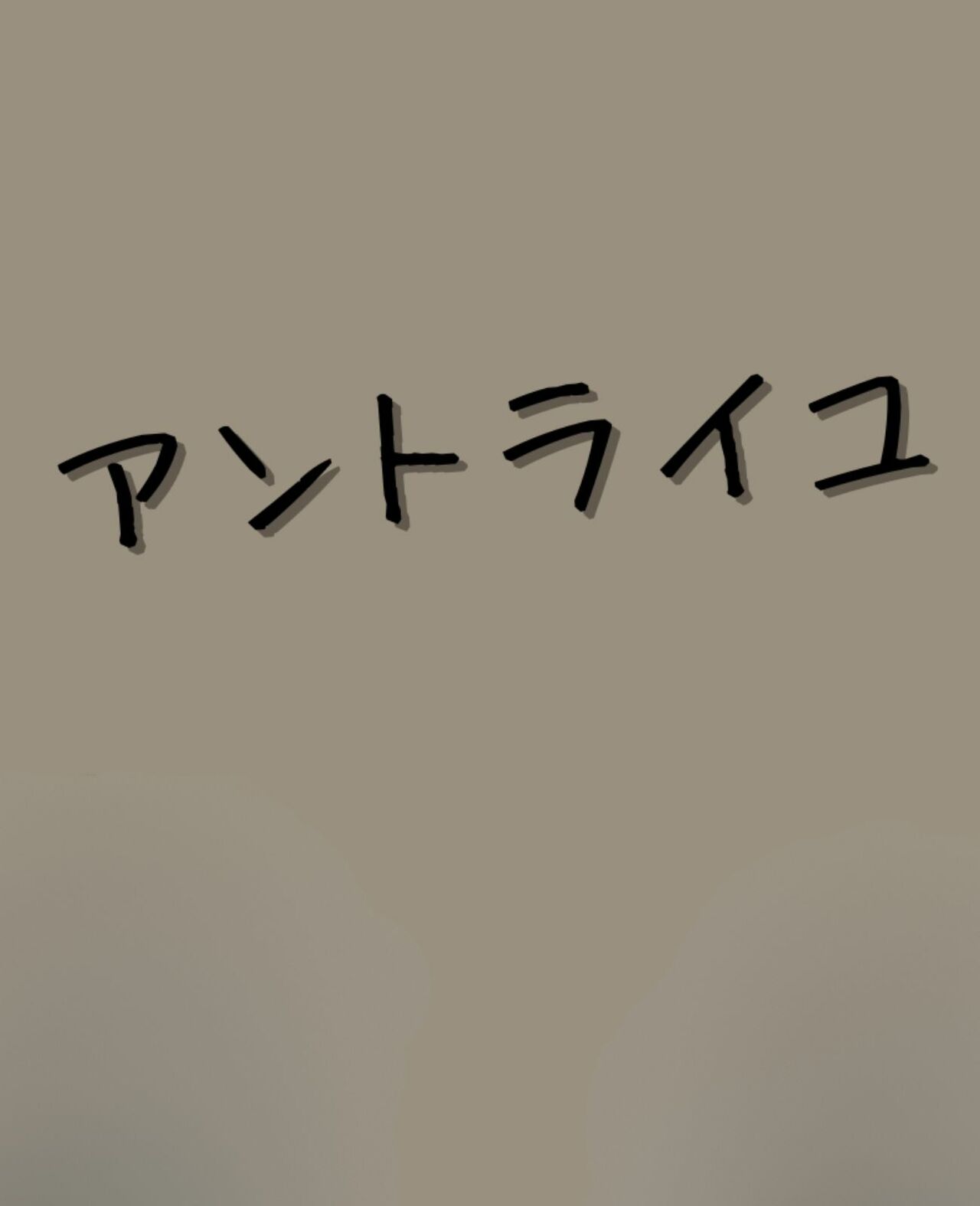【前回の記事を読む】風に靡く彼の金髪がキラキラしてまるでアニメに出てくる美青年のよう…「海が見える駅」は私たちのお気に入りだった
アントライユ
2
二人でプレートを適当に見ていると、私たちの前にいた男性が話しかけてきた。「How much?」と低めの声で問いかけてくる。目の前にいるカップルが外国人だと悟る。ハート型のプレートの値段を知りたいらしい。
私は冷や汗をかきながら必死に答えようとした。生憎、英語のテストがいつも赤点だったことしか思いつかない。もっと勉強しておけば良かった。いや、私は国語が得意なのだ。日本に居れば英語なんて必要ない。
「Two thousand yen.」
千春が私の後ろからそう口にした。
「千春、英語話せたんだ」
「これ位は中学で習うだろ」
外国人男性は嬉しそうに千春の手を握り、カタコトの日本語で「どうぞ」と順番を譲ってくれた。輝く笑顔に負けそうになりながら、その厚情を何とか断ろうとする。
「いえ、私たちは並んでなくて」
「行こ。譲ってくれてんだし」
千春の予想外の言動に戸惑ってしまう。こういうものには興味なさそうなのに。太陽に雲がかかったような微妙な気持ちが邪魔をし、思わず彼の腕を掴む。
「待って。これって恋人同士でやるものじゃないの?」
「別に誰が鳴らしても良いんじゃね?」
千春は自ら鐘の方へ向かって進んで行く。私は周りの目を気にしながら、すごすごと着いて行った。
私は最後まで渋ったが、二人で綱を持って左右に振った。海に向かってカーンと鳴り響く鐘は臓器を軽く揺さぶった。その気持ち悪さにサッと手を引く。可愛らしく高らかに鳴る様は、まるで自分たちの関係を見透かしているようだった。
私たちには似合わない甘い雰囲気と相まって居心地が悪くなってきて、その場を離れようと試みる。千春の腕を掴んで歩みを急かす。彼は不服そうに眉間に皺を寄せた。
「掴むなよ。歩きづらい」
「だって、見られるの恥ずかしい」
千春は私に抵抗するように身を引いて歩いた。彼を引きずる私は、輝かしいカップルたちから見たら大変滑稽なのだろう。視線が刺さる。被害妄想なら良かったのに。
「私たち、恋人に見えてるのかな」
千春は黙ったままだった。