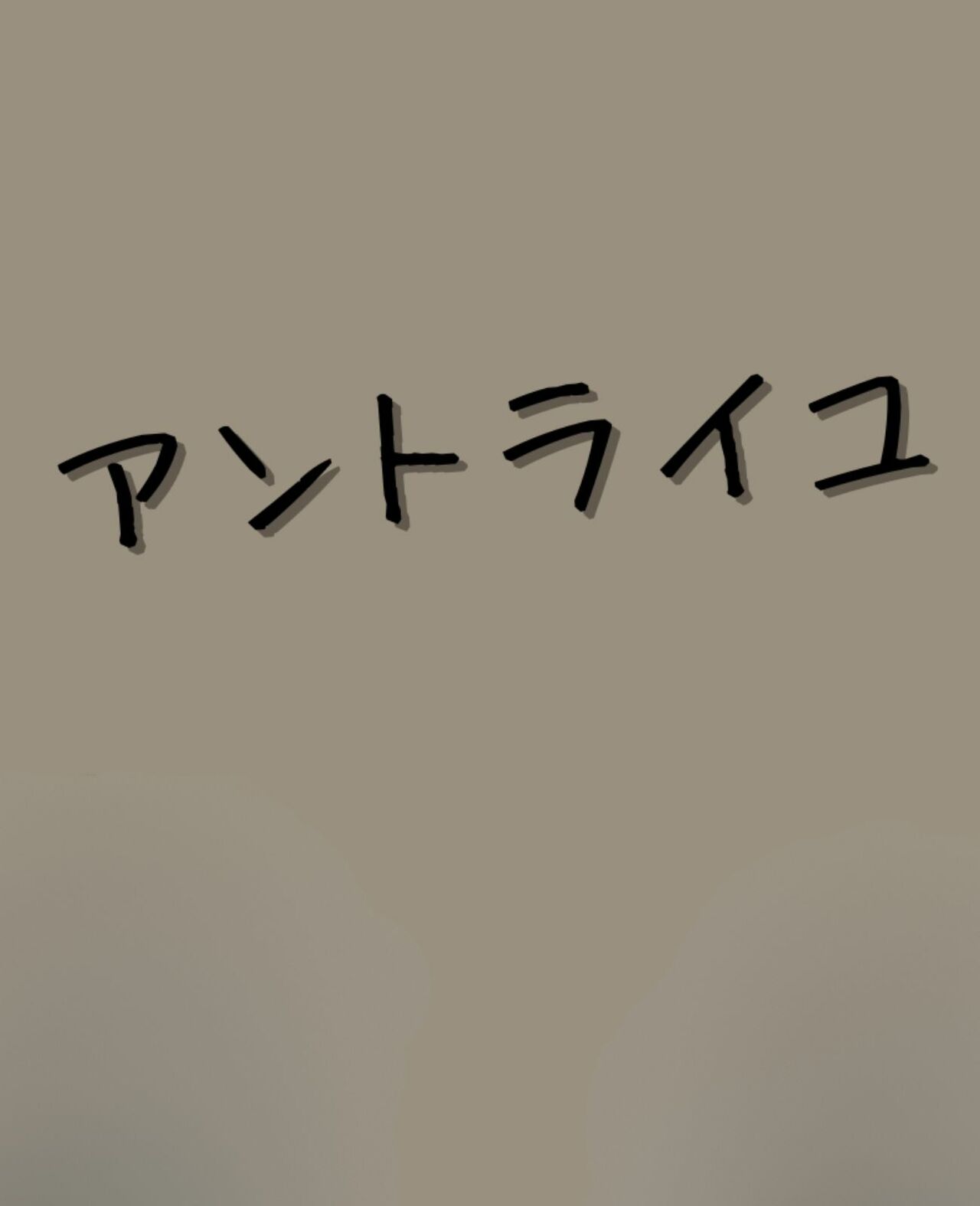私は口を尖らせて踵を返すと、銀色のプレートが目に入った。そこには気になることが書かれていた。鍵やプレートは錆びたり古くなっても、取り外して大切に保管しているらしい。ここを訪れた仲睦まじい恋人たちにとっては、きっと願ったり叶ったりの温情だ。
「愛も定期的なメンテナンスが必要です。何年か後には新しい鍵を取り付け、新たに愛を誓いましょう。だって」
なんて素敵な世界だろう。私は一人嘆声を漏らした。ドラマチックな言葉は女の子なら一度は心が躍る。でも千春は興味が無さそうにプレートを見つめる。それを見て『愛』は私たちに関係の無いことだということを思い知らされる。胸に閊える何かに気づかないふりをして力無く垂れる拳にグッと力を込めた。
すると、空気を読まずに腹がぐぅと鳴った。私は早く腹を満たそうと歩み出すが、彼は立ち止まったまま吸い込まれていくのではないかと思うほど海に釘付けになっていた。何か惹かれるものがあるかの様に眺め入る。
「千春、行こう。サバサンド食べたい」
彼の背中を小突くとハッとした顔で振り返り、私を睨め付けた。その鋭さに少し恐怖を抱きながら一歩後ずさる。
「どうしたの? 千春」
「いや、ちょっと考え事」
そう言って私から視線を外した。
「こんなロマンチックな場所、よく知ってたね」
「調べたら偶々あったから」
千春は徐に歩き出した。
目的地のレストランは相変わらず混み合っていた。
何とか席を確保して、一つ息を吐く。海風が爽やかなベランダの片隅だ。爽やかな春に差し掛かった季節なのに日差しがきつくて、日焼け止めの塗布が甘かったことを後悔する。