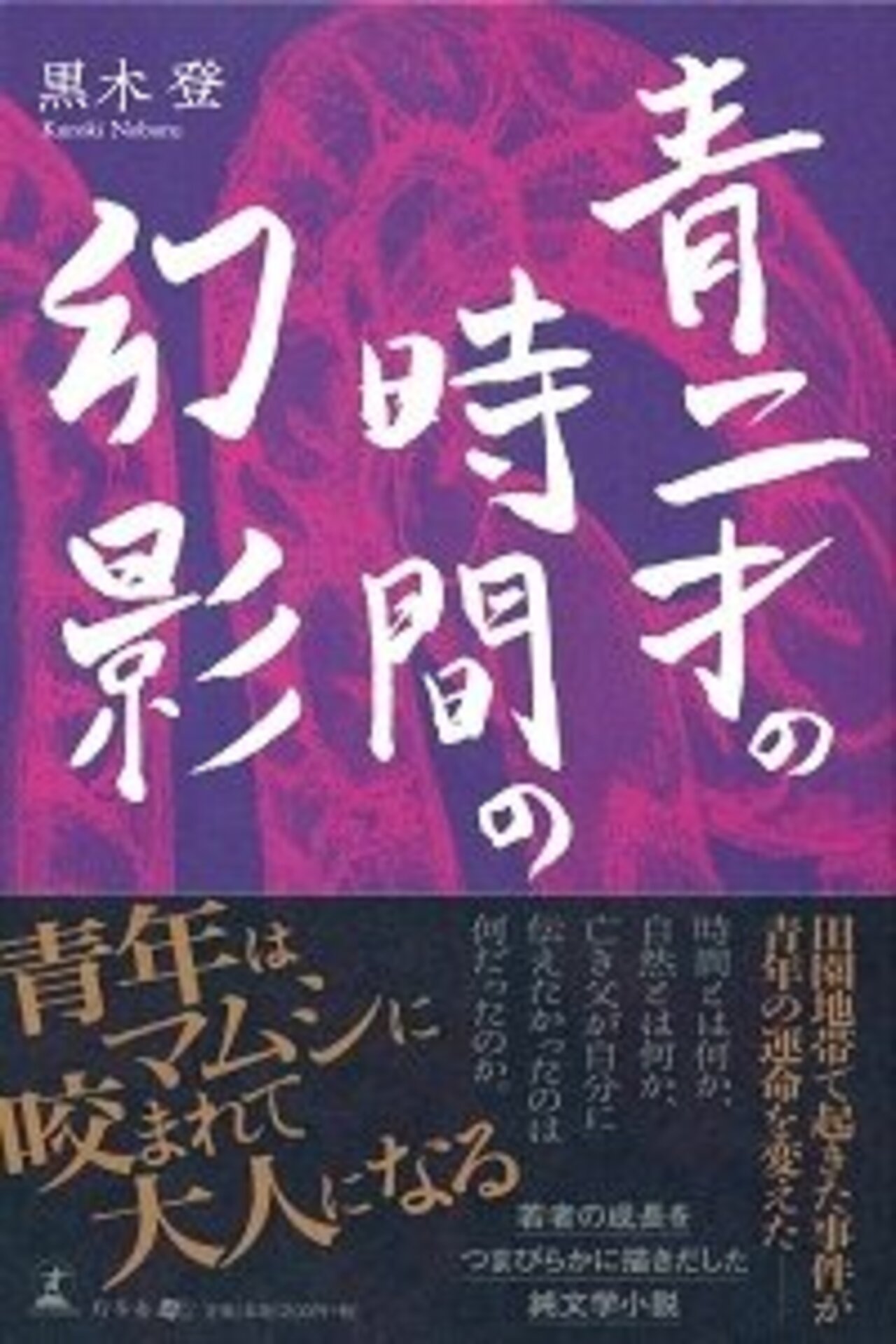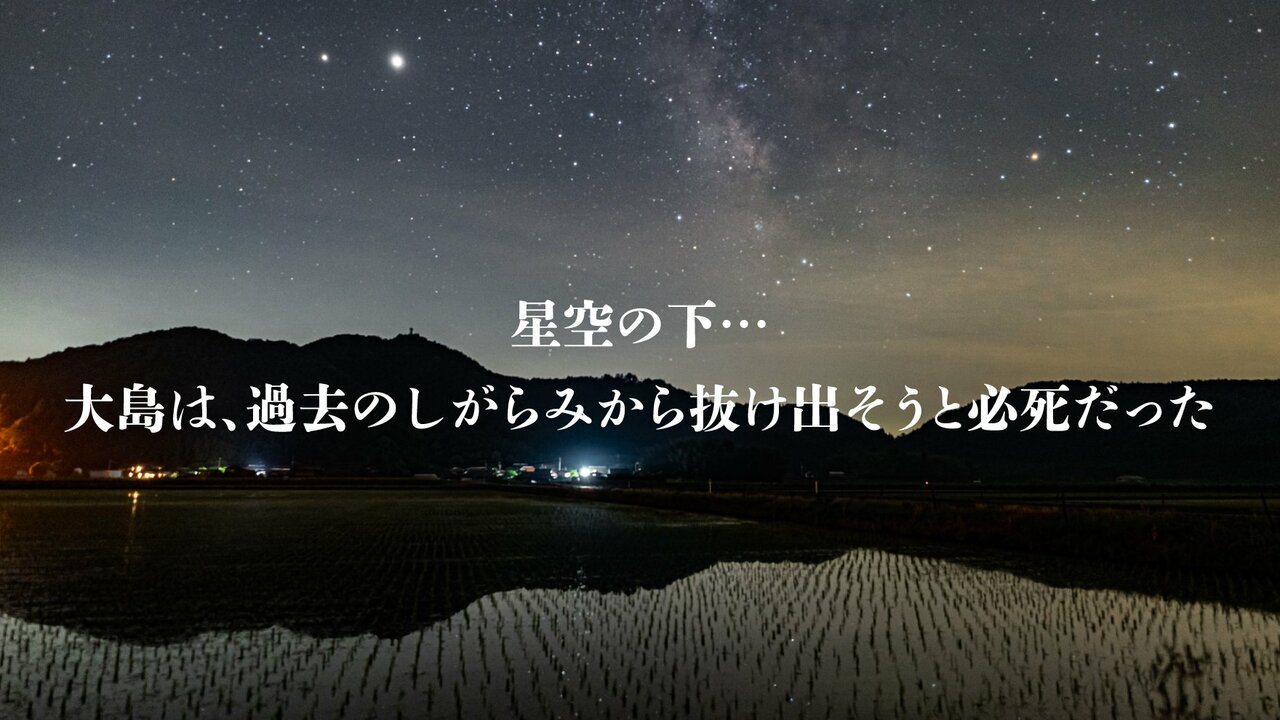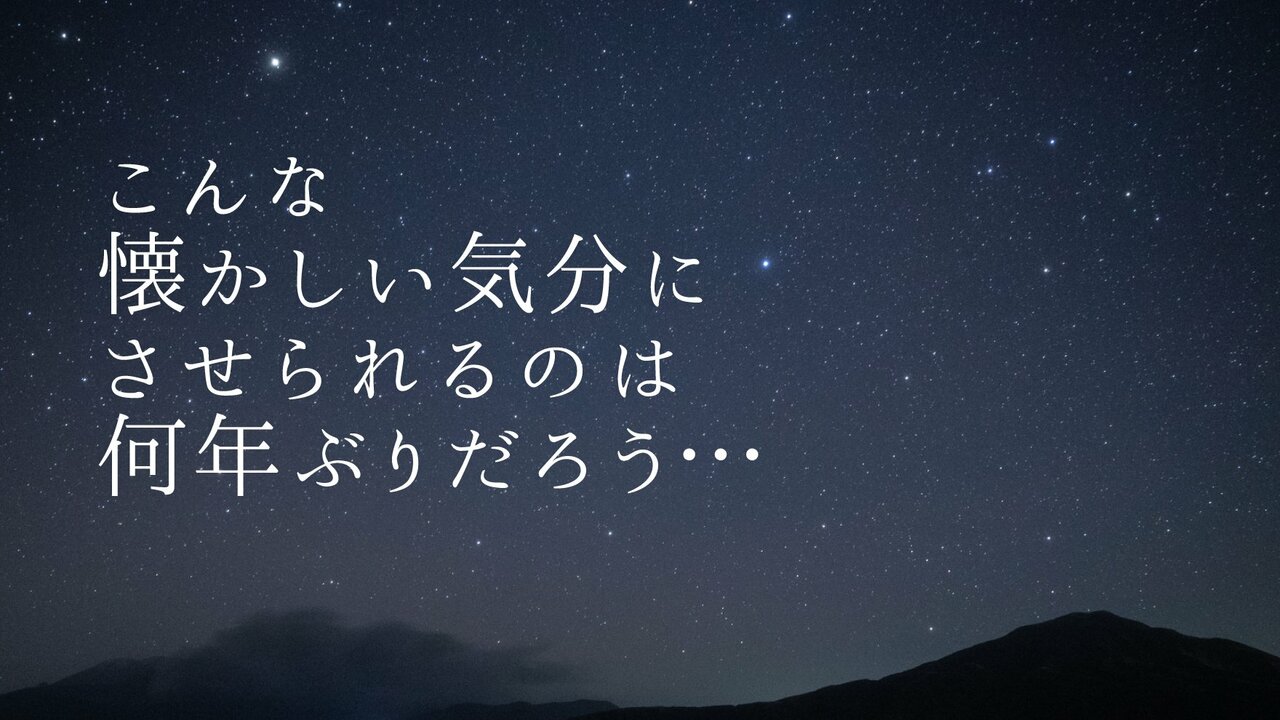時間
それは、つい最近のことだった。
その頃の大島といえば、社会人として第一歩を踏み出したばかりだったので、若者らしく夢や希望を抱き、未来へ向かって大きく胸を膨らませていたのは言うまでもなかった。
ところが、この時間という問題が急浮上してくると、その存在感は強烈だったし、取捨選択の余裕もないまま、心の中に割り込んできたのである。
以来、生活のリズムが狂わされてしまうことになる。
しかし、良く考えてみれば、そもそもの発端は子供の頃の体験がトラウマのようになって心の中に宿り、そうして潜在的に暗い影を投げかけている以上、今の自分と全く無関係だとは言えなかったし、むしろそこに災いの火種が隠されているのなら、それを明らかにしない限り、この時間という呪縛から解放されることはないだろう、と思われたのだった。
そうして自分を戒めると、今度は大人の視点で、その不可解な時間と向き合い、時間とは何かとか、その謎めいた時間に真っ向から挑もうとしていたのである。
だが、この時間についての考察は雲を掴むようなもので、そう生易しいものではなかった。
その日も、大島は仕事から帰ってくると、家の用事をすませたあと、さっそく机に向かっていた。
しかし、頭の中を思考の波が怒濤のように押し寄せ、そうして複雑に絡み合うまではよかったが、それから先がいけなかった。頭の中がこんがらがって、もつれた糸が思うように解けないのだ。
思考回路がいかれると、もうお手上げだった。憮然とした表情で不快感をあらわにすると、堪忍袋の緒が切れた。高ぶった感情を抑えきれない。
息が詰まりそうになると、匙を投げるのも早かった。
頭に血が上ってカッとなった瞬間、大島は蒼白い顔をいっそう硬直させ、椅子から急に立ち上がっていた。立ち上がったかと思うと、前後の見境もなく、アッという間に部屋を飛び出していたのである。
大島が自己嫌悪に陥るのは、そう珍しいことではなかったが、堪忍袋の緒が切れて部屋を飛び出したのは、そのときが初めてだった。
気がつくと、大島はアパート前の薄暗い路上に憮然とした表情で突っ立っていた。慌てふためいていたのか、突っ掛けを引っ掛けたままの格好だった。