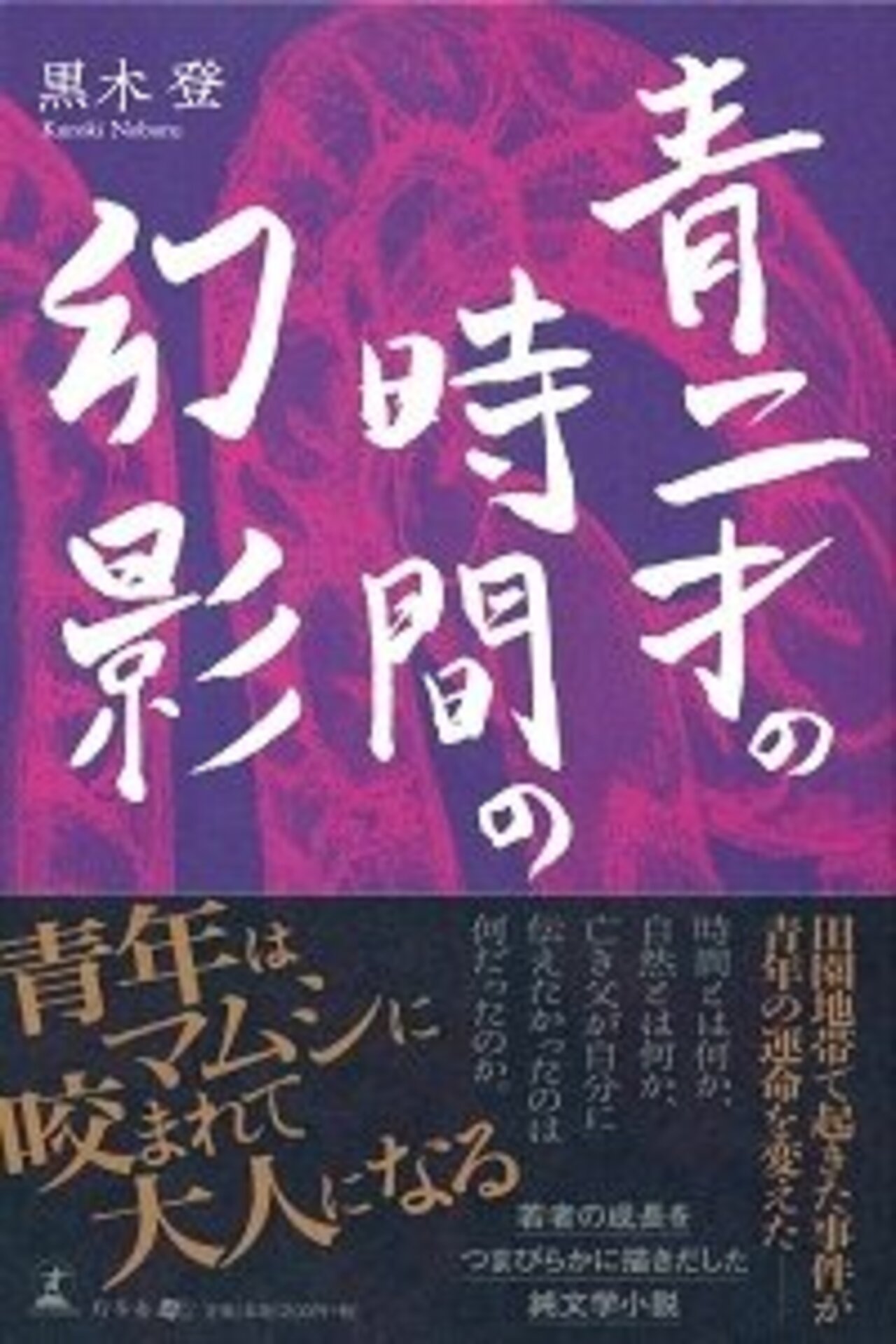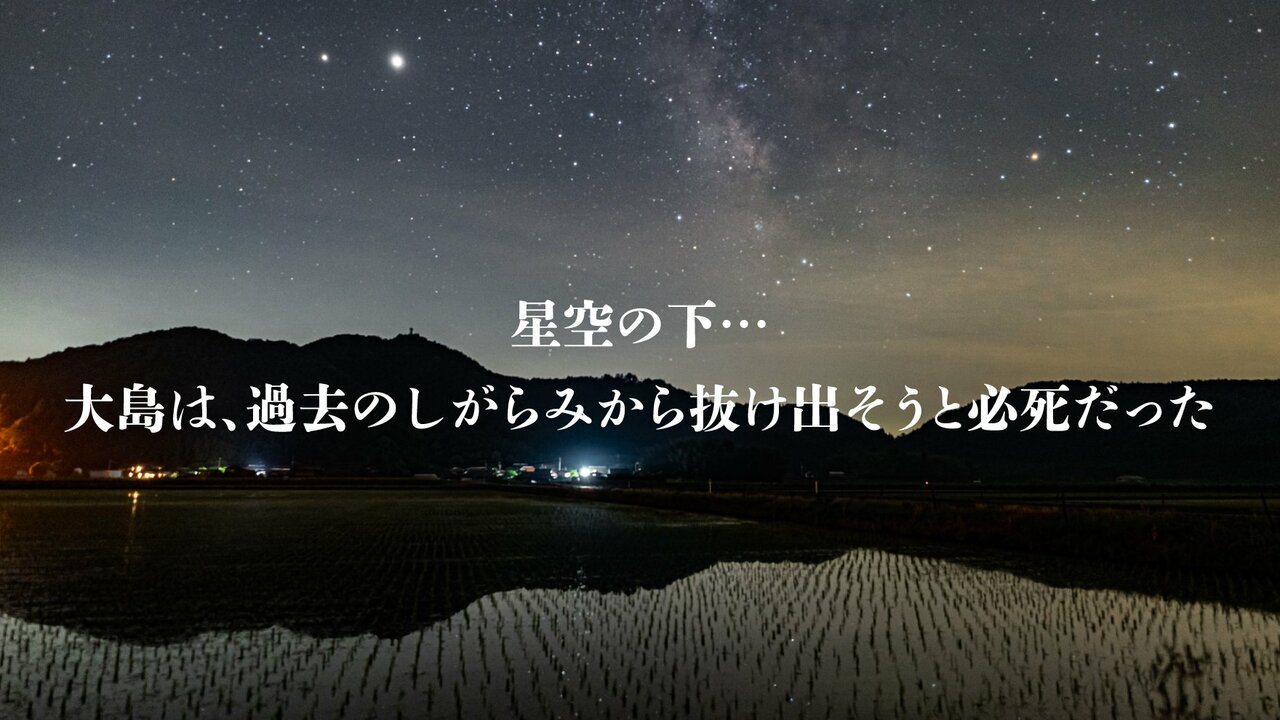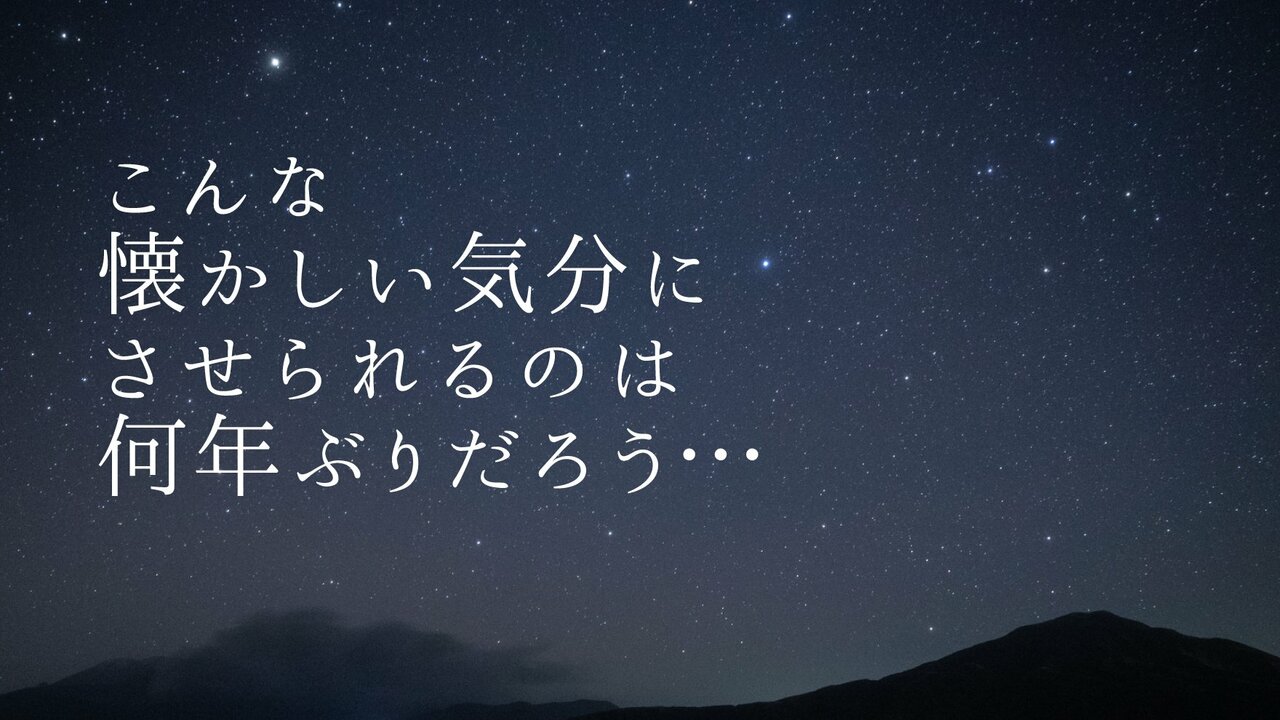何かに虐げられたような気分だった。憔悴し切ったような顔があった。若者特有の精悍さなどはない。ひんやりした空気が頬を伝わったが、気持を立て直すまでにはいかない。
畜生……。
腹立たしさや悔しさが蒸し返されてくる。心が彷徨い出すと、大島は心の重い荷物を引きずりながら、薄暗い路地を憂鬱そうに歩いてゆく。その辺りは、猫の額ほどの狭いエリアに長屋風の古い二階建て木造アパートが密集しているところだった。
古い時代からの名残りなのか、路地という路地は極端に狭く、迷路のように入り込んでいる。どことなくドブ臭い臭いもする。市街地の中でも都市景観を損ねている地域の一つに挙げられているところだったが、未だ改良の兆しは見えない。
かつて都市計画法に基づいて、その辺りの土地区画整理事業が持ち上がったものだが、事業が宙に浮いたままになっていたのは、市の予算規模が試算金額に追いつかないという財政上の事情があったからだろう。
老朽化した木造アパートの中には、壁板が剥がれそうになっているところもあったが、そのまま放置されたままだ。裸電球は、いつまでたっても裸電球のままである。
夜ともなれば、酔いつぶれた男の喚き声とか女の甲高い声、あるいは赤ん坊の泣き声などに悩まされたものだが、そんな胡散くさい雰囲気に不快感を覚えなければ、持ち家を持たない低取得者層にはそう悪い居住地ではなかった。
その夜は、夫婦喧嘩の荒々しい声などは聞こえなかった。大島は、静まり返った薄暗い路地を肩を落としながら、とぼとぼと歩いていく。時折、弱々しい視線を前方に向けると、野良猫が数匹、連れ立って駆けていくのが見えた。
大島の足取りは、重かった。
行く宛てなどもなかった。ただ無性に、どこともなく歩き回りたい気分だった。外のひんやりした空気に触れながら、少し頭を冷やそうと思ったのだが、昂った感情を鎮めるのは容易なことではなかった。
どうかすると、先ほどの、あの重苦しい部屋の雰囲気に感情が舞い戻って虚しさが蒸し返される。
大島の顔から、また溜め息がもれた。
薄暗い路地裏を通り抜け、大通りに面したひときわ明るい通りへ出たときも、ふと立ち止まって、往来する車のヘッドライトや行き交う人々の群れにそれとなく目を向けたものの、引き返す気持は起こらなかった。