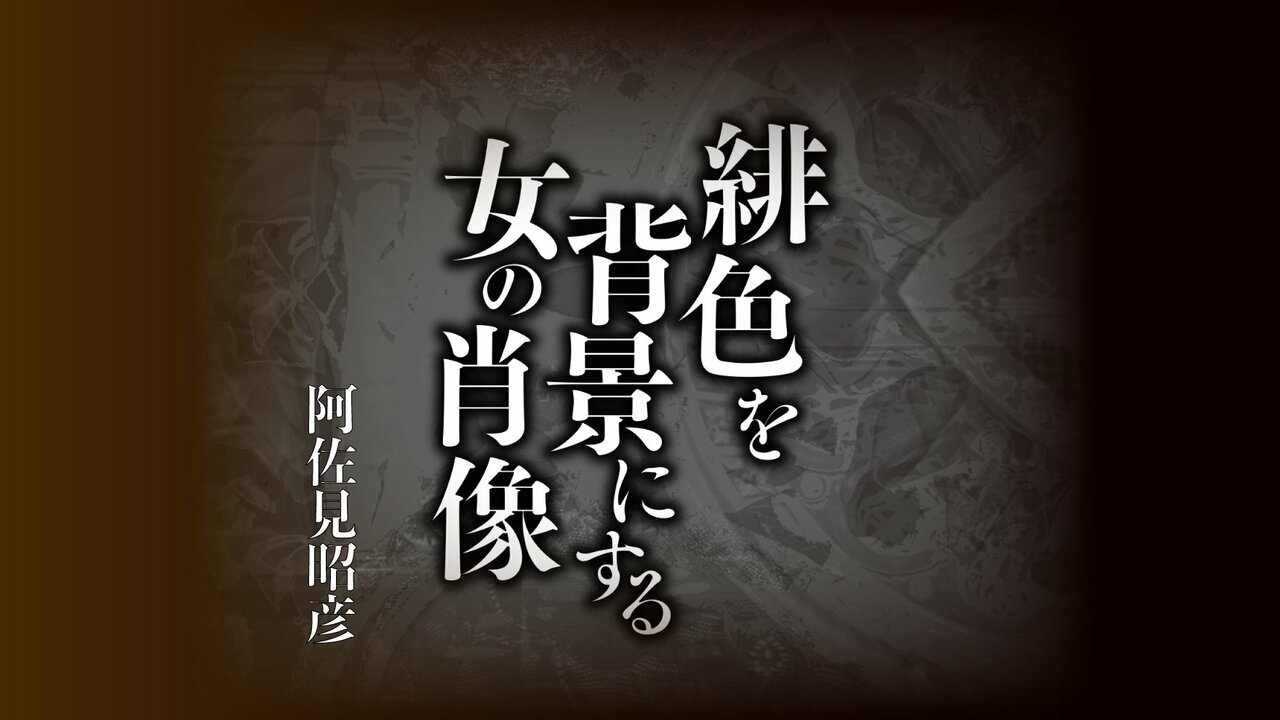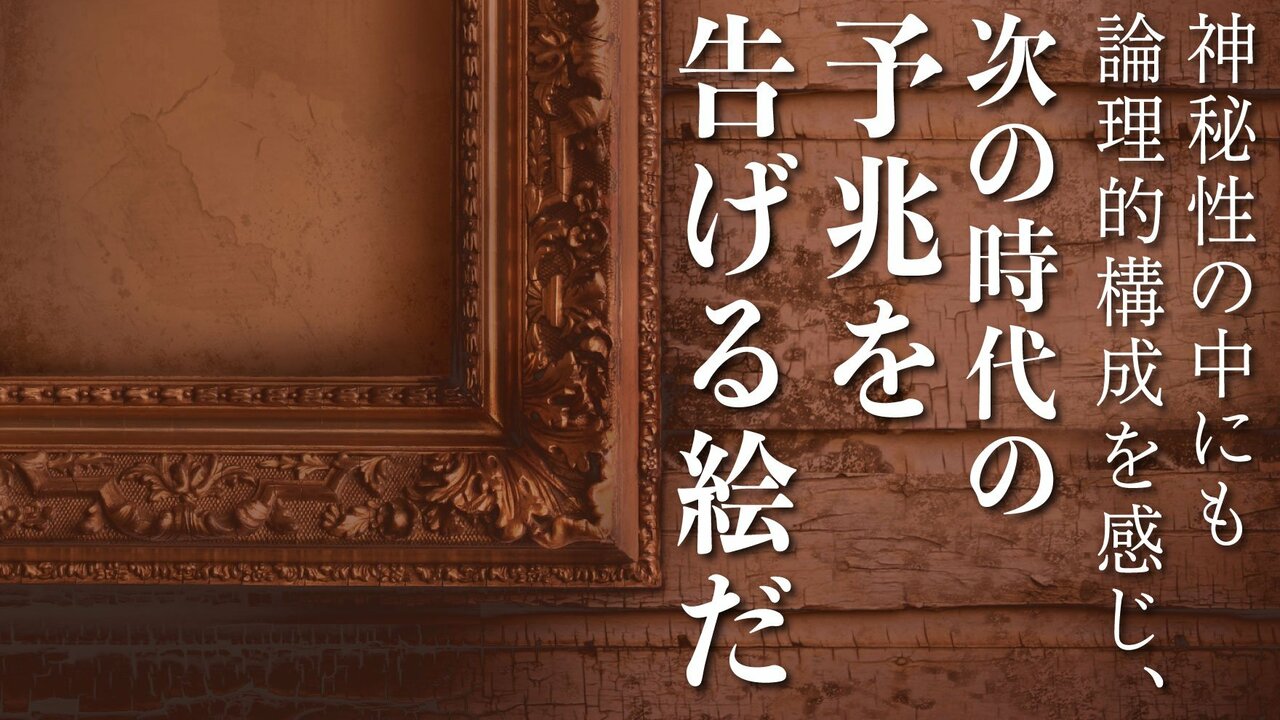邂逅─緋色を背景にする女の肖像
「あんたはなんでも良く知っているね。ヴォーン会長の格調高い挨拶で始まった恒例の前夜祭パーティーには、海外を含めて三百人を超える出展画家達が参集していた。貴族を筆頭に、政治家、実業家、文化人、そして裕福なパトロンたちに混ざって、多くの著名な画家や画商も招待されていたんだ。
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
毎年決まってそうなんだが、パーティーでは特に著名な美術評論家の解説や評価に皆の関心が集まったものだった。
この夜のパーティーで下馬評にあがった十数点の絵の中から、大賞の新人賞が選ばれることが常だったし、それにこれまでの歴史でも、このコンテストで大賞を射止めた新人の絵は、次の時代に対する絵画の方向性というかな、そんな予兆を指し示してきた実績に裏付けられていたからね。
そのときの批評家の一人が、今や英国の美術評論界の皇帝といわれるミッシェル・アンドレだった。当時新進気鋭でね、その年の審査委員長だったのさ。彼が絵を見ながら会場を移動するのにつられ、マスコミ、画商、そしてパトロンたちが大勢集まって来た。
彼らは一団となって、アンドレを取り巻く大きい輪を作った。あの頃、毎年のように繰り広げられてきた彼の精力的な批評は、遠慮会釈なく次々と打ち出される鉄砲の弾のように激しかった。
それは、もはやこのコンテストでは評判のイベントにさえなっていた。運よく評価される絵も、毒舌で一刀両断にこきおろされる絵だって、取り上げられるだけでも光栄だったという具合ですな。
しかしその年、一九六六年は大方の予想と期待を裏切り、アンドレはただの一言もコメントを発せず、会場を一周し終えてしまった。恒例の毒舌を楽しみにしていた招待客たちは、今年は一体どうなっているのかと、少々不満の空気が会場に漂い始めたまさにそのときだった。
突然、彼は再び会場をゆっくり動き始めた。驚く間もなく皆で後を追いかけると、彼はある一枚の絵の前でその歩みをピタッと止め、長い時間をかけてその絵に見入っていた。
広い展示空間の中で映画のひとコマが突然停止したかのような出来事だった。長い沈黙が続いたが、そのうち誰ともなく観衆の間に軽いどよめきが湧き起こった。会場全体がピーンと張り詰めた特別な空気に包まれた。
それは《邂逅─緋色を背景にする女の肖像》と題されたピエトロ・フェラーラの絵だった。