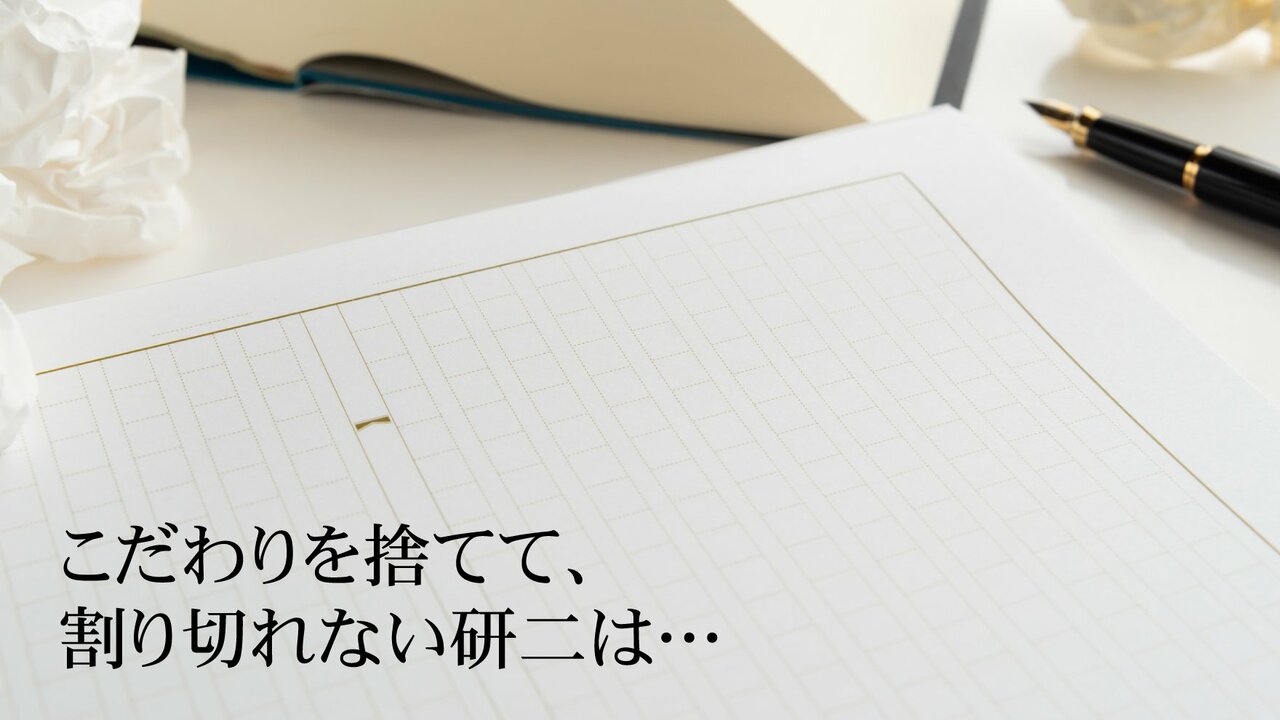「芹生さん。作品として上質なのは分かりますが…」
島崎が珈琲を口にした。
「残念ながら、まだ出版には難しい」
前回も同様の批評を受けているので覚悟はしていた。以前に書き上げ、温めていた小説だから作風自体は変わっていないのだ。前回と違うのは、自分の心の中にすがる気持ちがあることだけだった。
「ご存じのように出版業界は厳しい環境です。うちも例外ではない。文芸部門は愛澤先生のおかげで順調ですが、雑誌部門は厳しい状況です。わたしも編集統括として編集部門全体を見なければならない立場になり、文芸部編集部長の頃よりむしろ独断を通しづらくなりました」
島崎はすまなそうに言った。
「芹生さん」
島崎は一呼吸置いて言った。
「こだわりを捨てて割り切ったらいかがですか?」
言われるであろう言葉だった。
「芹生さんの筆力なら、その気になればいかようにも読者に受け入れられる作品が書けると思います。あとは割り切りです」
「はい……。それは分かっているのですが」
なんでも書く覚悟で来たのに、いざその言葉を突きつけられると割り切れない自分がいる。
「芹生さんの芸術性へのこだわりは理解しているつもりです。とても味わい深い文章だ。でも今の時代、文章の美しさを鑑賞する、味わいを求める、あるいは理解できる読者は残念ながら少数です。多くの読者はストーリー性を求めます。しかも平易な、分かりやすい文章で。
わたし自身はその傾向を寂しく思っていますが。いずれにしても出版サイドとしては売れる見込みが立たない本は出版しない。出版されなければ誰も読まない。もちろんネット出版という方法はありますが、おそらく何の広告も打たないネット上の純文学作品を読む読者は極めて少数でしょう」
「もちろんそれは理解しますが」
「まあ、あとは芹生さんの決断次第です。『グッドバイ』や『命売ります』もあるじゃないですか。太宰も三島もエンタメは書きましたよ」島崎は珈琲を飲み干した。
島崎の言うことに反論の余地はないが、今さら自分の作風を変えることは容易ではない。
創作には文体だけでなく、創作に至る動機、思想などすべてが絡んでくる。そして何よりも読者の受けばかりを意識することは、自分が追い求めてきた芸術性を諦めることになる。
「夢を諦めないで」という沙希の言葉が頭をよぎる。
「島崎さん。ご教示ありがとうございます。でも、わたしにとって簡単なことではありません。しばらく考えさせてください」
「いつでもお声かけください」島崎は笑みを浮かべた。