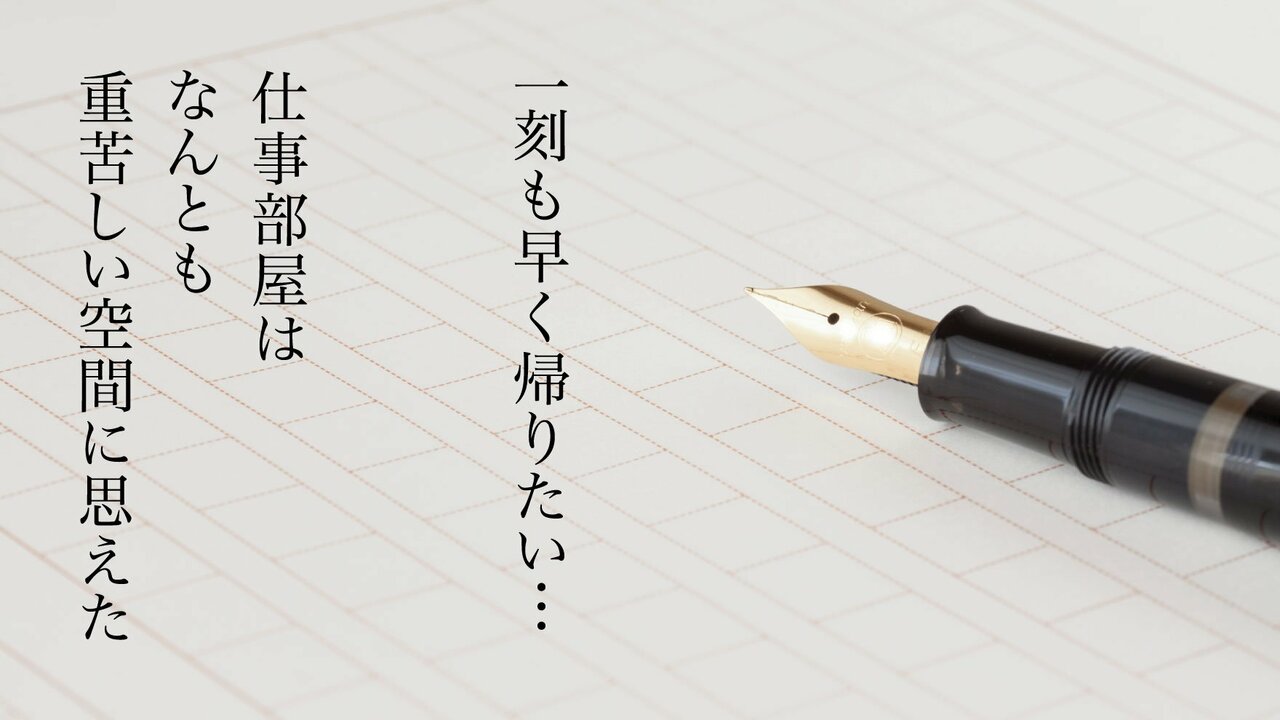【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
雇用関係
「いえ、なんでもありません」
「それなら結構ですが。なんでもご相談くださいね」
と言って彼女はくすっと笑った。普段なら愛嬌と受け止められるしぐさも、今は素直に応じられない。
「何か変ですか?」
「あ、いえ、失礼しました。でも、芹生さんは、パーティーでお会いしたときもそうでしたけど、いつも何か思い詰めたような目をされていますね」
「そうですか。それは失礼しました」
「別にあやまらなくても」
そう言って、美和は軽やかな笑いを発した。その屈託のない笑い声は、今度は鎮痛剤として少しだけ心の痛みを和らげた。
「芹生さんを見ていると、古典から抜け出してきた作家の香りがするんです。あっ、勝手なことを言ってしまいました」
「いえ、わたしは古いタイプの作家、いや物書き志望ですから」
ようやく、おそらく一時的なことではあるが、冷静さを取り戻して受け答えをした。
「古いって、悪いことではないですよね」
その言葉に、パーティーでの出会いではまだ女子大生然としていた西脇美和に、おぼろげながら大人の気配を感じる。
「えーと、芹生さんでしたっけ? 愛澤企画の社員心得の説明を始めてもいいですか? わたしもやることがあるので」
久連山が抑揚のない口調で割って入り、俺を現実に引き戻した。
「心得」という言葉は、あまりいい響きではない。まるで躾紐だ。
「いいですか」
久連山は催促した。
「あ、すいません。お願いします」
返事をすると同時に西脇美和が、
「会社に戻ります。芹生さん、またお会いしましょう」
と言って席を立った。
「それでは」
久連山は、ペットボトルに口をつけた。
「まず、愛澤企画で知り得たいかなる情報も決して外部に漏らさないこと。これは雇用契約書に書かれているので確認してください」
「分かりました」
「つけ加えますが、愛澤企画に籍がある限りは出版社を含め、一切のメディアと接触してはなりません」
「えっ、それは」
受け入れ難い要求だった。
「不満ですか?」
「いえ、でも。わたしも物書きの端くれです。自作を出版社に持ち込むことを止めるわけにはいきません」
「それはここを辞めてからにしてください。情報の秘密保持とはそういうことです。このことは契約書にも記載されていますし、あなたはサインしましたよね」