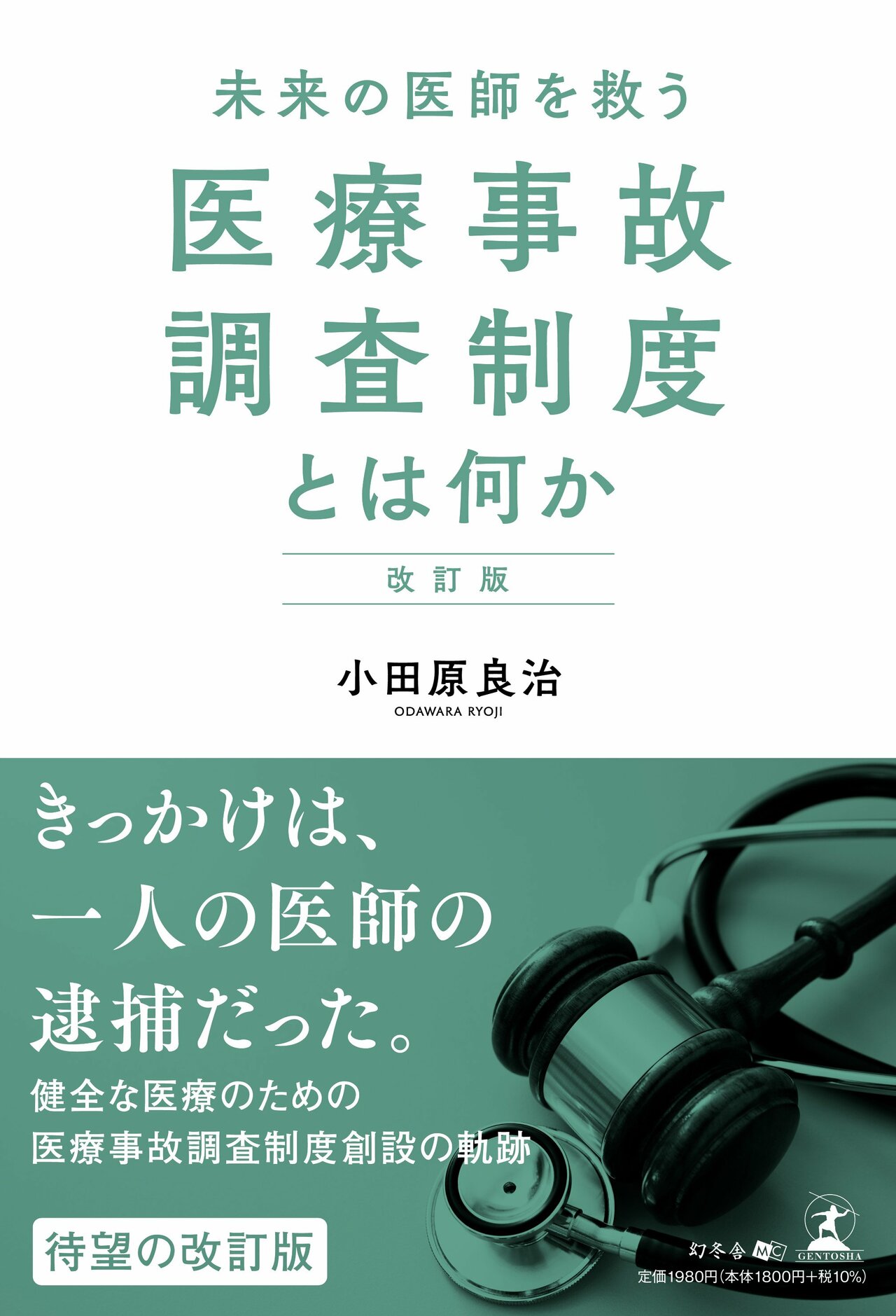しかしながら、死体の検案とは、既に述べたとおり、死因を判定するために死体の外表検査をすることであるところ、上記【1】の事実関係によれば、平成十一年二月十一日午前10時44分頃、D医師が行った死体の検案すなわち外表検査は、Aの死亡を確認すると同時に、Aの死体の着衣に覆われていない外表を見たことにとどまる。
異状性の認識については、誤薬の可能性につきE医師から説明を受けたことは、上記事実関係のとおりであるが、心臓マッサージ中にAの右腕の色素沈着にD医師が気付いていたとの点については、以下に述べるとおり証明が十分であるとはいえない。
D医師が心臓マッサージを施している際、Aの右腕には色素沈着のような状態が見られた旨供述する、D医師の検察官調書謄本(原審甲56号証)が存するが、それほど具体性のある供述ではなく、同時に、それをじっくり見て確認まではしなかった旨も供述していること、
同人は警察官調書謄本(当審検察官請求証拠番号4)においては、右手静脈の色素沈着については、病理解剖の外表検査のとき初めて気付いた旨供述し、原審公判及び当審公判においても同旨の供述をしていること、L医師の原審証言には、上記【1】のとおりこれに沿う内容の証言があることなどに照らすと、D医師は、当時、右腕の異状に明確に気付いていなかったのではないかとの疑いが残る。
以上によれば、同日午前10時44分頃の時点のみで、D医師がAの死体を検案して異状を認めたものと認定することはできず、この点において原判決には事実誤認があり、これが判決に影響を及ぼすことが明らかである。この点の論旨は理由がある。