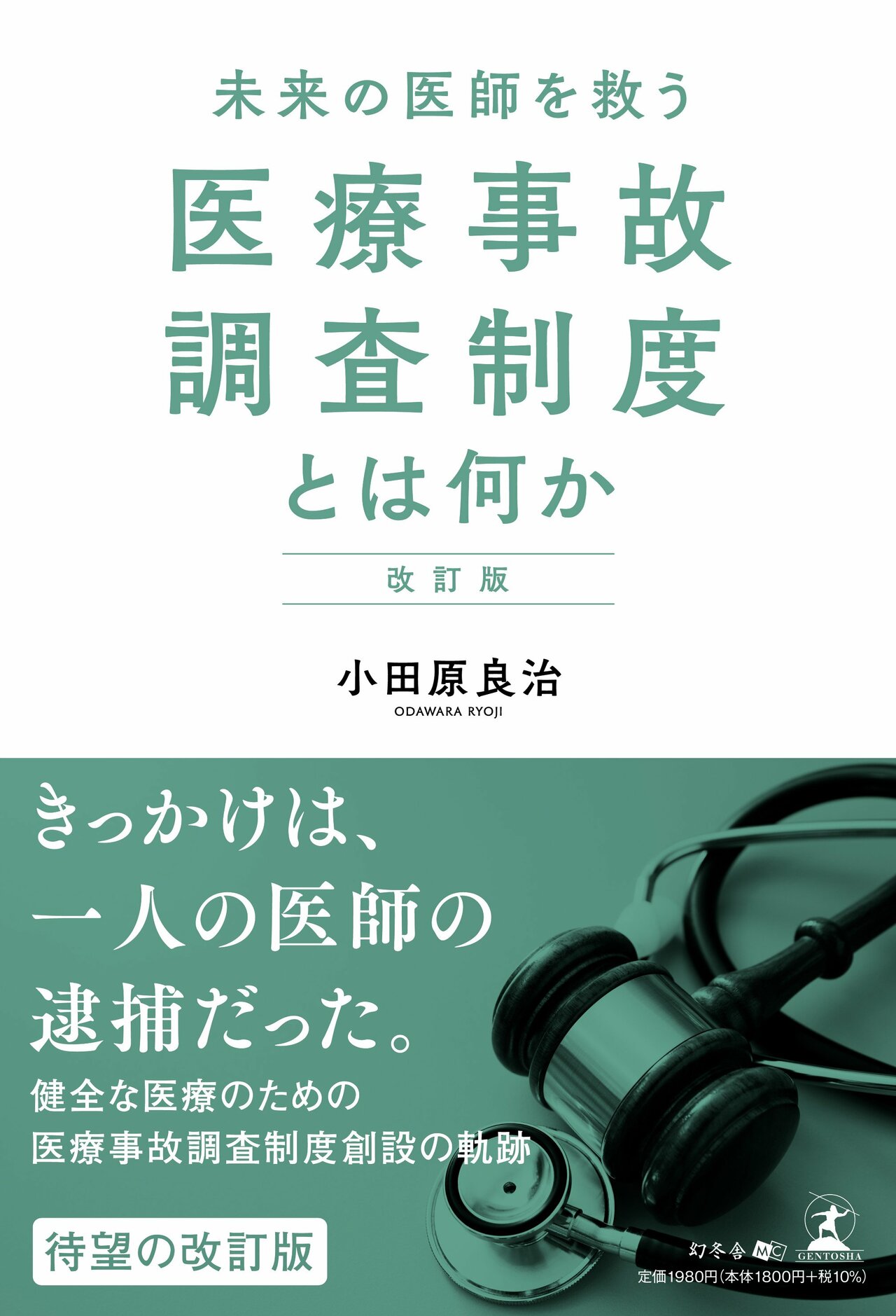これによれば、当該事例が、死亡診断書を交付すべき場合か、あるいは、死体検案書を交付すべき場合かをまず決すべきことになるが、実際問題として、その死亡の時点でこれが必ずしも客観的に明らかでないこともあり、また、医師がその判断に迷うこともあると思われる。
ウ.翻って、死亡診断書を交付すべき場合であっても、死亡診断のために死体の検案をすることはあり得る。昭和24年通知が、死亡の際に立ち会っていなかった場合につき、死亡後の診察という表現にしたのは、医師法第20条本文が規定する、診察したときは診断書を、検案したときは検案書を交付するとの区分けに忠実に考えたからと思われる。
しかし、そもそも、検案それ自体の、医学上の定義は、医師が死因を判定するために死体の外表検査を行うことをいうとされてきたものであり、そこには、診療中の患者であったか否かによる限定はない。
実質的にも、近似、DOA(医療機関搬入時に心停止・呼吸停止状態)の場合でも、医師がまだ死亡していないと判断し、診療を行ったときは、死亡診断書を交付すべきであると説明されてきたが、そこには境界的事例があり得るし、また、本件のような医療過誤の場合、昭和24年通知の解釈として、診療中の疾病と「全然別個の原因」といえるかにつき、医師が判断に迷う場合もあり得る。してみると、医師が死亡診断書を交付すべき場合であると判断したとのいわば形式的理由により、死体を検案して異状を認めておきながら、医師法第21条に定める届出義務が生じないとすることは相当でない。
つまり、医師法第21条にいう「検案」を死体検案書を交付すべき場合に死体を検案した場合に限定することは相当でない。したがって、医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が、死亡した者が診療中の患者であったか否かを問わず、死因を判定するためにその死体の外表を検査することをいうものと解すべきであり、医師が、死亡した者が診療中の患者であったことから、死亡診断書を交付すべき場合であると判断した場合であっても、死体を検案して異状があると認めたときは、医師法第21条に定める届出義務が生じるものと解すべきである。