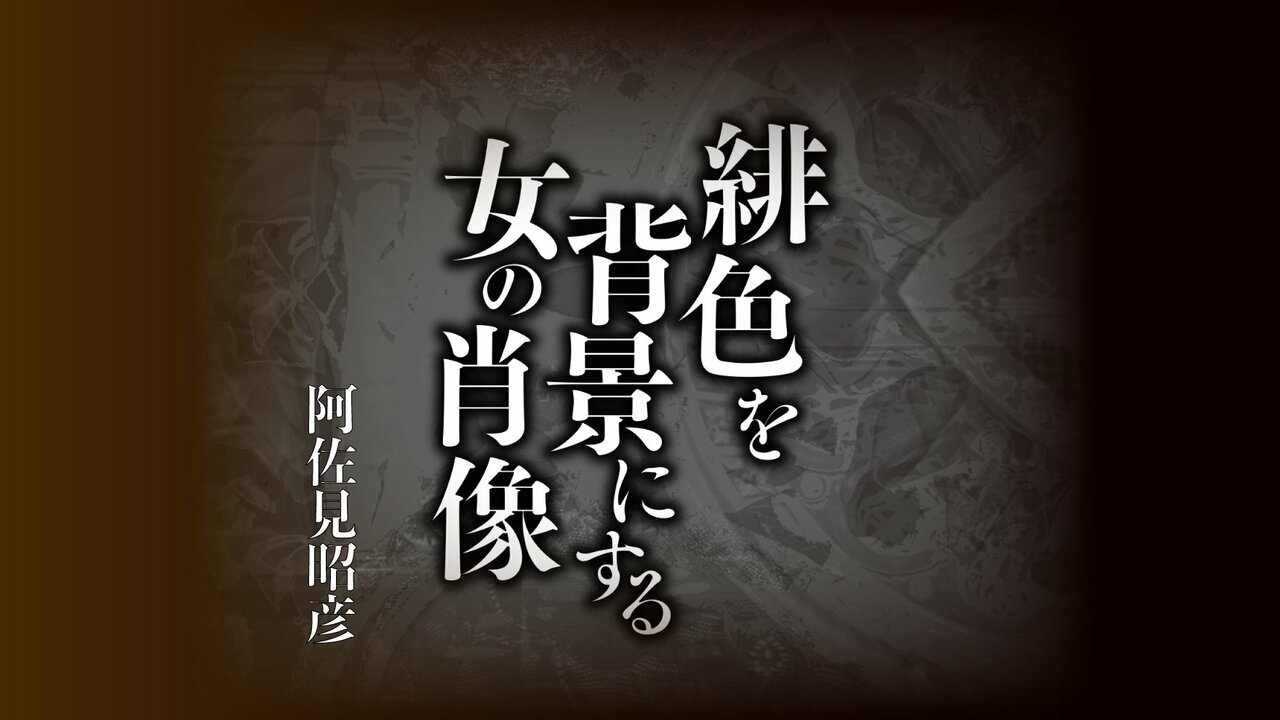3
エスプレッソは色も濃厚だが、触感もまったりとして香りも強かった。砂糖を多めに入れると苦さは消え、まさにイタリアのエスプレッソになった。この辺りはイタリア系の住人が多く住んでいる区域なのかもしれない。エスプレッソを味わいながらも、気持ちはあの美しく官能的な女の顔から一刻も離れなかった。
もどかしい気持ちに急かされるように、コインをテーブルに置いて隣のギャラリーに向かった。
Gallery Esteと、ガラスに箔押しされた框戸を引いて中へ入ると、そこはおおよそ四十坪ほどの広さの部屋で、手前半分にはさまざまな絵が十数点ほどイーゼルに載せられて陳列されていた。奥には画材や額縁が揃えられ、商品棚やケースと並んで大きい作業台が置かれている。そしてその台の上には各種のサンプルや、マットとして使われる厚紙の束などが所狭しと並べられていた。
ふと気がつくと、七十歳くらいになるのだろうか、銀髪痩身の男が店の奥からじっとこちらを窺うように見ていた。
「おはようございます。今日は良い天気になりそうですね。やはりロンドンの初夏は格別です。ところで、あちらのイーゼルに飾られている女性の肖像画なのですが……リトグラフでしょうか?」
宗像は例の絵を裏側から指差して尋ねた。すると、まるで今日宗像が、ギャラリー・エステを訪れ、この絵に目をつけることが予め分かっていたかのごとく、男は突然堰を切ったように説明をし始めた。
「リ……リトグラフではありませんが、まあだいたいそれと同じようなものです。しかし、さすがにお目がお高い。良いものに目をつけましたな。この絵はね、ここに残っている最後の一点なんですよ。しかも、イタリアの天才画家ピエトロ・フェラーラの絵ですぞ。フェラーラをご存じでしたかな?」
男はそう言いながら、イーゼルから絵を外して店の中央まで運ぶと、周囲を見回し、近くの台にそれを立てかけた。天井から吊り下げられたスポット照明の角度との関係を考えたようだった。そしていったん絵から離れて照明の具合を確認し、再度向きを調整し終えると両手を大きく広げて肩を竦めた。
一連の作業が終わったらしく、おもむろにジャケットの内側に手を突っ込んだかと思うと名刺を差し出した。
「ギャラリー・エステのコジモ・エステと申します。ええ、ここは私の店なんですよ」
差し出された名刺を確認すると、なるほどギャラリー・エステ社長コジモ・エステと書かれている。アドレスが、フィレンツェ、ヴェネツィア、ロンドンと表示されているところをみると各地に三店舗を出しているようだ。しかも本店はフィレンツェとなっていた。エステ氏は続いて店の説明を始めた。
「ロンドン店は私の画廊の中では一番小さいお店です。本店はこの何倍もありますからね、フィレンツェ最大の画廊ですよ。はい、何しろシニョリーア広場に面する歴史的な文化財の中で、商売させていただいていますから」
今度は宗像が名刺を手渡すと、それを受け取るや否やエステ氏は畳み掛けるように言った。
「ほう、日本の写真家さんですか? では芸術家ということですな、素晴らしい。ところでこちらにはどんなご用件で? どこで何を撮るのですかな?」