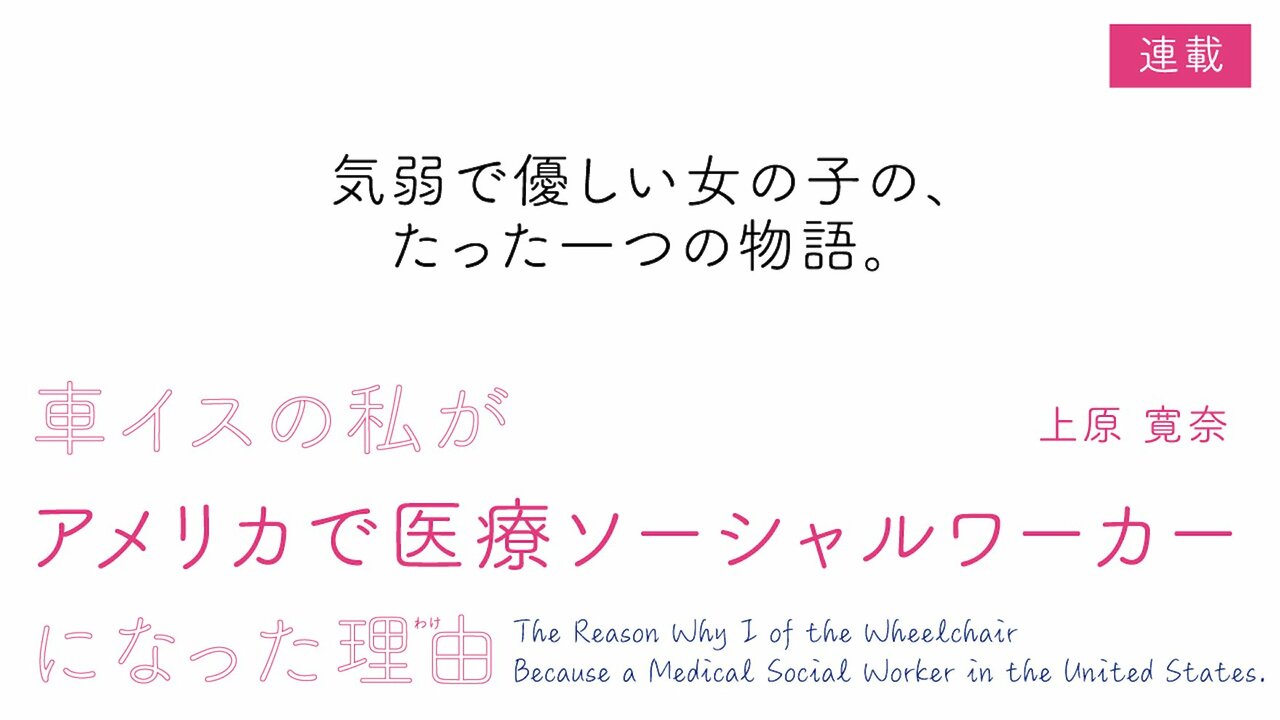【前回の記事を読む】薬の副作用で125cmで約50キロまで太り、骨ももろく歩くことが困難になった。身長も125cmで成長が止まった…
二章 大阪警察病院入院時代
「やばい、死ぬのか?」
私が警察病院に入院したのはたった五歳の時だった。私には、正直何が起こっているのか、自分の病気が何なのか全く理解できていなかった。会う看護師さん看護師さんに、「私はガンですか? 死ぬのですか?」と聞き回っていた。幼い私が、唯一知っていた怖い病気がガンだったのだろう。
谷池先生も看護師さんも両親も誰一人として、私に自分の病気についての説明をしてくれなかった。看護師さんたちときたら、「早く元気になろうね」、「頑張ろうね」などと、私にとっては理解できない宇宙人語しか話してくれなかった。少しひねくれた子供だったのだろう。そう言われるたびに「これ以上どう頑張ればええねん」、「薬もちゃんと飲んでるけど、元気になんかなれへんやん」と思い、「みんな、噓つきやんかっ」と心の中で叫び、敵意を剝き出しにしていた。
私は子供ながらに、両親の悲しそうな辛そうな表情・様子からひとつ理解したことは、私の病気はただの風邪ではなく、何か悪い病気に違いないということだった。母はほぼ毎日お見舞いに来てくれた。関節の激痛と高熱の症状がなかなか安定せず、私は「やばい、死ぬのか?」と怯えた。なにも理解できないまま、ただただ両親のために我慢して治療をしていた。
結局、自身の病気についてちゃんと理解を得られたのは、大阪大学附属病院に入院した九歳の時だった。私が発病した三五年近く前は、難病指定にされている若年性多関節リウマチで命を落とす子供たちもいたそうだ。この本を書くことを勧めて下さった河先生に、「カンナちゃんは死なんかった」とぽつりと言われたことがあった。河先生の言葉は私の心になんとも言えないせつなさを運んだ。
警察病院での生活
警察病院入院中は、祖母と二つ離れた弟が幼稚園に行くまで、三人一緒に個室で暮らしていた。“暮らしていた”というのは、四〇度以上の高熱が一日五、六回と発熱時の関節痛以外は、家と何ら変わらない環境で過ごせていたからだ。冷蔵庫、炊飯器、テレビにおもちゃに何でも揃っていた。
おもちゃは小さい玩具店より遥かに持っていたと思う。きっと両親が退屈しないように、頑張っているご褒美にと買ってくれていたと思う。入院中は病院食を食べなかったので、祖母が病棟にある共同炊事場で私のために毎日ご飯を作ってくれていた。そこにあるガスコンロの使用料が五円だったそうで、あまりの安さに驚いた。祖母が買い物に行くと私の好きなきゅうりのぬか漬けも忘れず買ってきてくれた。