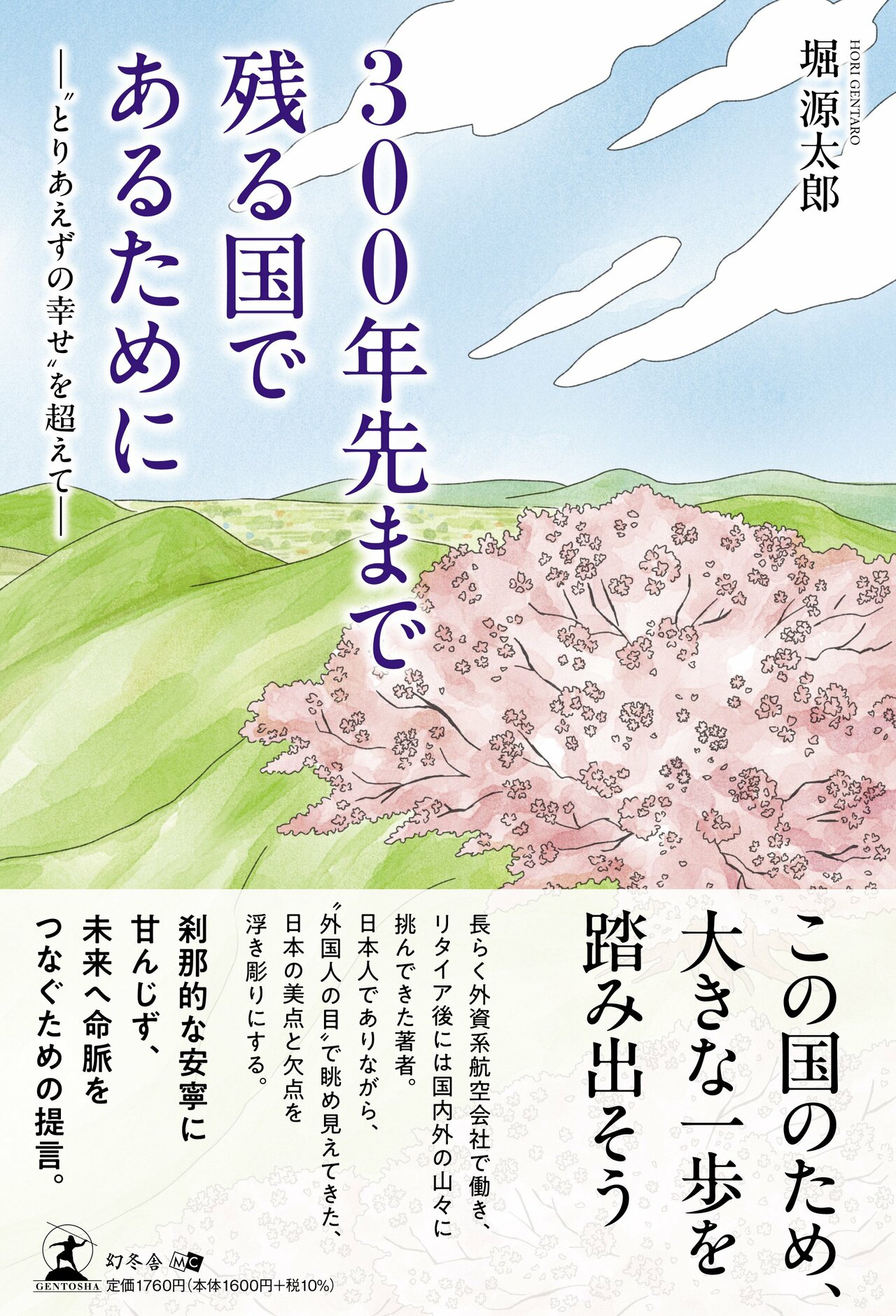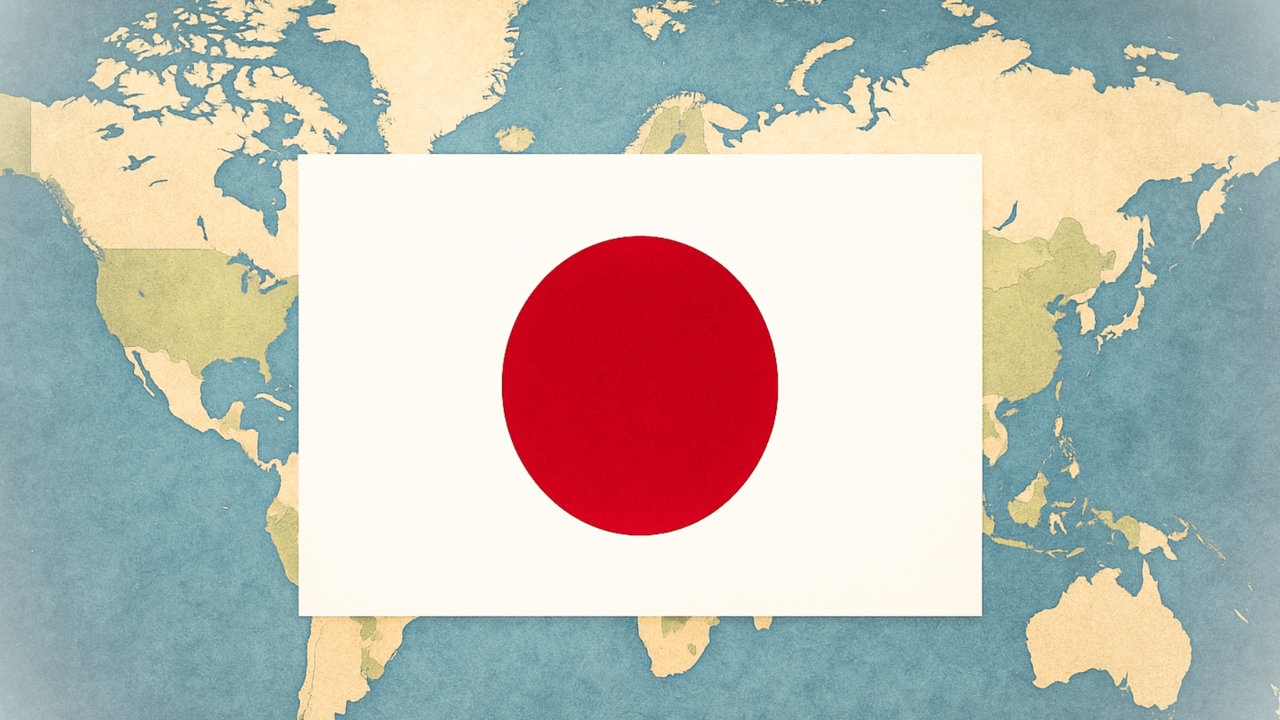差別
遣唐使以来という、2度に渡る使節団が日本から海外に派遣された。最初は、1860年(万延元年)、日米修好通商条約批准書の交換の為であった。正使の他、福沢諭吉・勝海舟・ジョン万次郎他、総勢77名の約9ケ月に渡る、ハワイ・サンフランシスコ・ニューヨーク・アフリカ・東南アジアを経由する世界一周の旅であった。
乗船したのは、米海軍所属のポーハタン号で咸臨丸が随伴した。2度目は、1871年(明治4年)から1873年(明治6年)の18ヶ月間に渡る、所謂、岩倉使節団である。岩倉具視以下、木戸孝允・大久保利通等、107名が米欧12ヶ国を旅し、スエズ運河から、アジアの植民地を経由して帰国した。
此の旅は、「文明開化」には貢献したものの、主目的であった「不平等条約」の改正は、相手国からは歯牙にも掛けられず失敗したという。これ等2度の「視察」旅行は、「蛙」が井戸の外に出た事に等しい。「蛙達」は、多くの事を見聞し、多くの事を学び、その後の「改革」に生かされた事は間違いがない。「蛙達」は、一言で言ってしまえば、「彼我(ひが)の差に驚愕」したのだ。
今の世界でも、東京から飛行機に乗ってニューヨークに行ったら、そこは、「22世紀」の世界であった、となれば、我々も、同じく「驚愕」する事は間違いないだろう。その結果、「西洋社会」に対する、憧憬が強まり、逆に「植民地化」された、国々の人々に対する幻滅や失望が高まったという訳だ。
つまり、西洋に対する憧れが、東洋に対する「差別」になったのだ。憧憬や憧れと、優越感は「裏返し」の関係にある。世に、横文字や外来語が溢れているのは、その憧れの紛れもない証拠だ。
日本人は「差別的」な国民であるかと問われれば、多くの人は「違う」と答えるかもしれない。だが、それは大いなる誤解である。殆どの人が差別する経験も、差別される経験も無いのだから「違う」と答えるのも当然の事だろう。それは、ただ単にそういう「機会」が無かった為だけである。本当は非常に「差別的」なのだ。
それは、均質的な「村社会」であったと同時に、外に出て、初めて知った西洋との驚天動地の「彼我の差」が元となったのだろう。もうそろそろ、と思うのだが、幕末以来150年以上経っても、それは未だに払拭されていないように見える。
東洋人に対する「差別」は、西洋に対する憧憬の裏返しに過ぎない。西洋に対する憧れや劣等感が払拭されて初めて、その差別意識は解消されるに違いない。
【イチオシ記事】夫の不倫現場に遭遇し、別れを切り出した夜…。「やめて!」 夫は人が変わったように無理やりキスをし、パジャマを脱がしてきて…
【注目記事】認知症の母を助けようと下敷きに…お腹の子の上に膝をつき、全体重をかけられた。激痛、足の間からは液体が流れ、赤ちゃんは…