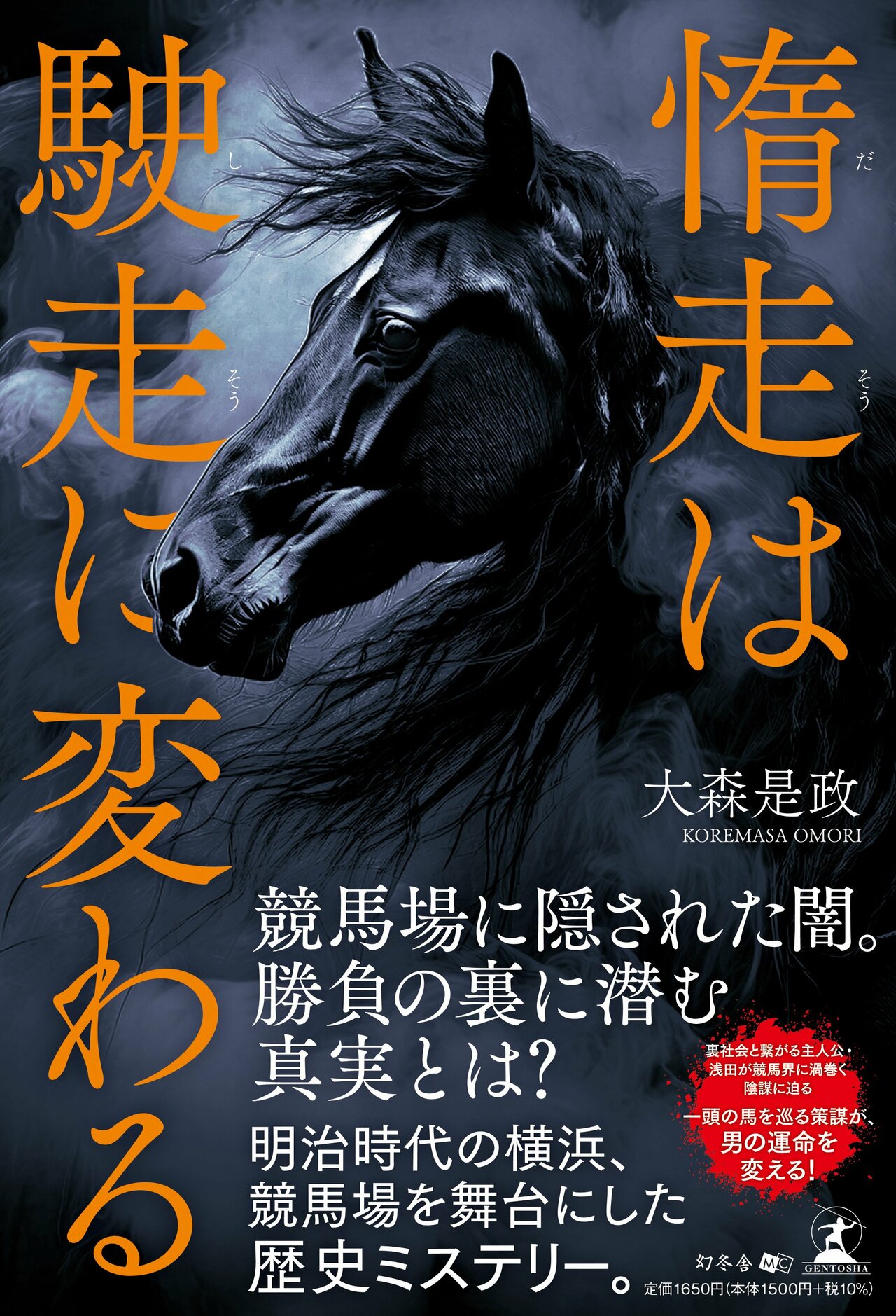「例の馬券なんですが、払戻金は前もって決められているわけではなくて、売上に応じて変わることになります。簡単に言えば、こういうことです。総売上から競馬会がテラ銭を引いて、残りの金を馬券を当てたやつらで均等に分ける。
つまり、人気の本命馬に張っても、戻りは少ない。一方で人気薄の穴馬に張ってれば、でかい。おそらく、売場には人が殺到するはずです。そのうち、博打といえば競馬ということになっても、おかしくないと思ってますよ、俺は」
「それはいいとして、賭博犯処分規則の方は大丈夫なのか?」
元号が明治になってからも、仙石一家のシノギは順調だった。商家の旦那連中の中には自分でも囲碁を嗜む人が多く、賭け碁を勉強の場として捉えていた。
そうした人たちが太い顧客として居続けてくれただけでなく、個人同士で賭けの場を持ちたいという人に真剣師をあてがうなど、シノギの幅も自然と広がっていった。
開港に伴い、横浜が急激な発展を遂げたことも好材料であったのは間違いない。資金や人手の流入により、自然と一家の上がりも多くなった。
状況が傾いたきっかけは、明治十七年一月の賭博犯処分規則の制定だった。賭博犯に限り、現行犯ではなくても逮捕は可能とし、刑法を適用せず、警察が独自に処分を下す。そうした条項が入れられていたためである。
自由民権運動に博徒が加担することを危惧しての制定だった。しかし、権力を得た警察がなにをしでかすかわからないという懸念を持っていたのは、博徒に限らない。
胴元に近い立場の真剣師は、賭け碁の場に上がるのを避けるようになり、普通の碁打ちに戻った。結果、仙石一家は、丁半博打の賭場の上がりに頼らざるをえない状況に陥っている。
【イチオシ記事】夫の不倫現場に遭遇し、別れを切り出した夜…。「やめて!」 夫は人が変わったように無理やりキスをし、パジャマを脱がしてきて…
【注目記事】認知症の母を助けようと下敷きに…お腹の子の上に膝をつき、全体重をかけられた。激痛、足の間からは液体が流れ、赤ちゃんは…