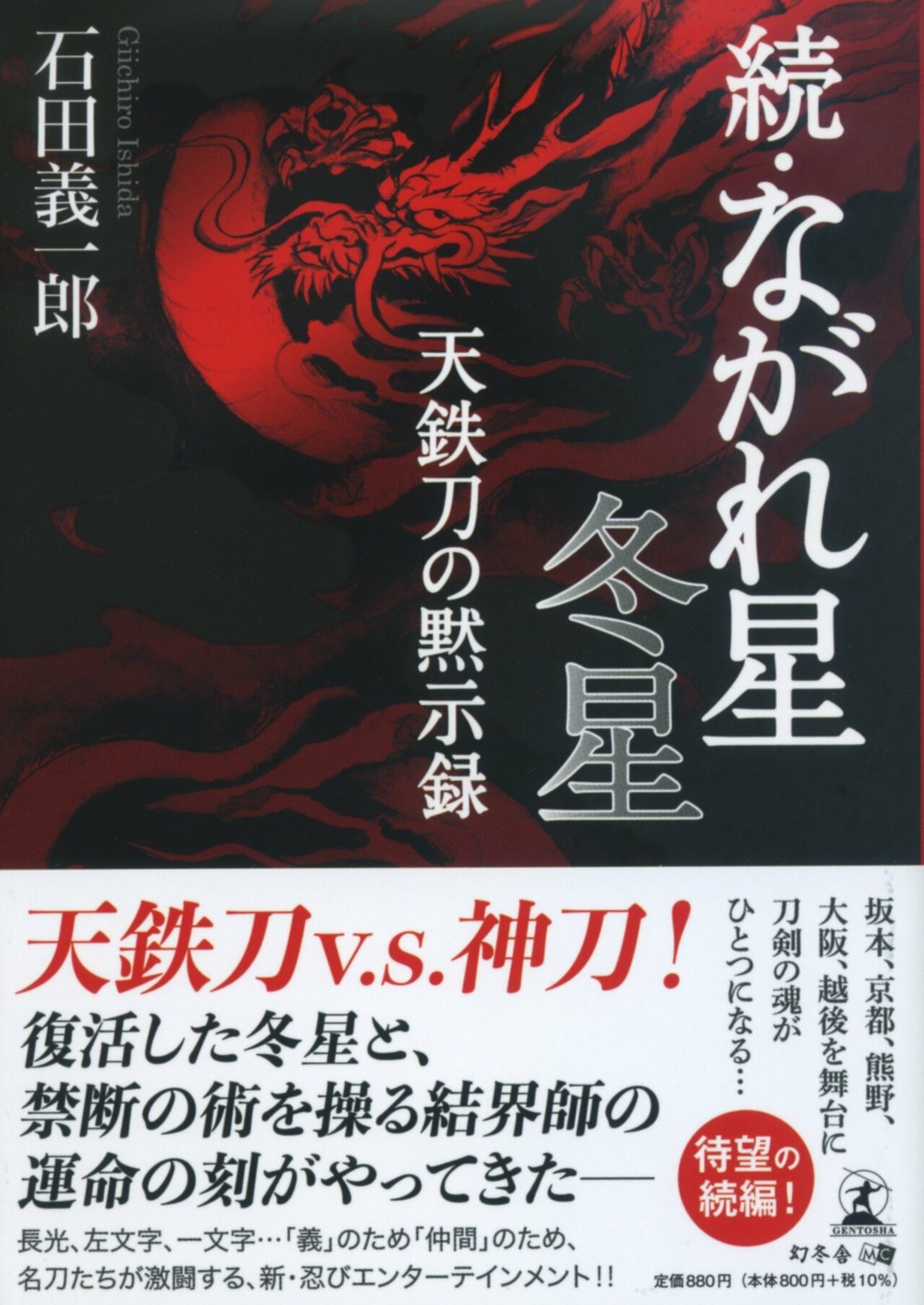ようやく目の前が明るくなり、道が開けてきた。
(やった、ついに町の入り口道にたどり着いたか!)
義近が安堵(あんど)したのもつかの間、その光景に思わず胴震(どうぶる)いした。
──道が、ない
目の前は崖(がけ)で、はるか下には川が流れている。
まさに奈落の底といってもいいほどの高さであり、ここから落ちたらひとたまりもない。
底が靄(もや)で霞(かす)んでいる。
(なんてぇことだ、あまりに夢中で走ってきたから道を間違えたのか……)
義近は、へなへなと腰を落とした。
それまで我慢していた傷の痛みが急に全身を襲いだした。草鞋(わらじ)は片方が脱げ、足の裏が血まみれになっている。応急的に止血した脇腹からの出血がひどい。
絶望の淵に打ちひしがれているとき、背後から人の足音と話し声が聞こえてきた。後を追いかけてきた、亜摩利と蘇摩利だった。
「小僧、ずいぶんとやってくれたわね。ただじゃすまないよ!」
亜摩利が肩の傷を押さえながら苦々しく吐き捨てた。
「あたいも道連れになるところだったわ。下っ端の連中は何をするかわからないね。焙烙玉で己も吹っ飛ばすとは野蛮だね──」
蘇摩利は自慢の脚力で焙烙玉の爆破寸前に逃げていた。
彼女らは義近の血の跡を目印に追いかけてきたらしく、まさに手負いの獲物を狩る猛々しい獣のようであった。