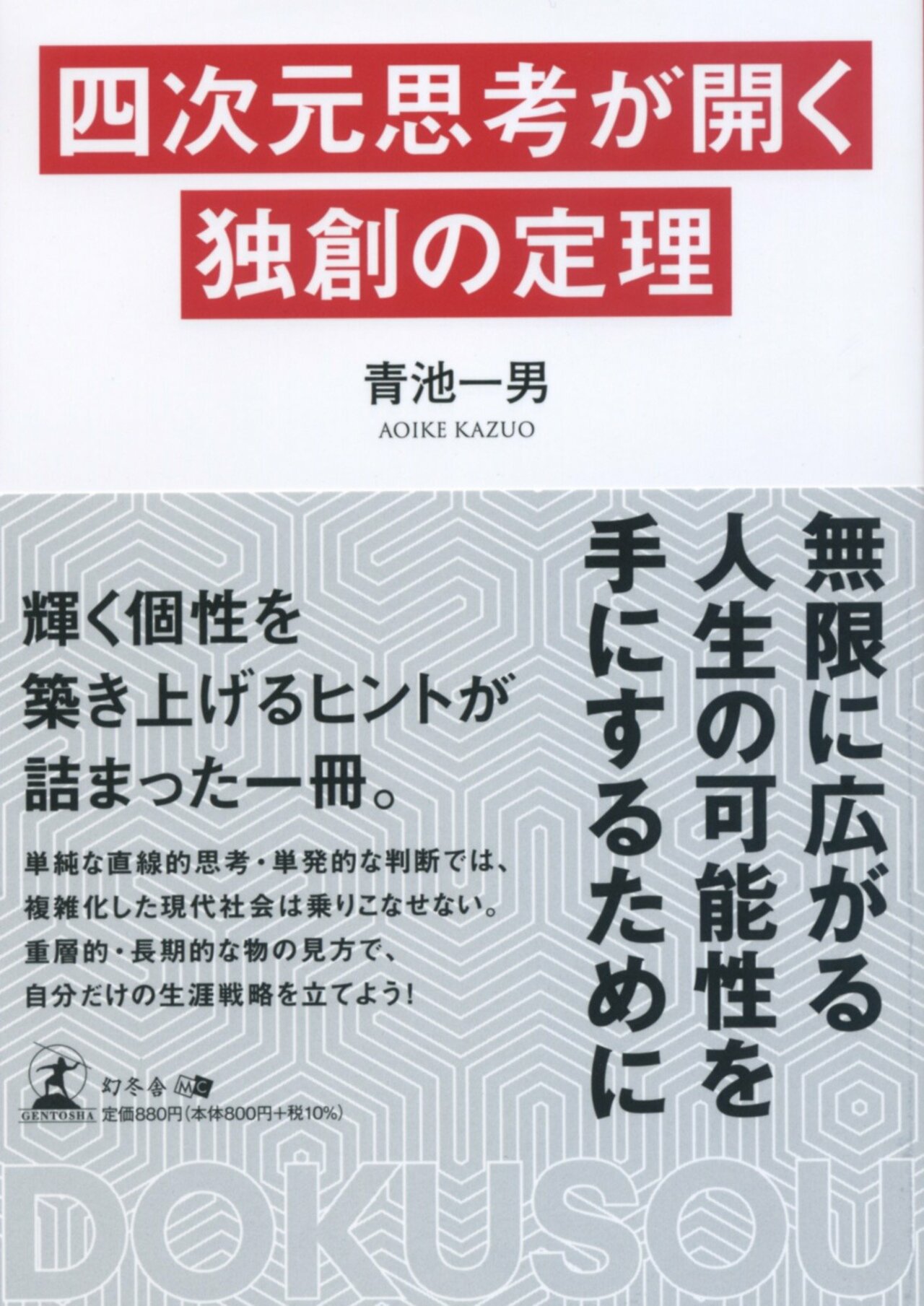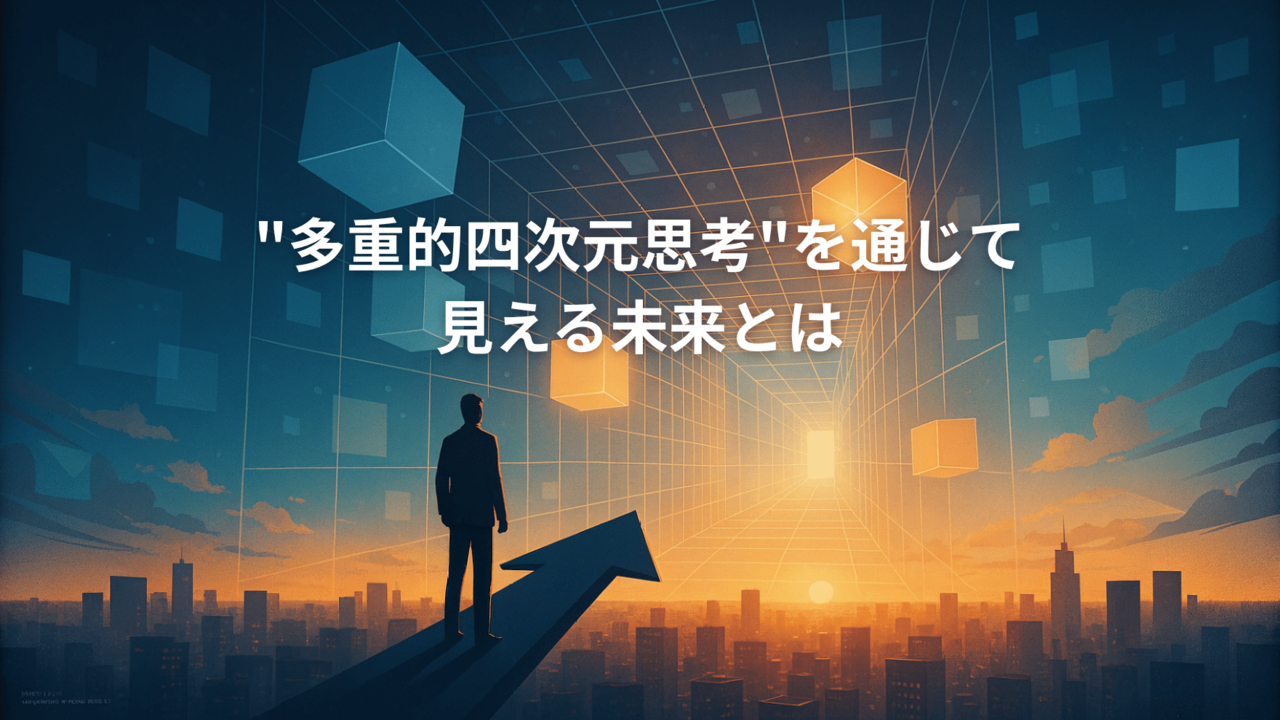国富とは
個人の成長も一国の経済成長もその原理は同じである。
経済成長を推進するものは何か。
経済学者の言葉を引用してみよう。
真の国富とは、マネーそれ自体ではなく、その国の「住民の技術と勤勉さ、天然資源とこれらを結合させる設備にある。」
アバ・ラーナー(Abba Lerner,1903年–1982年)
イギリスで教育を受け、1939年からはアメリカ合衆国に移住。 生涯を通してケインズ経済学を一貫する形で活動1
「富を生み出す力」は、富そのものよりも無限に重要である。
フリードリッヒ・リスト(Friedrich List,1789年–1846年)
ドイツ人経済学者。
ナショナルイノベーションシステムなどいくつかの理論を発展させた2
▼成長産業を生めない日本企業
日本企業の産業破綻の象徴としてあるのは、なんといっても「東芝」であろう。
日本のインフラ整備と家電産業の中心であった名門企業である。売上高の半分以上は電力会社や自治体、防衛関連、サービスであり、原発輸出であった。
米原子力ウエスチングハウス(WH)社関連で1兆円の減損処理を強いられた。現在もその影を引きずっており株式市場は未上場の状態にある。国策会社的な面はあるにしても経営統治不全が多く指摘されている。
DRAM全盛時代は5割強のシェアを握っていた半導体産業ではあったが、基本特許を米国勢に押さえられ韓国、台湾との価格競争に敗れ次々と撤退に追い込まれた。
東芝が自ら開発したNAND型フラッシュメモリーであったが韓国サムスン電子に特許を供与したため、逆にサムスンの巨額投資にあい、東芝はひさしを貸して母屋を取られた状態となった。
その他のメモリー、リチウムイオン電池、青色LEDなど同じ轍(てつ)を踏んでいる。これに輪をかけたのが「選択と集中」である。
集中といっても市場優位性に疑問のある商品に選択を行っても利益を創出できないでいるのである。ある面で東芝問題は日本企業全体の問題なのである。
1 中野剛志『国力とは何か』講談社 2011年 188頁
2 中野剛志『国力とは何か』講談社 2011年 188頁