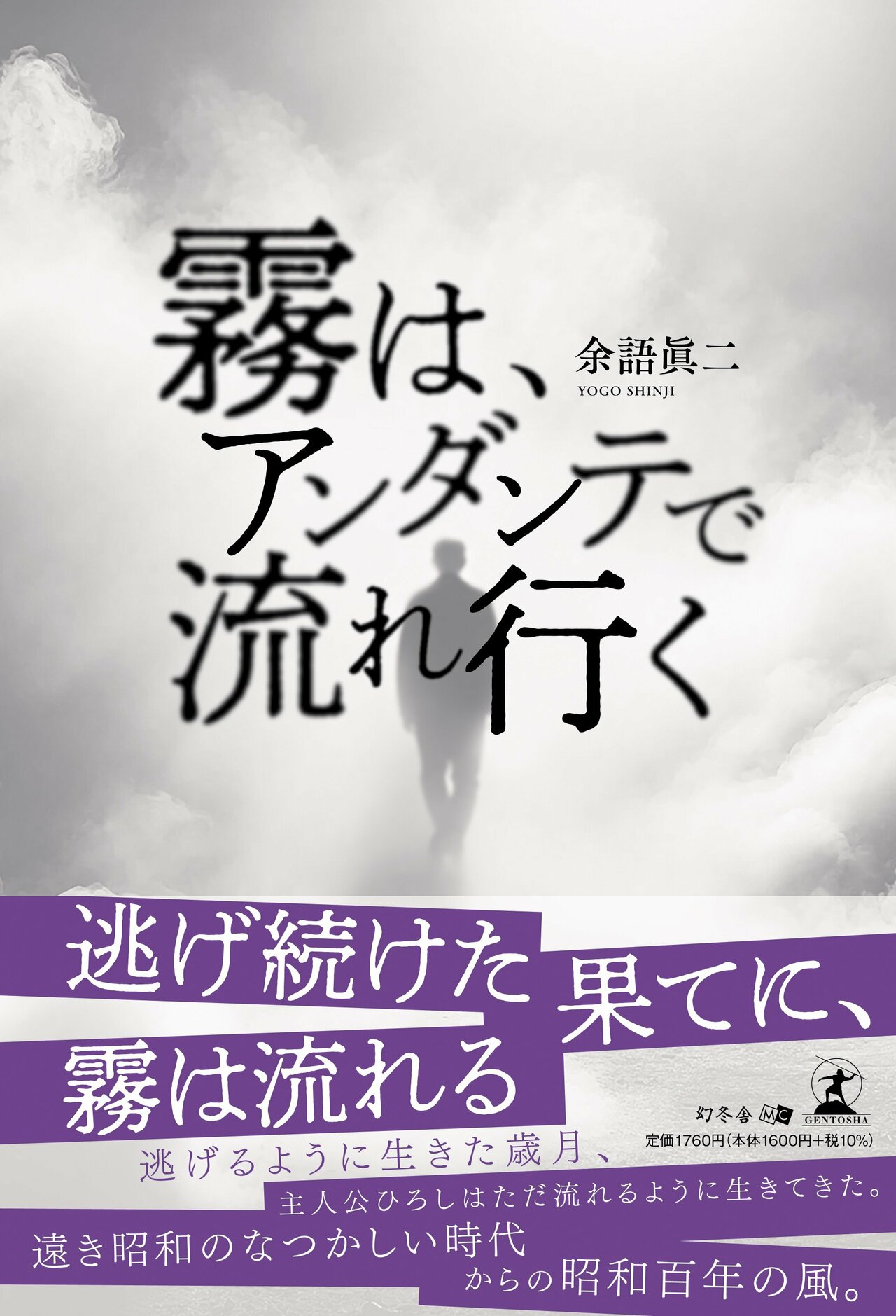小学校から帰ってくると縁側には花瓶にすすきが生けてあり、その横にだんごと芋の煮っ転がしが置いてある。
「今日はお月見なんだ」
「そうよ、中秋の名月ね、まんまるお月さまの日だね」
母が静かにつぶやいた。
夜空に風がさやかに流れていた。
ひろしは、あの夏の水晶山の出来事を母に秘密にしていたが、なんとなくこのとき話してみた。すると母は、ガキの喧嘩と関係あるのかないのかわからないような話をし始めた。
「かあさんはね、日本が戦争に負けてよかったと思ってるの。戦った兵隊さんたちのことを思うと、そんな気軽には言えないけど。戦って勝っても、次はまたどこかの国と戦う。負けた人々の憎しみと怨みの連鎖が始まり、いつまで経っても平和にならない。憎しみと恨みの繰り返しだから、負けてよかったの。
みんなが負けて、それでもう勝とうと思う人がいなくなれば良いと思う。母さんのお母さん、ひろしのおばあちゃんがいつも言ってたのよ、『負けるが勝ち』って。勝ったり負けたりしてたら、憎しみや恨みはいつまでも続くもの。人の世のことだって負けるが勝ちよ」
ひろしが小学校に上がる頃、祖母は亡くなっていた。母は何故か、あまり帰省をしたがらなかったので、祖母の葬儀の後はもう帰省はしなくなった。
少し変わった人だった祖母によく暗唱させられた五言律詩(ごごんりっし)を、長い間、ひろしは覚えていた。スラスラと暗唱できたのは、高校生ぐらいだろうか。
国破れて 山河あり
城春にして草木深し
時に感じては 花にも涙をそそぎ
別れを恨んでは 鳥にも心を驚かす
意味もわからず、祖母に大声で唱和させられた。高校の漢文の教科書にも杜甫のこの「春望」が載っていたが、授業で教わった解釈にひろしは違和感を覚えていた。
「国破れて山河あり 城春にして草木深し」――長春の春に国は破れ、人生のはかなさ、散り際の潔さを悠久の自然の不変性や回帰性を肯定的に捉える解釈に対し、ひろしは人の営みと自然界の理不尽な天災や戦いが、人に自然現象の虚しさや儚さ、戦の残虐さを長い歴史の中で捉える意味があるのではないかと勝手に思っていた。
あの頃、よく祖母に「おてんとうさま」の仰せの通りにしなさいと教えられた。
「天命に導かれて国を治めなければ、この世はだめになります」
祖母が言い残したことはこんなことかなあと、ひろしは後になって思い浮かべたことがある。
そして、祖母が切ってくれたよく冷えた西瓜を腹一杯食べたことを、暑い夏になると思い出す。