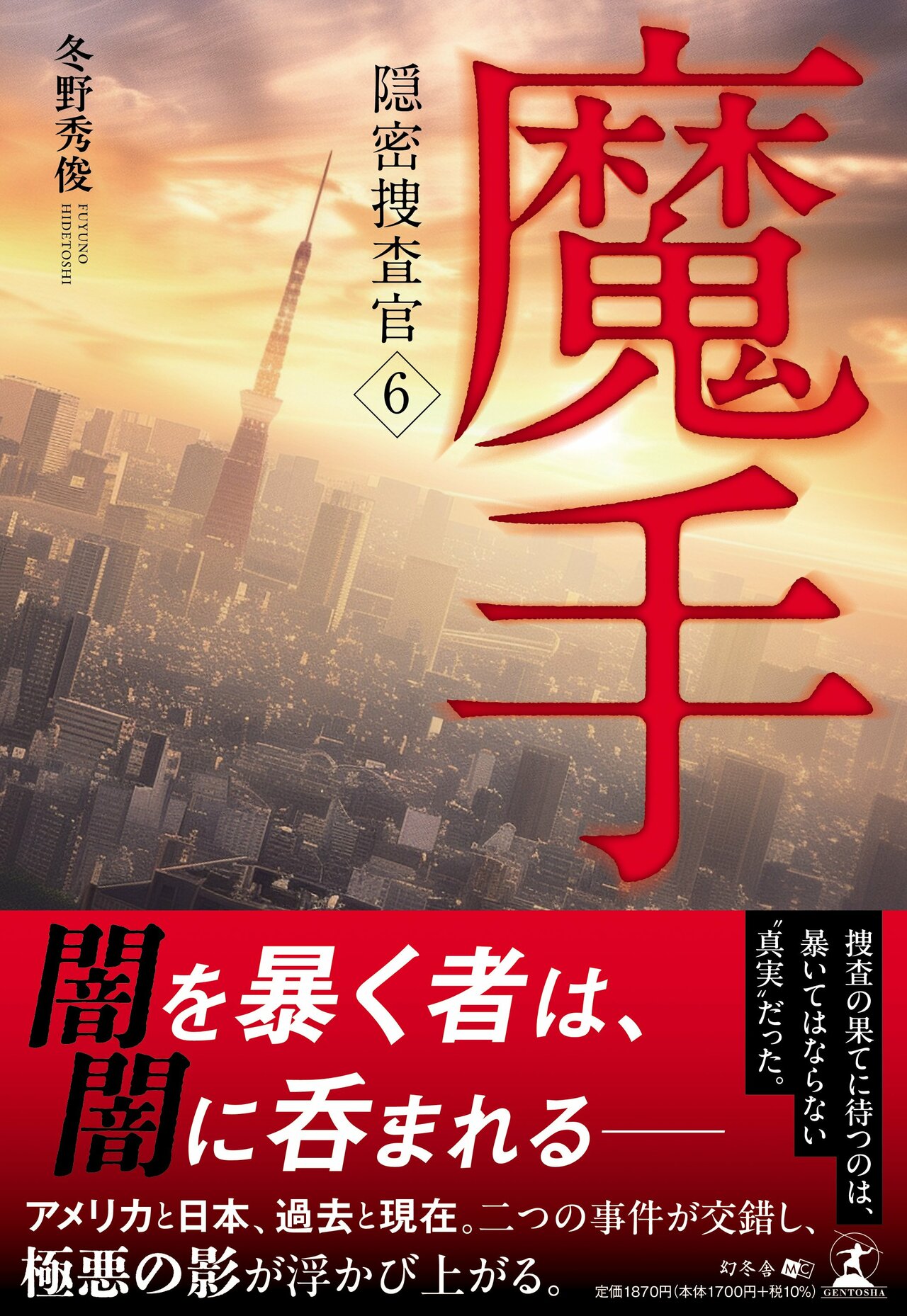【前回の記事を読む】「危ない!」急に抱きつかれ無言のまま周囲を見回した。注意してみたが2人に危険が及ぶようなものは何もなかった…
(一)
ホテルに着いた二人がとった行動は、正反対のものだった。軽くシャワーを浴びた清一が、一階のフロアーのラウンジでゆっくりと寛いでいるのに対し、スージーは警戒のための準備に余念がなかった。
二人が市場広場の山手にあるステーキ店を訪れたのは、十九時少し前だった。スージーが予約していたこともあって、さほど待つこともなく、男性従業員が店の奥に案内してくれた。四人掛けのテーブルは、薄暗いランプの中を行った一角にあった。
席に着いた清一は、成程と思った。ホテルでは派手に見えた赤いドレスが、天井の照明とテーブルのランプの灯の中で、とてもエレガントに見えたからだった。
「清一さん、偶にはゆいさんと出かけたりしないの」
ここでは仕事抜きだと言わんばかりのスージーの質問だった。ゆいは、清一の再婚相手だ。先妻の明子が亡くなった後、清明(きよあき)と有(ゆう)という二人の子供を抱え、絶望の中にいた清一を救ってくれたのが義姉のゆいだった。
「なかなかそんな時間は」
遠くの照明に視線を送っていた清一が、目の前のランプに視線を移して言った。その言葉には、刑事には家庭が犠牲になるのは宿命、至極当然という思いが滲み出ていた。事件の捜査にのめり込むタイプの清一にとって、家庭崩壊は充分現実的なものだったが、ゆいがそれを阻止してくれていた。
「そうそう。お母さん、早ければ年内、遅くても来春までには、帰国できそうよ」
スージーが、タイミングを見計らったように言った。
「えっ、だけど」
「多分、そうなると思うわ」
「それは、既にアメリカにいるということ」
と言って、清一が身を乗り出した。
「これ以上は、たとえ清一さんでも無理。ごめんなさい」
スージーが、微笑みを浮かべて言った。それから、徐にテーブルの上に置かれた清一の手を包み込むと、テーブルの下へ誘導した。スージーの怪しげな動作は、しばらく続いた。その間、二人は見つめ合ったままで一言も発しない。そして、清一の目が和むのを待っていたように、スージーの手が離れた。
「清一さんのこと、気の毒だと思う。でも、もう少しの我慢」
「気にかけてくれて、ありがとう」
そこには、落ち着いた顔の清一がいた。
最初、清一はスージーがとったなまめかしい行動を理解できなかった。それは、心が熱くなる男女の行為でないことは百も承知していたが、スージーの意図するところが分からなかった。けれども、二人の手がテーブルの下で再び結ばれた後で行き着いたのは、盗聴器だった。
スージーは、テーブルの下に仕掛けられた盗聴器にいち早く気づき、愛の囁きにも似た行為で清一に伝えたのだった。