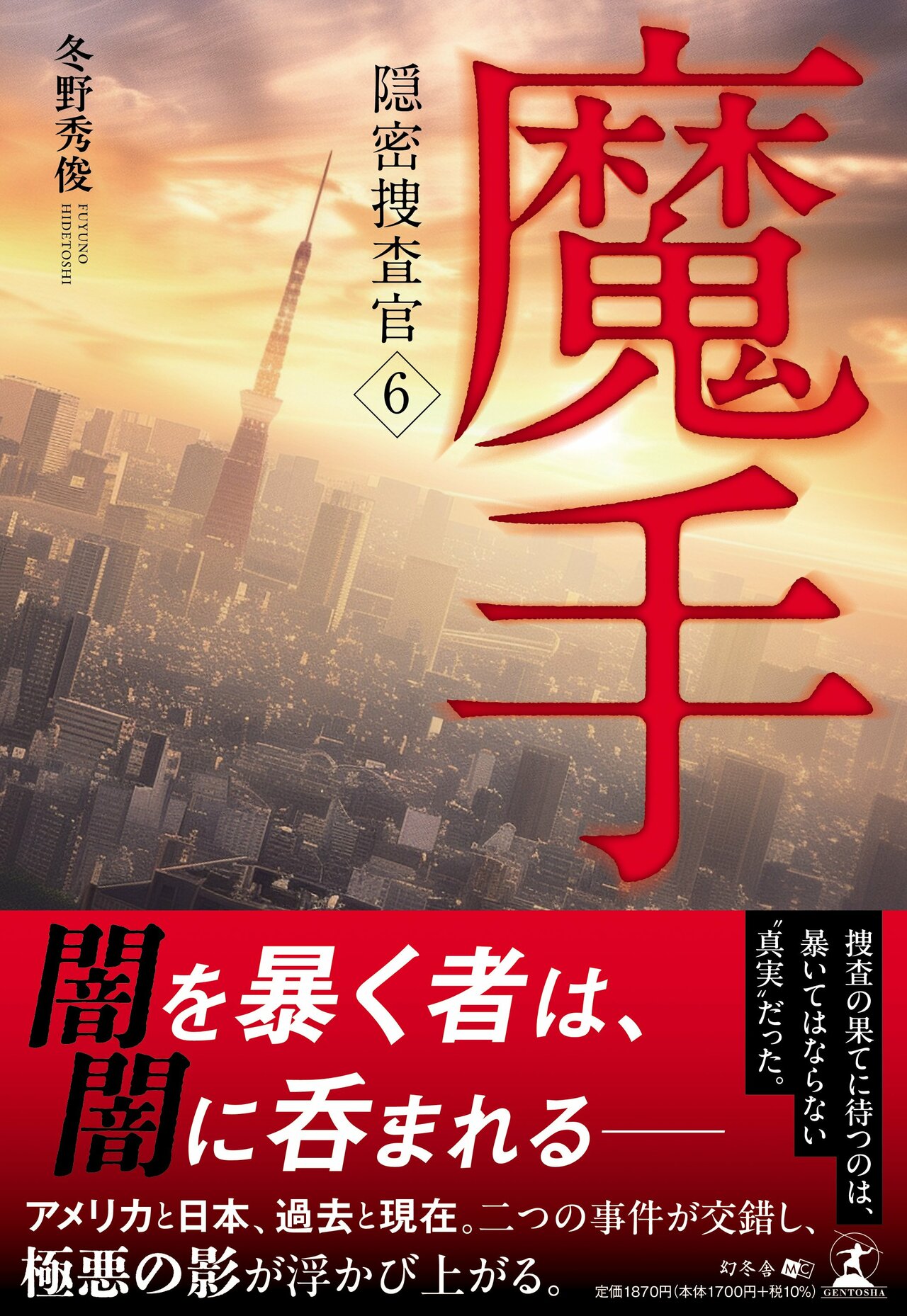その後も二人の会話は、盗聴器の存在に臆することなく続いた。それから、運ばれてきた厚さ五センチほどのステーキに舌鼓を打つと、店を後にした。
ハリオットホテルに戻った二人は、一階ロビーにあるバーで会話を続けた。
「ここなら安全かも」
着席すると、スージーが言った。バーはフロアーより一段低い場所にあったが、視界を遮っているのは数本の柱だけだった。
「それで」
それは、恰(あたか)も呼び水のような一言だった。
「加担しているとは思っていないわ。ただ、技術が悪用されているのは、間違いないわ」
スージーはここに至っても固有名詞を使用しなかった、あくまで物事を慎重に運ぼうとしているようだった。
「そう」
と、清一は短い返事をするしかなかった。清一の母が開発した薬品が軍事転用される恐れがあることは知っていたが、多方面に応用が利くものだとは想像していなかった。アメリカが、自国の優位性を確保するために、清一の母が開発した薬品を監視下に置こうとしているのは間違いのないところだった。
話が一段落すると、二人は十五階にあるプライベートルームへ向かった。二十二時前ではあったが、多忙な一日だったので疲労感が漂っていた。けれども、真夜中に熟睡を脅かす物音が襲った。
それは、コツコツと壁をノックする音だったが、清一が壁に耳を当てると呻(うめ)き声を伴っていた。清一はズボンに片足を突っ込みながらスージーの部屋へ急いだ。このような時にはすぐ行動しなければ悔しい思いをしたことが多々あったからだ。