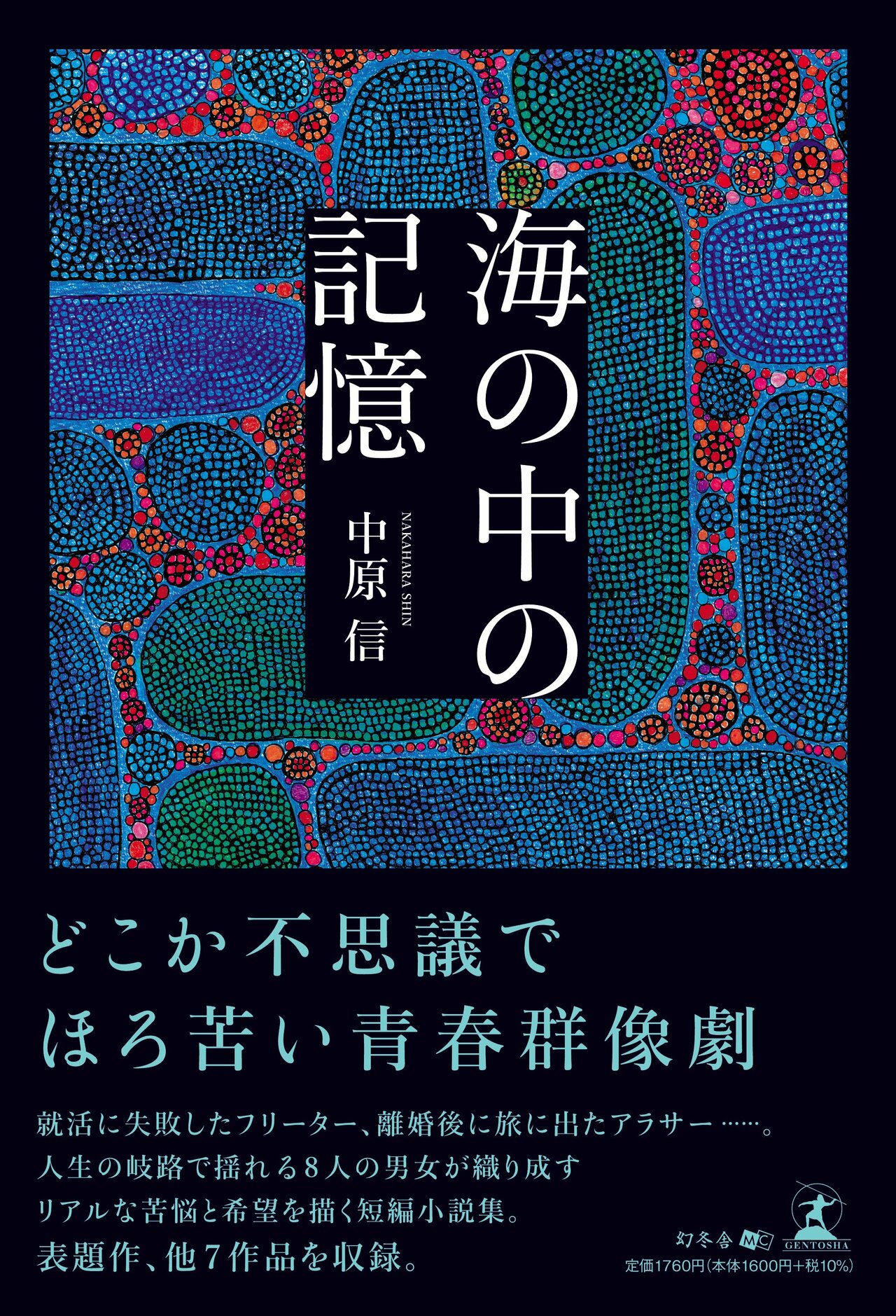一九八〇年、ジョン・レノンを暗殺したマーク・チャップマンが、『ライ麦』の愛読者であったことが明らかになり、サリンジャーはたいへん苦しんだと言われる。
認知の歪みを生じさせやすい人間が抱く、ある種の幼児性とテロリズムは、表と裏の関係にあるのかもしれない。
教授がいつだったか言及していた「説得力」とは、サリンジャーの戦争体験だとわかるが、当時はまだその正体が何であるか、ピンと来なかった。今なら、その「説得力」を要求する男たちの論理(ロジック)もよく見えている。
ただ、教授は、口頭試問の途中から、サリンジャーの主題から外れに外れて、『ライ麦畑の捕手』とともに、『ハックルベリーフィンの冒険』が州によっては、禁書扱いになっていると憤慨し始めた。
論文とは関係ない話を延々と聞かされ、私の卒論に関わる口頭試問は、ようやく終わった。
卒業式の日、私は就活用のスーツを着て一人で出席した。夜、母から電話があり、心から喜んでくれた。高卒の母にとって、四年制大学を卒業することは、夢だったという。母の世代にあって、英文科卒の才女は憧れの的なのだ。
出版社の入社試験に落ちたことは、正直納得がいかなかった。
こんなことなら、北海道の中学校か高校で教員になるべく、教員免許を取っておくべきだった。
そうでなければ、お見合いをして牧場経営者の息子と結婚する、という選択肢もあった(私には荒唐無稽に思えるが……)。
しかし、出版の仕事をしたいという気持ちは、むしろ落とされた後に高まっていった。