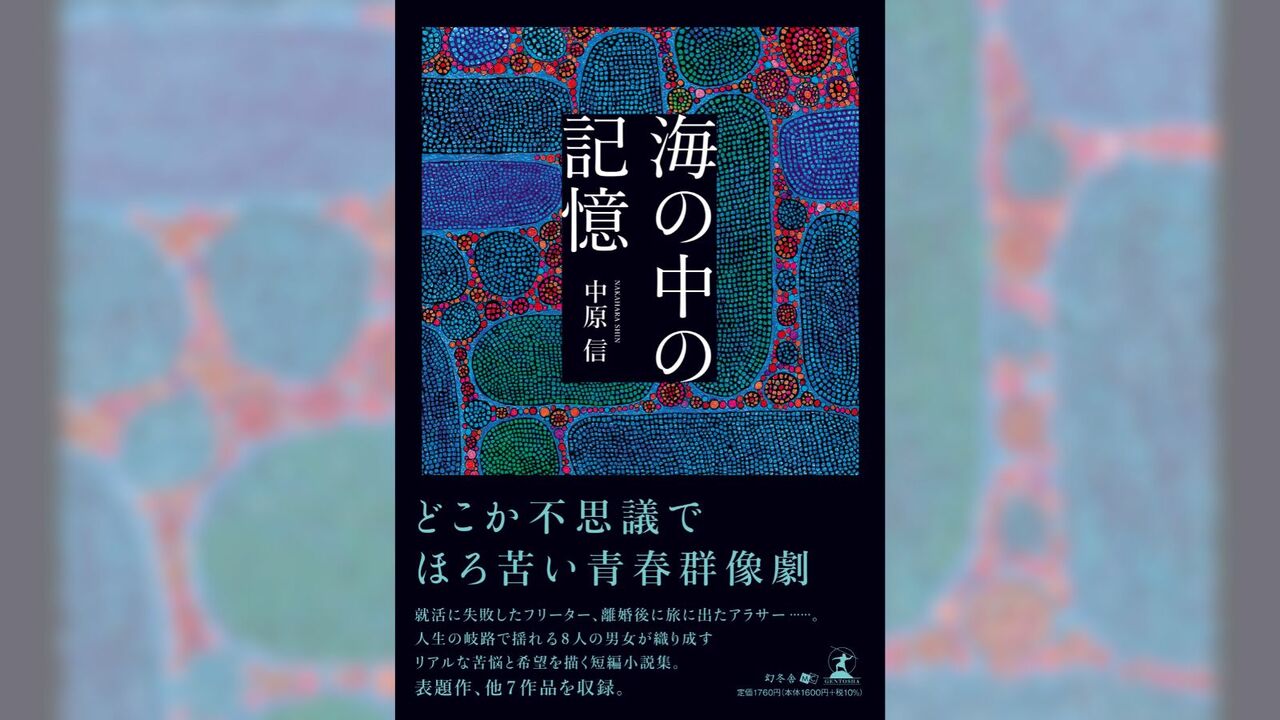【前回記事を読む】冷戦下の過激な『スパイ狩り(マッカーシズム)』を非難したサリンジャー。作品に宿る、平和な現代を生きる若者には伝わりづらい「説得力」とは...
アメリカ文学
「大丈夫?」
Kは優しく声をかけてくれた。全身から力が抜けてしまった私は、赤ちゃん返りした子どものように甘えたくなり、Kに私の体を支えてほしいと頼んだ。
「あの、とても気分が悪いの。私のアパートまで遠いから、あなたの部屋で、二、三時間休ませて……」と私はKに懇願した。Kは頷いて私を介抱してくれた。
Kのアパートは大学のすぐ近くにある。Kは自分の部屋のソファに私を寝かせた。洗濯してあると思われる大きなタオルでクッションを包み込み、それを枕にして、私の頭の下に置いてくれた。客用と思われる花柄のタオルケットを、寝ている私の上にかけてくれた。
力を失った私はそのままぐっすり眠ってしまった。
目が覚めると電気は消えていた。静かな木造アパートの一室にあって、真夜中、私とKは二人きりだ。Kは仰向けの姿勢でよく眠っている。私は枕元に寄ってKを見つめた。昼、精悍な大人の顔になったと思ったが、寝ている時は子どものようだ。
私はKの唇にそっとキスをした。
最初で最後のキスだと思った。
Kは目を覚ますことはなかった。寝返りを打って、英語で寝言を言っている。私は足音を立てないように注意して、アパートの部屋を出た。
日が昇る時間まで、まだ二、三時間ある。電車やバスは動いていない。ひっそりと寝静まる街。川に突き当たった。堤防沿いを歩く。橋は遠い。貨物線用の鉄橋がある。私はこの線路の上を歩いた。
人はどこにもいない。橋桁の下、川面は揺れている。真っ黒だ。薄曇りで星はほとんど見えないが、月はぼんやり見える。
足下に目を移す。川の上に映し出された月がたゆたっている。空にある月は朧気だが、川の月は空より線がしっかりして見える。
鉄橋の真ん中あたり、私は一人ぼっちだった。急に涙が溢れ出てきた。静かに、ただただ流れ出た。傷つけられた動脈から血がどくどくと出ていくように、夥しい量の涙が両眼から出てきた。
声が出ない。涙が出ることは、自分の体に起きていることなのに、他人の体のような感覚になった。
私は寒気がして、布製の薄汚れたショルダーバッグの中に詰め込んであったパーカーを出して身に着けた。
鉄橋の終わり、私は対岸の堤防の上に上がり、天井河の堤の階段のあるところで道路に降りた。そこからどんな道を通って、自室に戻ってきたのか、よく覚えていない。ようやく家にたどり着き、ベッドに潜り込み、寝てしまった。ひどく疲れていた。