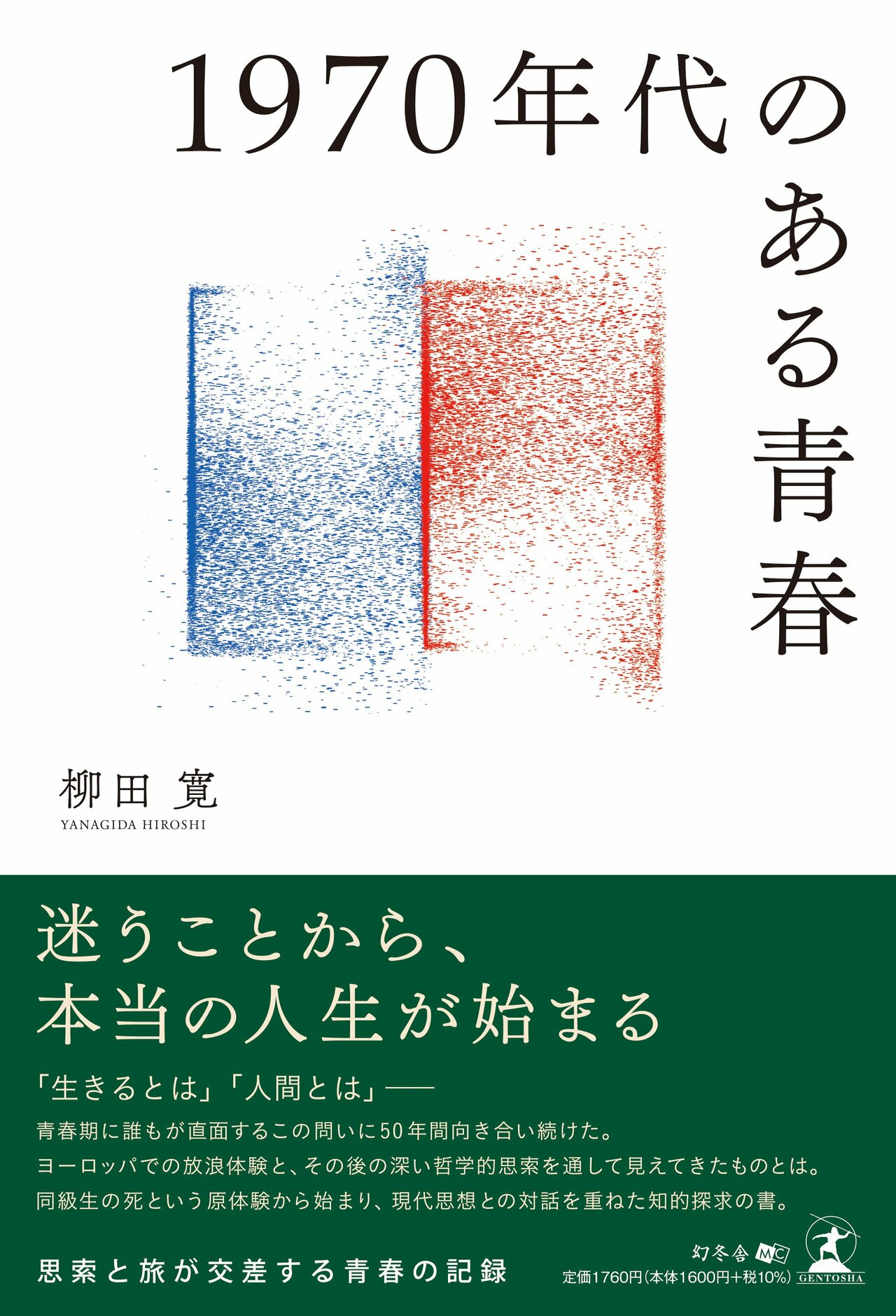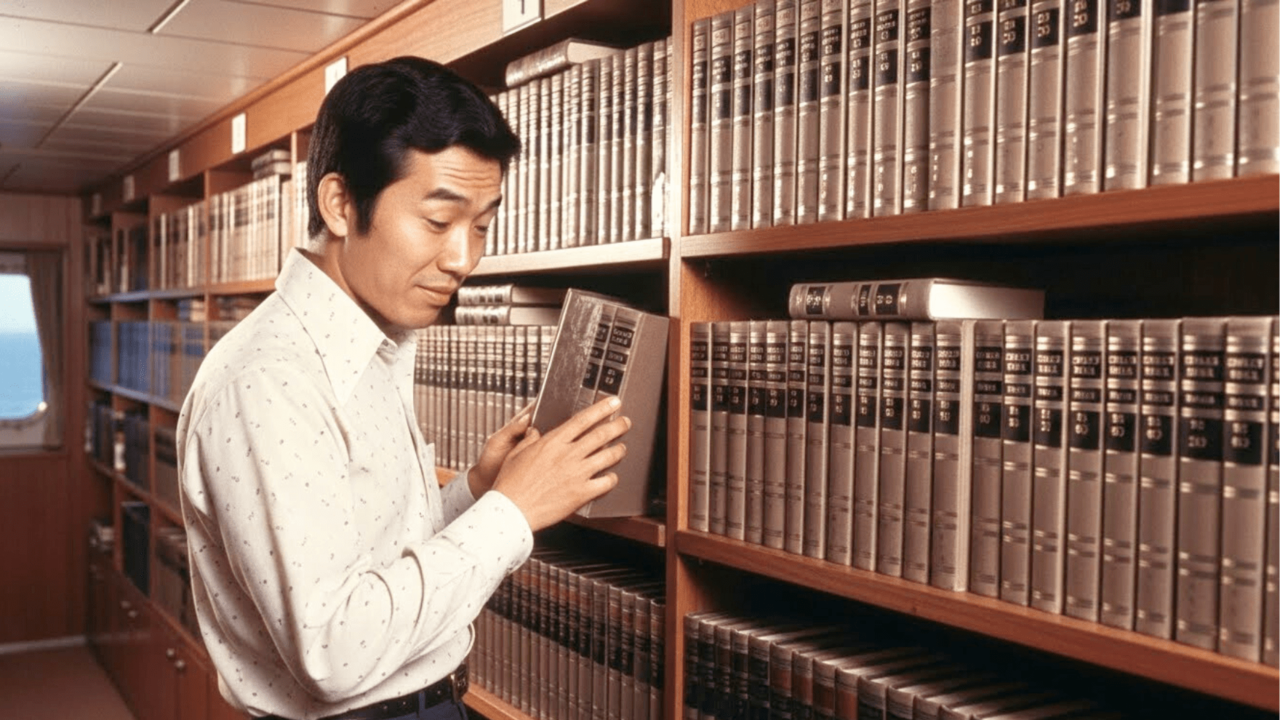それは、母親と息子の会話であったが、息子がテーブルに食器を揃えるべくスプーンを取り上げた時にそれを落としてしまい、その時、彼が「Oh, la cuillère!」と叫んだのである。そのスプーンに対応するフランス語の響きが耳に飛び込んできた時に、その響きが単なる言葉としての響きを超え、とてつもなく典雅なものに聞こえたのである。
これはあくまでも個人的な体験であり、他の人にはいささかの説得力を持たないものであるが、大袈裟に言えば私にとっては一つの啓示に等しいものであった。この体験がフランス語を真剣に学ぶきっかけとなったことは確かである。
第二外国語はドイツ語を選択していた。というのも、当時、北大を受験する際にはあらかじめ受験票に希望する第二外国語を指定しなければならなかったからである。法曹界ではないが、法学部での勉学を必要とする将来を考えていたので、法学部へ行くならドイツ語という偏った先入観があった。
入学後の教養課程ではクラスのほとんどの学生が、法学部へ移行するという雰囲気のなかでドイツ語を学んだ。その時、二人のドイツ人教師が日本人の教師の他に担当されていたが、その体形にゲルマン民族の屈強さを見て驚いたものである。
2メートルはあろうかと思われる身長とがっしりした体形に、これではフランス人のようなラテン系の人物では身体的には太刀打ちできなかっただろうと素直に思ったものだった。
一通り文法を学んだ後、講読ではモーツアルトのオペラ『魔笛』を読まされたが、ドイツ語の響きそのものにはそれほど惹かれるものはなかった。それでも英語以外の外国語を学ぶことには興味があり、特別熱心な学生ではなかったが、休むことなく授業には出ていた。
しかし、大学紛争で授業がなくなってから異変が起きた。というのも、学生運動家たちにより教養部が閉鎖され、授業がなくなってから、私は無性に小説を読みだしたのである。
ずいぶんと遅いスタートであったが、日本を問わず海外の小説や詩集を興味の向くままに読み漁った。とりわけ、カミュの『異邦人』で描かれている世界、主人公のムルソーの世界に対する立ち位置に自己の分身を見る思いがあり、また、ボードレールの散文詩「異邦人」に波長が合うものを感じたのだった。
【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…