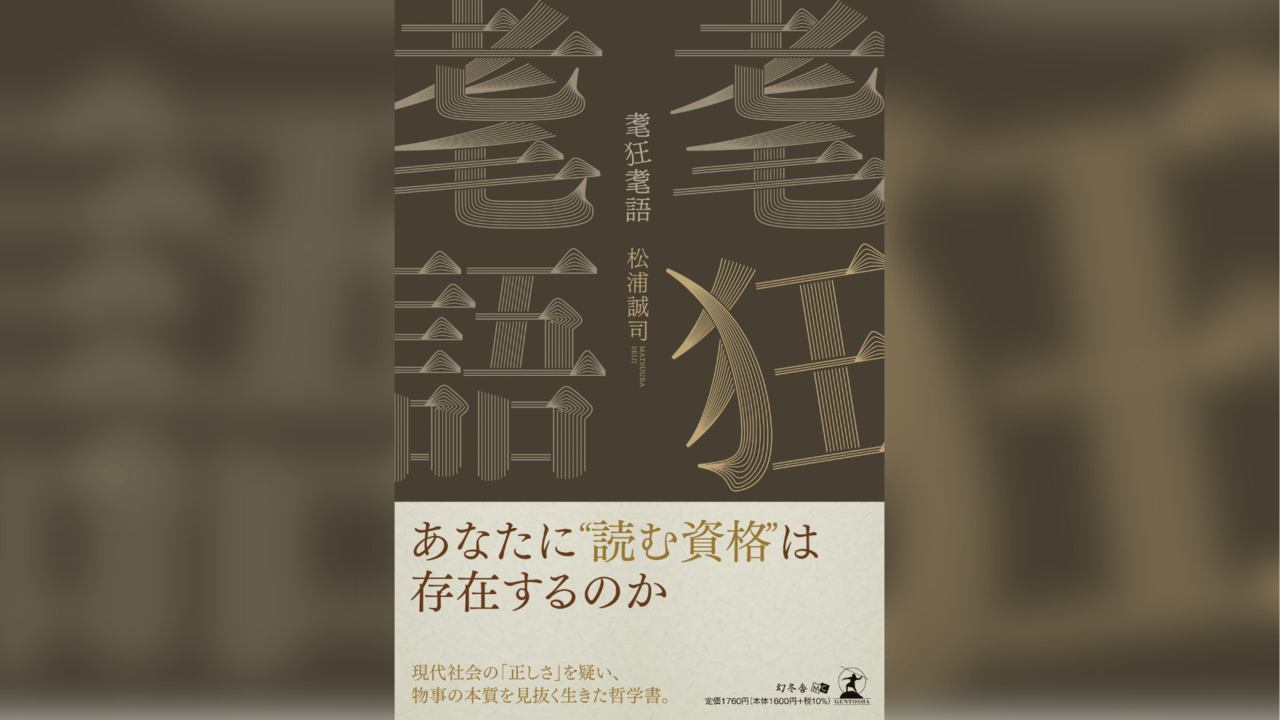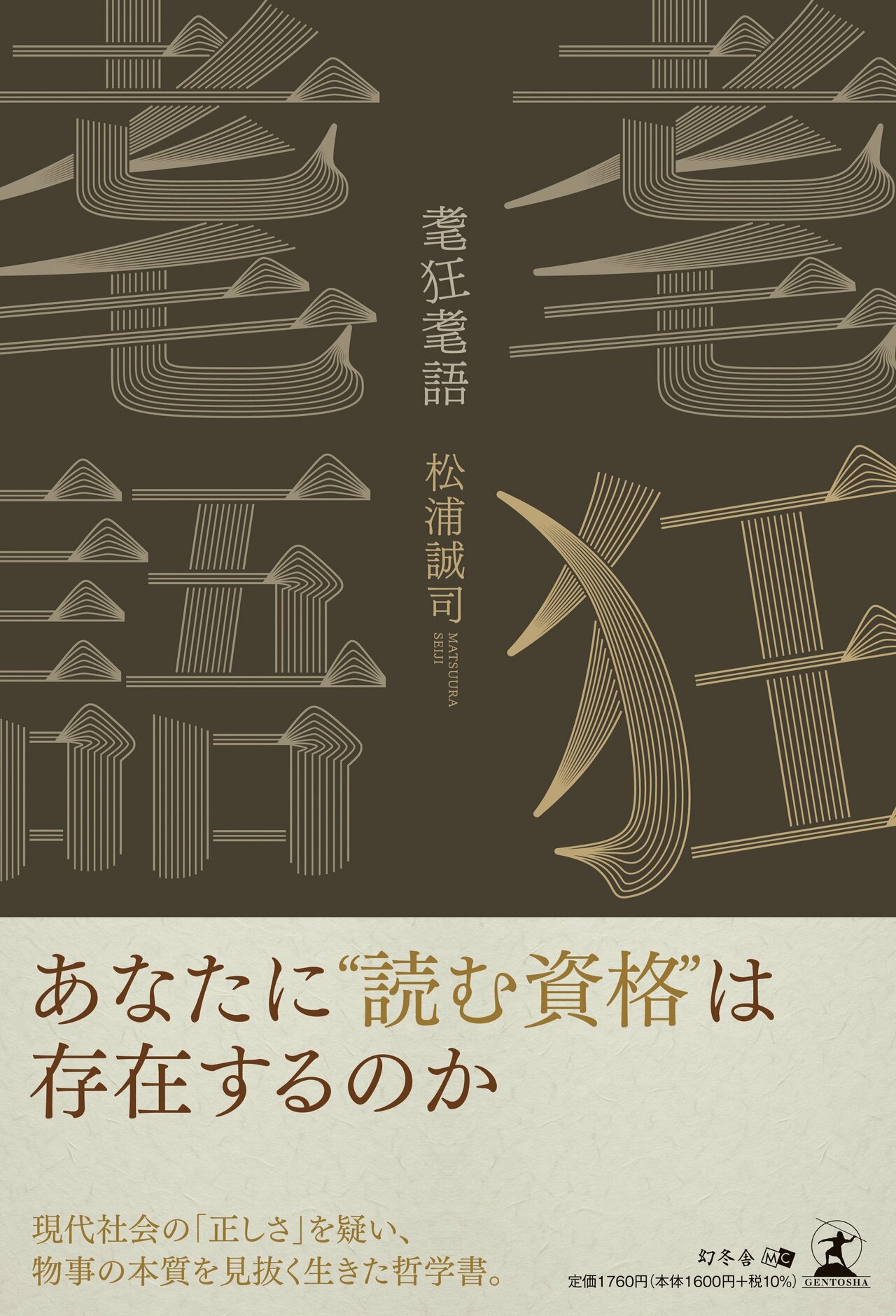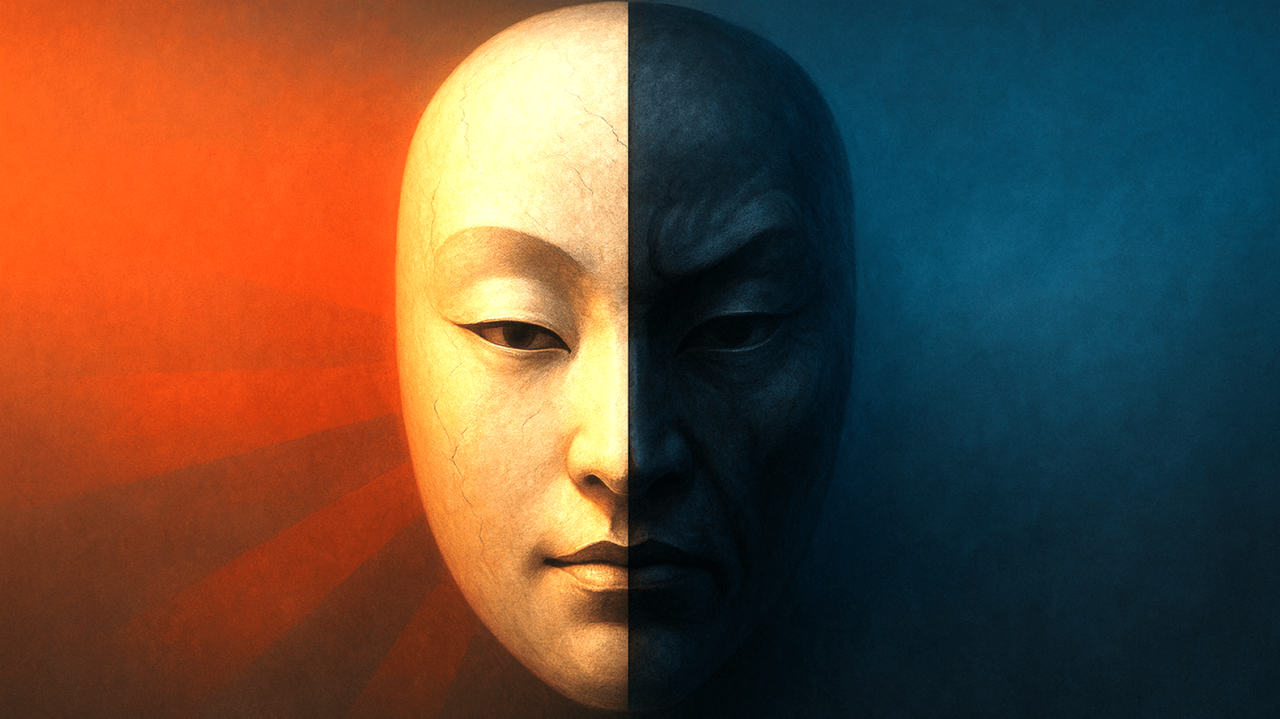【前回の記事を読む】どうせ一度きりの人生なら、パンではなく「理想」を喰って、生きていこう
人生哲学
「切る、抜く」
令和となり、「遣り切る」、「遣り抜く」という語が、死語となって久しい。
一時期、流行った「ゆとり教育」の賜物か、日本人から「切る」、「抜く」などという切羽詰まった悲壮感漂う心情が、影を潜めて久しい。
「100%がMAX!」なのか?「150%がMAX!」なのか?は、各個人の規範により異なるだろうが、どうも現代社会に於いては「100%以上のMAX!」を他者に望むことは、「ハラスメント」に通じ、また「強要」「過酷」ひいては「虐待」さえも通ずるそうだ。
メール、FAX、LINE、等は、送ったら「それで、終わり」。
メール届いていますか、FAX送りましたが……、先ほどのLINEの件ですが……、という念には念を押す、くどいとも取れる「遣り切る」、「遣り抜く」が昨今、皆無である。
諸氏が理解し易い様に「切る」、「抜く」の意を「戀」に置き換えて挙げると、生誕100年を迎えた、歌人塚本邦夫の歌に「切る」、「抜く」の心が顕著に表現されている。
『馬を洗はば馬のたましひ冱ゆるまで人戀はば人あやむるこころ』
馬を洗うならば、馬体ではなく、その馬の魂が浄化し冴えるまで、洗い切れ。人を戀するならば、その人の命を奪い、殺してしまうまで、愛し抜け。
また、歌人北原白秋も、大正2年発刊の歌集『桐の花』にて「切る」、「抜く」を詠む。
『君かへす朝の舗石さくさくと雪よ林檎の香のごとくふれ』
白秋は、隣家に住む人妻、松下俊子との不倫によりこの歌を「不貞罪」の獄中で詠んだ。
獄中で堂々と自らの「不貞」を公に詠み、出所後、愛し抜いて、松下俊子と結婚した。
「いっそいま殺して欲しい白き手でおまえの戀が翳るそのまえに」
「遣り切る」、「遣り抜く」、「切る」、「抜く」がこの世から消えて、寂しい。
無難に、適切、適温、丁度、程々、等で、一度きりの自分の短い人生を茶で濁さず、「切る」、「抜く」に生きて、「華咲き乱れ、今、活きている」と、人生を謳歌して欲しい。