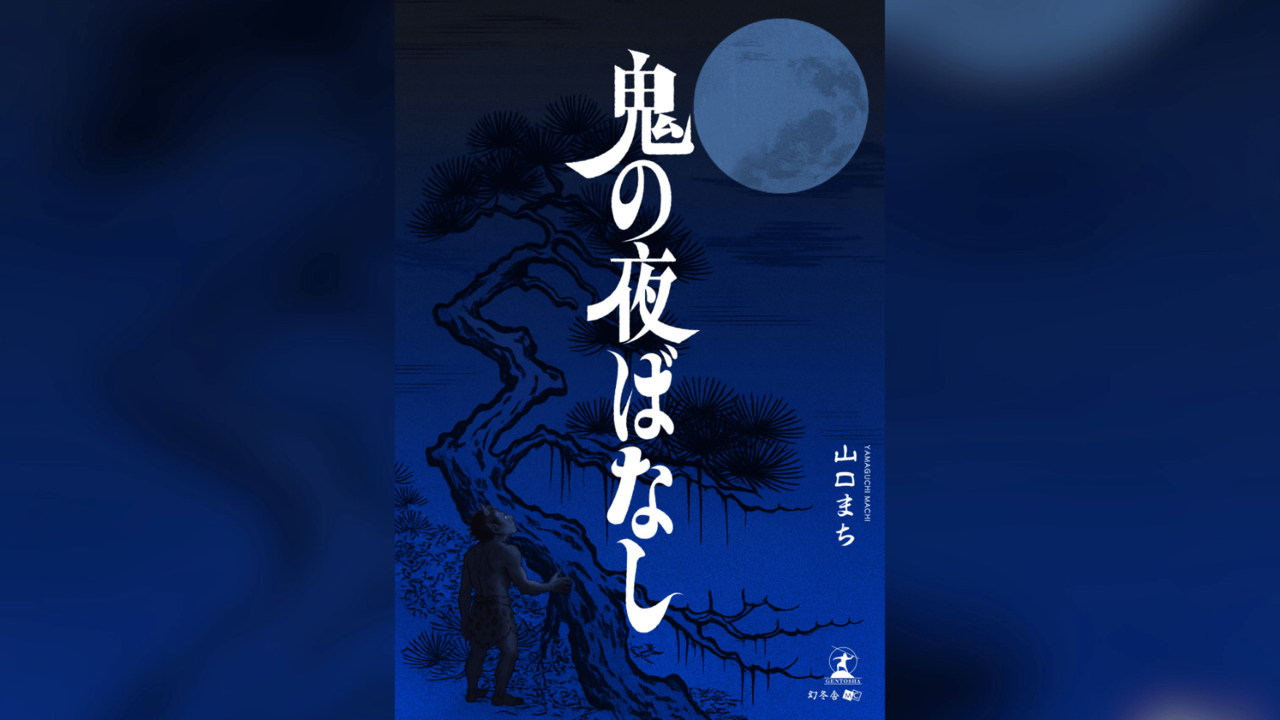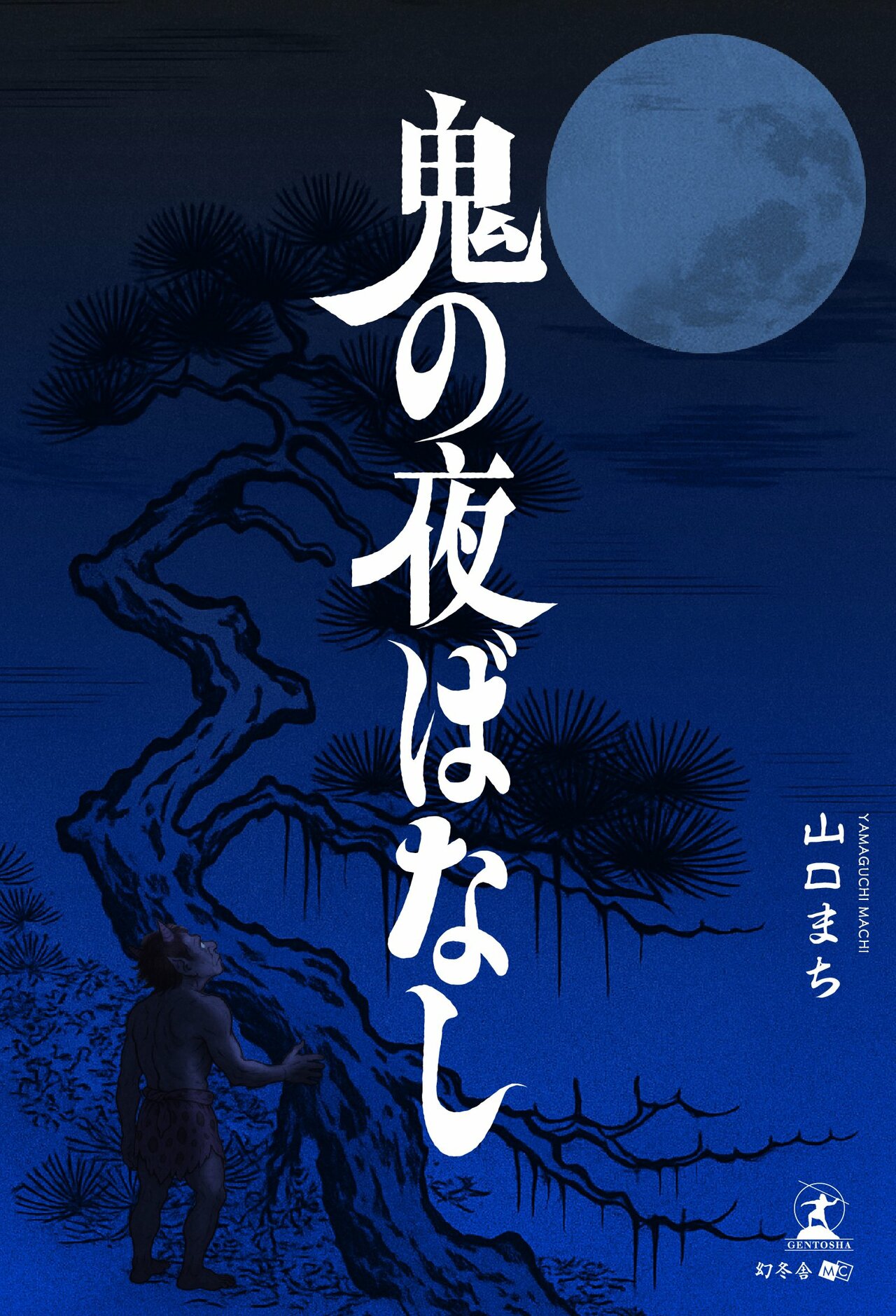「鬼」の話をしようと思う。
昔から今日に至るまで、繰り返し様々な物語に登場する、なんとも不思議な存在の「鬼」。古代中国の書物には、死者がこの世に帰ってきた姿という記述もある。
「鬼」とはいったい何だろう。
日本の鬼は、頭に二つの角(つの)、口には牙(きば)、恐ろしい顔と筋骨逞しい肉体を持つ地獄の獄卒がモデルのようだが、もともと鬼に決まった姿はなかった。丸い体に手足が付いているだけだったり、頭が牛や馬だったりと、恐ろしげな獣じみた姿で流行り病の元凶ともされた。
その昔は、時の権力者に抵抗する豪族が「鬼」とされることもあった。退治される対象となり、有無を言わさず滅ぼされていくのだ。
「鬼」の表記は『日本書紀』から見られ、時代が進むと『今昔物語』や『御伽草子』『宇治拾遺物語』また能の演目などに登場するようになる。
そこでは人智を超えた力を見せたり、人の心の奥底に潜む邪悪さ、極限まで肥大した羞恥心などを体現したりしている。「鬼神」だの「鬼畜」だの真逆な形態で表現されているが、時には滑稽な姿で笑わせてもくれる。
これから、忘れられた遠い昔の「鬼」の物語を今に甦らせてみようと思う。そして、現代においても不条理で不合理な情景に潜む「鬼」を表現してみたい。