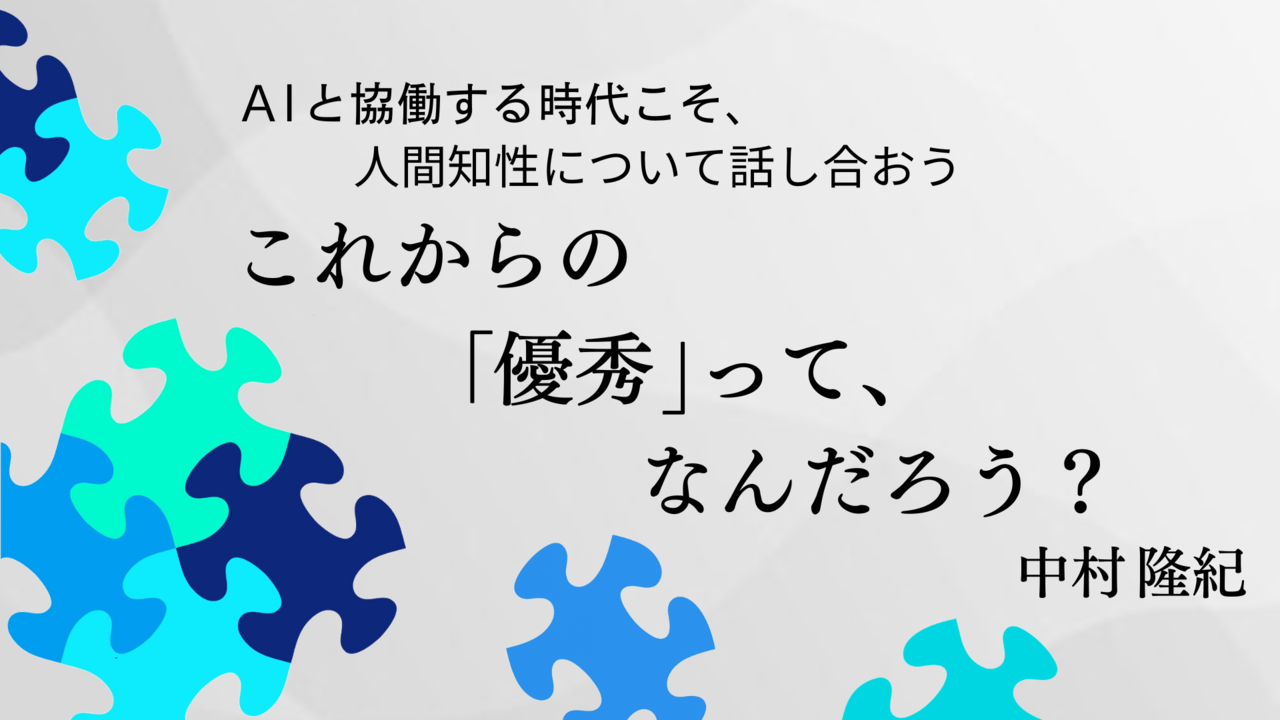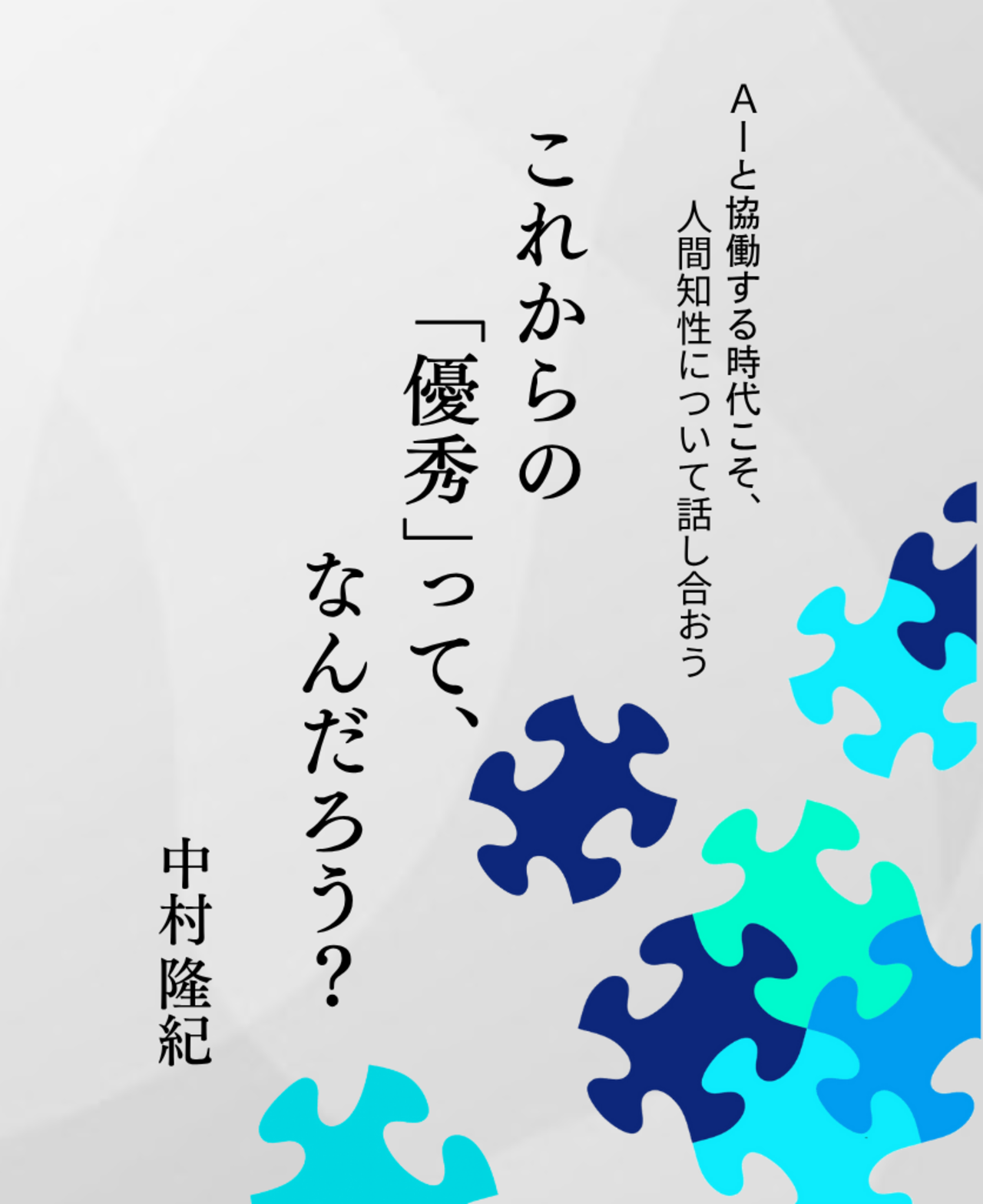【前回記事を読む】アメリカ的なAI vs 中国的なAI?…AIの出す答えは、モラルや公平性を保てるか?
第二章 すぐそばにある、知の分断
タエさんがエアコンをつけたまま、道路に面した大きな窓を、いったん開ける。夜風には、まだ初夏の軽さが残っていた。店の空気がゆるみ、みんなのグラスの表面で、水滴がふくらむ。
Keiさんが、いつもさばさばとワインを飲む仲間に話しかける。
「リョウコさんは、子どもからお年寄りまで、接するひとの幅がひろいですよね。世代の分断も、かなり感じますか?」
「そうねぇ。わたしは、世代の価値観は違って当たり前だと思っている。でも、少しギャップが深くなっているかもしれないわ。自分たちの得意なコミュニケーション以外は、お互いに通じ合うのをあきらめてしまっているというか。確かに分断という言葉は、その通りかもね」
「たとえば、おじさん構文……文章に行間がたくさん入っていたり、気を使って絵文字を連発してくるのは、ちょっと若いひとたちが引くとか、一時、話題になりましたよね」
マーケティング領域も仕事にするジョージが、会話を受け取る。
「そういう若手は、SNSがテキスト・コミュニケーションの中心なんです。短い文章だから行間はあけないし、反射的にレスするから飾り文字もわざわざ探さない。
彼らの世代が、全面的なデジタルネイティブかというと、スマホの様式には強いけれどPCには弱いひとがいたり、どのデバイスやアプリを中心に生きているかによって、言葉や文章に感じることが、すごく違うような気がします」
「いまどきの新人研修では、〈メールには、タイトルがある〉っていうことから教えるんだ」
Keiさんの言葉から、シュウトくんも会話に交ざる。
「あ、ふだんはハッシュタグがタイトルか……僕は子どもの頃から、オトナと仕事をしていたんで、メールに違和感はないです。でも、『お世話になっております』『何卒よろしくお願い申し上げます』とか……定型文って、どうなんですか? うーん、季節の挨拶とか、優しさを感じる場合もあるけど」
「『誠に遺憾でございます』なんて、曖昧な政治言葉もまだ残るのかしらね?」
「あれは職業病だ。けっこう難病だぞ」YOさんが、ひとこと入れる。
「ボク、半分ガイジンなので、『ヤバい』っていう日本語がよくわかりません。あれは、ほめているんですか? それとも警戒感を示しているんですか?」
「日本で一番ヤバい温泉を教えてください……あらら、なんかダメね」