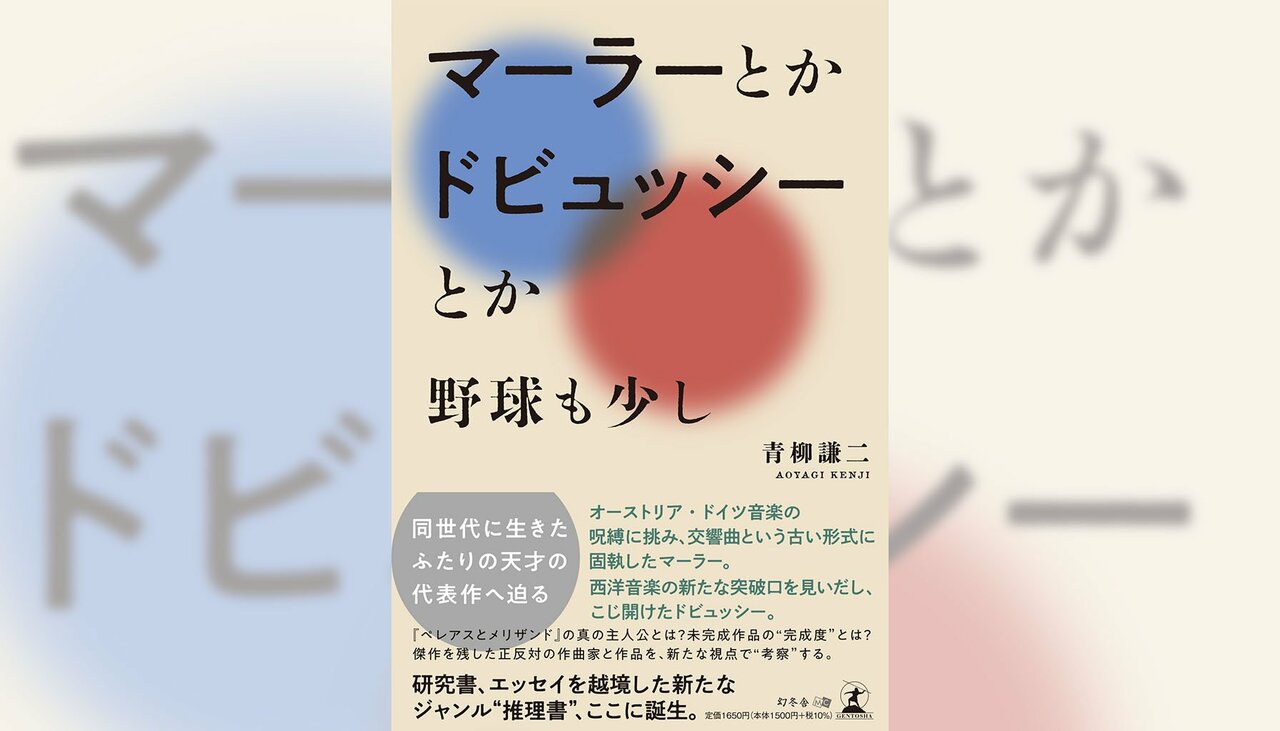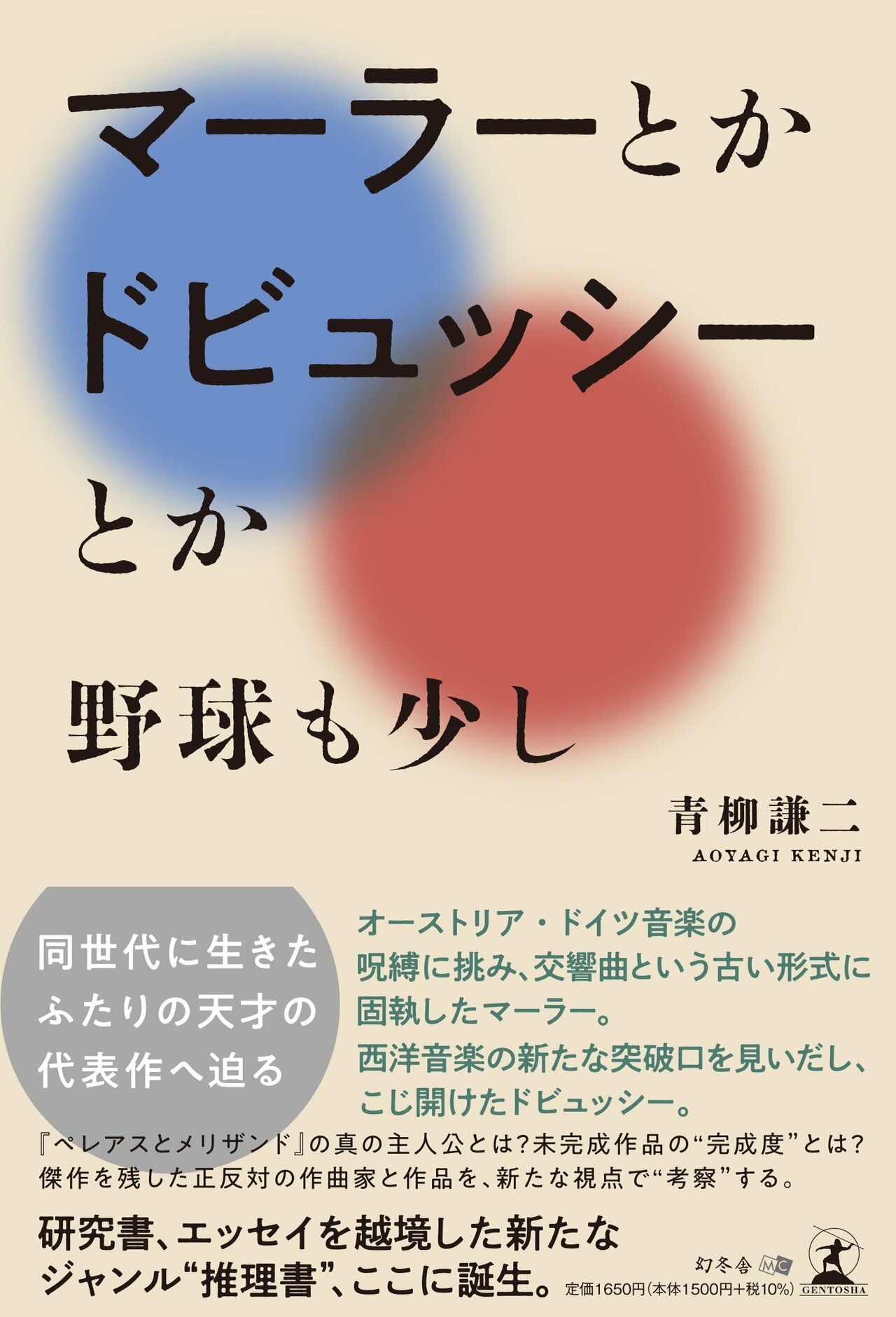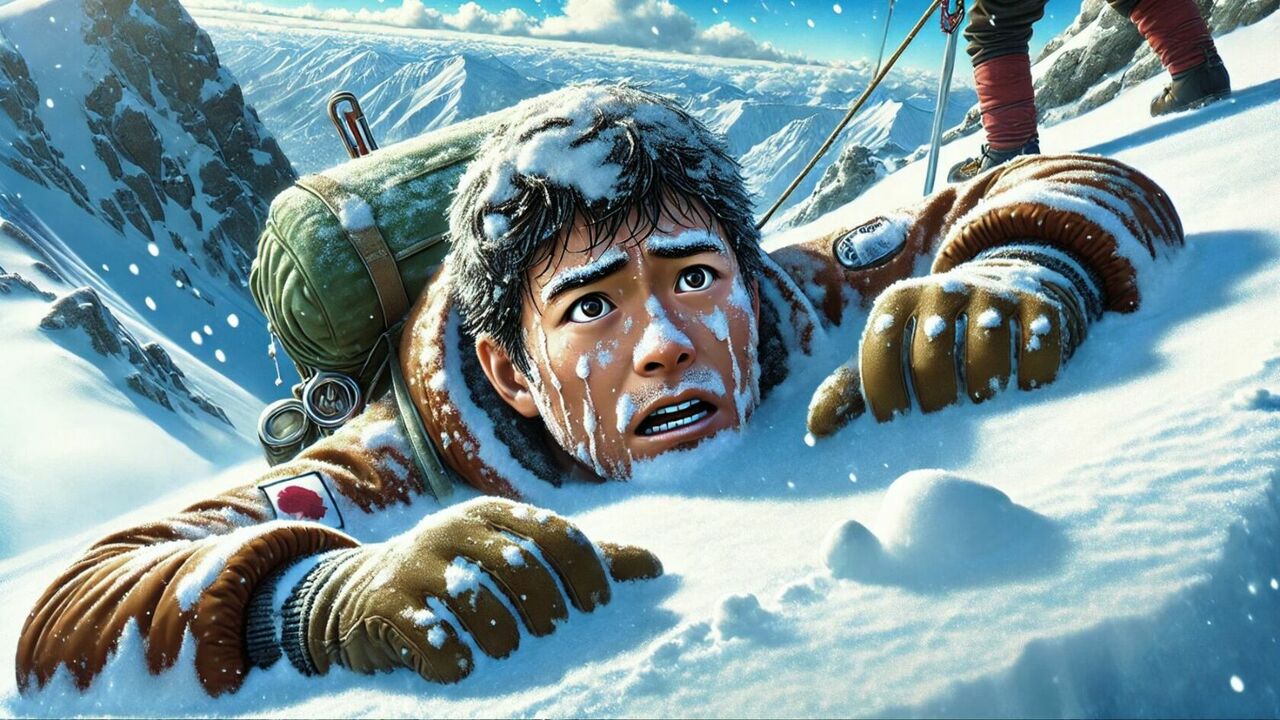【前回記事を読む】イギリスの食事はたしかに不味い。だがそれは、イギリス人が味覚音痴ということではない。彼らの営む食生活は…
序章 目に付く鱗
価値の並置化
ヘーゲルの美学などが典型的だろう。そこでは「美の理念」が、作品を通して顕現していく度合いが高まるにつれ、美の価値がヒエラルキー的に高まっていくのだった。因みに芸術音楽は芸術の中でもヒエラルキーの頂点に君臨していた。音楽にはなんとも都合の良い美学だった。
ところが現代では芸術音楽と大衆音楽も同じ地平に位置することとなる。ベートーヴェン好きも桑田佳祐好きも同じ音楽愛好家というわけだ。
こんなアナウンスも象徴的だ。「次の楽曲をお聴き下さい。素晴らしい名曲で桑田佳祐の曲です」。楽曲とか名曲という言葉は、一昔前にはクラシック音楽の専売特許で、ポピュラー音楽には使われなかった。蛇足だが私も桑田佳祐ファンだ。
分節
もう一つのキーワードは分節だ。母音を考えると手っ取り早い。
我々日本人は五つの母音を持っている。ひとたび五つの母音に習熟して成人すると五つ以外の母音はその五つの母音のうちのどれかに関連して認識なり習得なりされる。だから五つ以外の母音を習得するのは年を取れば取るほど困難になる。すなわち元々は連続体である母音の総体を、我々日本人は五つに分節していることになる。
このことはさらに単語の分節にも適応される。「月」と「moon」について考えよう。日本語の月は、「月がとっても青いから遠回りして帰ろう」とか「満月を眺めて楽しもう」などとなんとも情緒たっぷりの日本人の感情をともなう。
しかし英語の「moon」は、それこそ満月の時は化けものが出たり正気な人間も狂い出す、そんな「moon」なのだ。
すなわち両者とも地球の周りを回る衛星を指すことには変わりないものの、その意味する総体は異なる。「月」は「月」の意味するところのものにより分節され、「moon」は「moon」の意味するところのものにより分節され、それぞれの意味を持つということになる。この衛星は同じヨーロッパでも南に下ればまた意味が変わる。