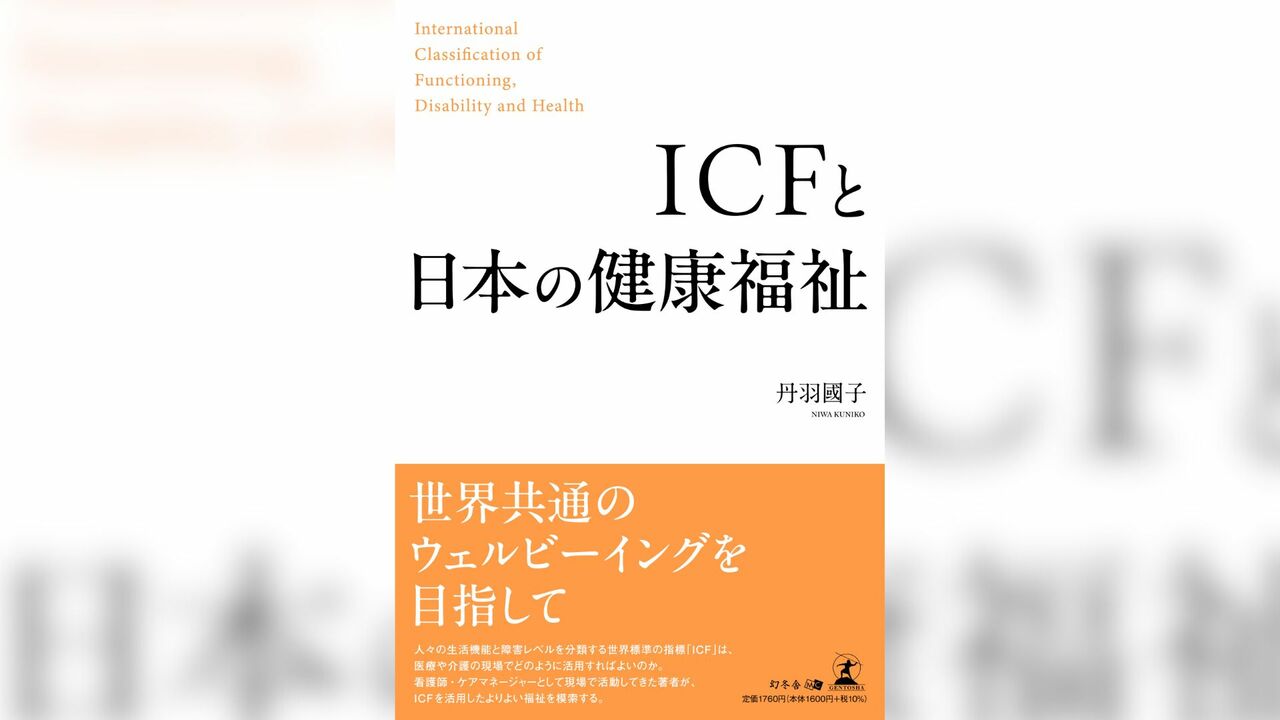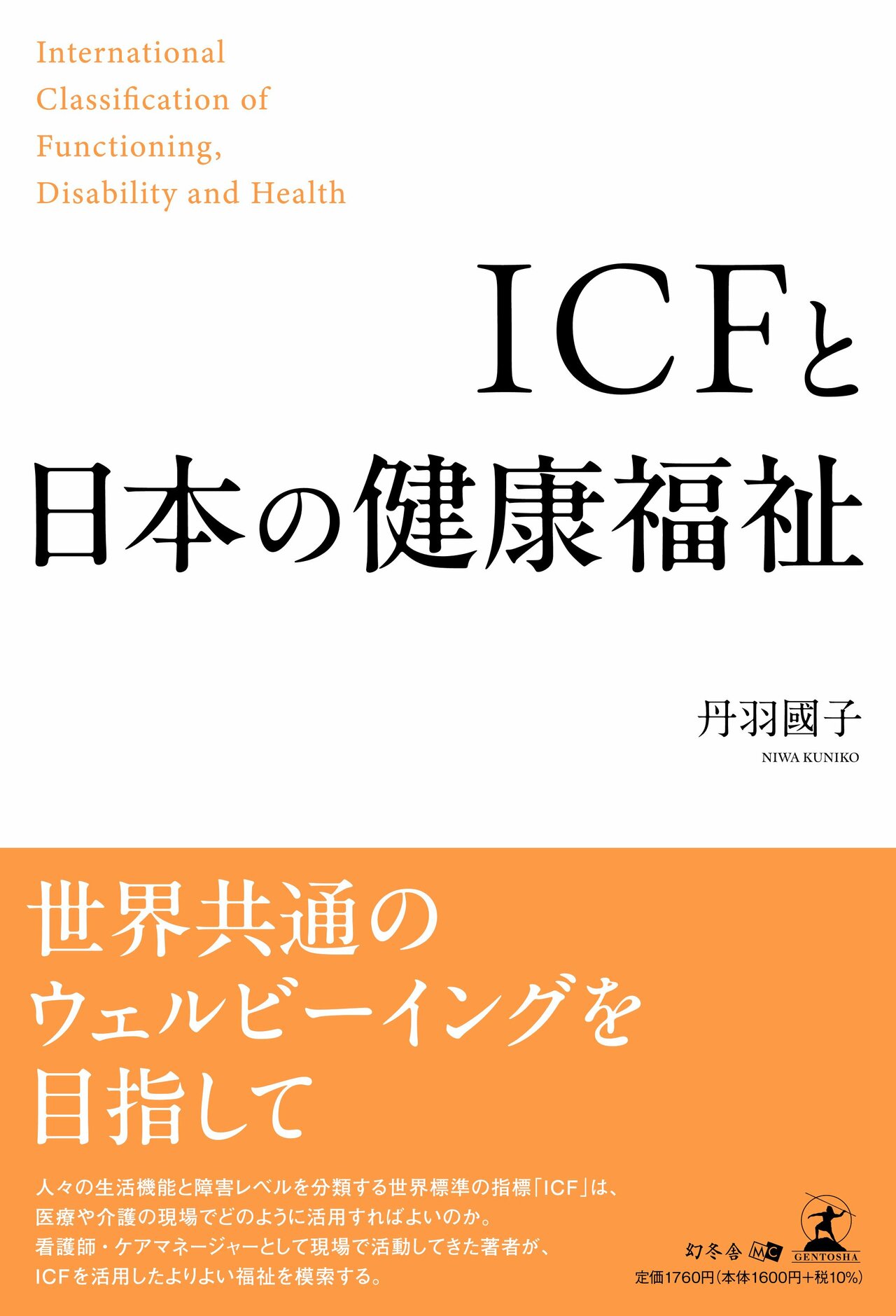【前回の記事を読む】全動物のなかの人類は地球環境のなかで唯一、直立二足歩行を可能にさせつつ脳を発達させた。しかし、脳の発達による弊害もあり…
第1章 健康福祉の原点
第2節 子は親を選べない不条理
子は親を選べない不条理のなか、人として人間として、健康で妊娠を願う父と母は、まず、父と母が健康な状態にあり、合意のもとに結婚していることが問われています。
理由は、人間の健康な躰は、約 37 兆余個ある細胞一つ一つの健康状態に基づいており、父と母の生体リズムと生活リズムが、何よりも健調(著者の造語。健康で調子が良い状態)である事が必須だからです。「進化の過程で脊椎動物が大脳を獲得するのに果たした遺伝子の機能を見つけた」(注1)やアレルギーは父の遺伝子が関わっている等があり、脳の研究は日進月歩で進んでいます。
1978 年にスコットランドのディングルトン病院研修時に、デンマーク・ノルウェー・アイルランド・スコットランドの 18 ~ 20 歳前後の研修生たちと寄宿が一緒でした。
食後や休日や行楽時に、結婚観を聴いてみると
「結婚して生涯を共に歩める人を選ぶには、15 歳位から恋愛もするが、一緒に生活して楽しいか、お互いを高め合える人かどうか、生涯を共に支え合って生活ができる人かどうか。2、3人の異性と同棲(1週間のこともあるが、1カ月近く生活する事もある)して、気が合うか、お互いの生涯を高め合える人かを確認してから結婚相手を選ぶのが一般的」
とのこと。老後を考えた相手選びに関心し、教えられました。
日本の場合、同棲して結婚する人も多くはなっています。しかし現実には、多くの男女が、一緒に生活するのは結婚後が多く、お互いを確認して結婚したはずでしたが、一緒に生活を始めると習慣の相違や違和感が多く、「こんなはずでは無かった」という人が多いのが現実です。
日本の夫婦関係は、世間体や親戚等の対外的関係を重視して我慢するとか、生涯を共にする関係は『生きるため』を一番にして、子どもとの関係は夫婦の関係に左右されて二の次になっているように感じます。
子は親を選べない不条理を考えれば、北欧等の結婚前の男女に学ぶ必要があるのではないでしょうか。