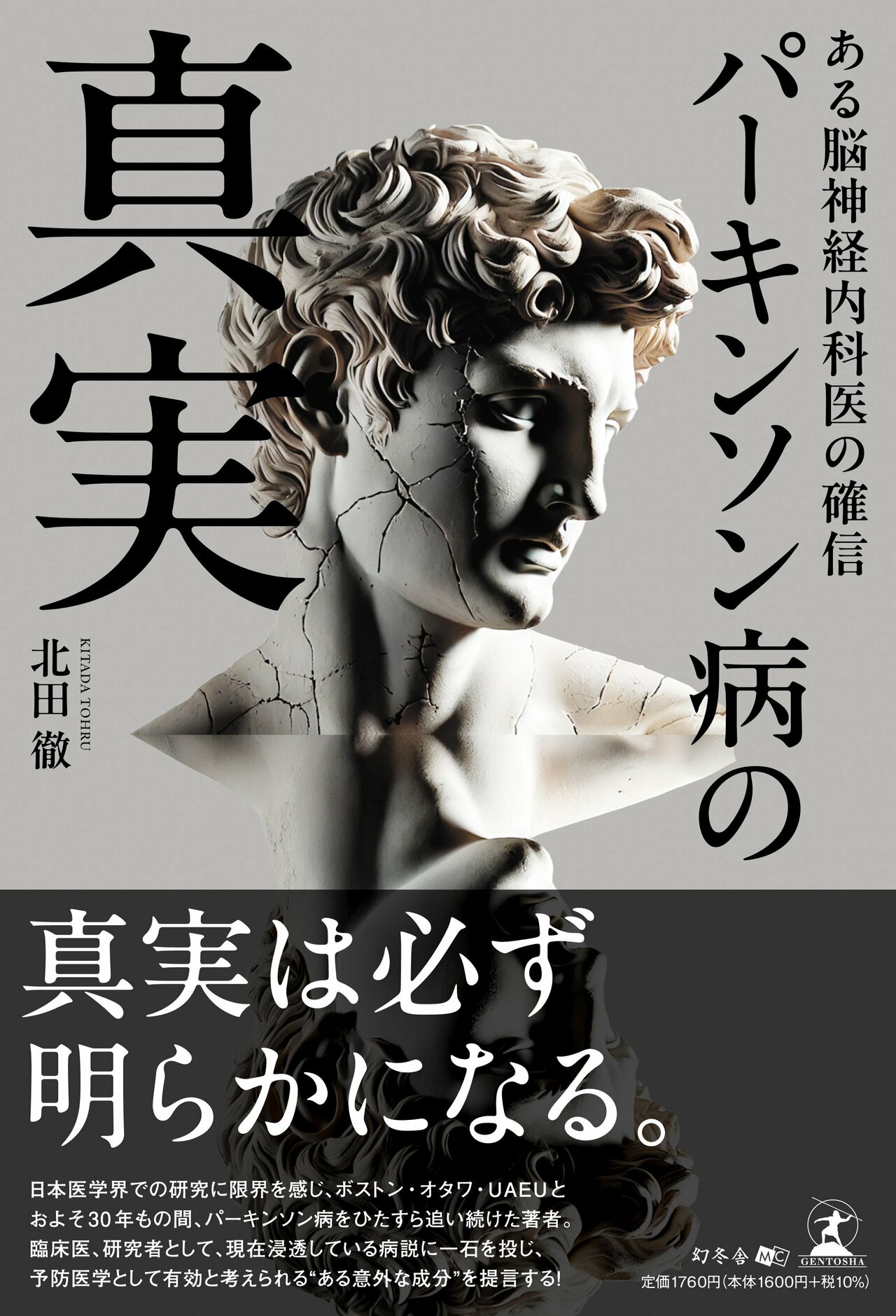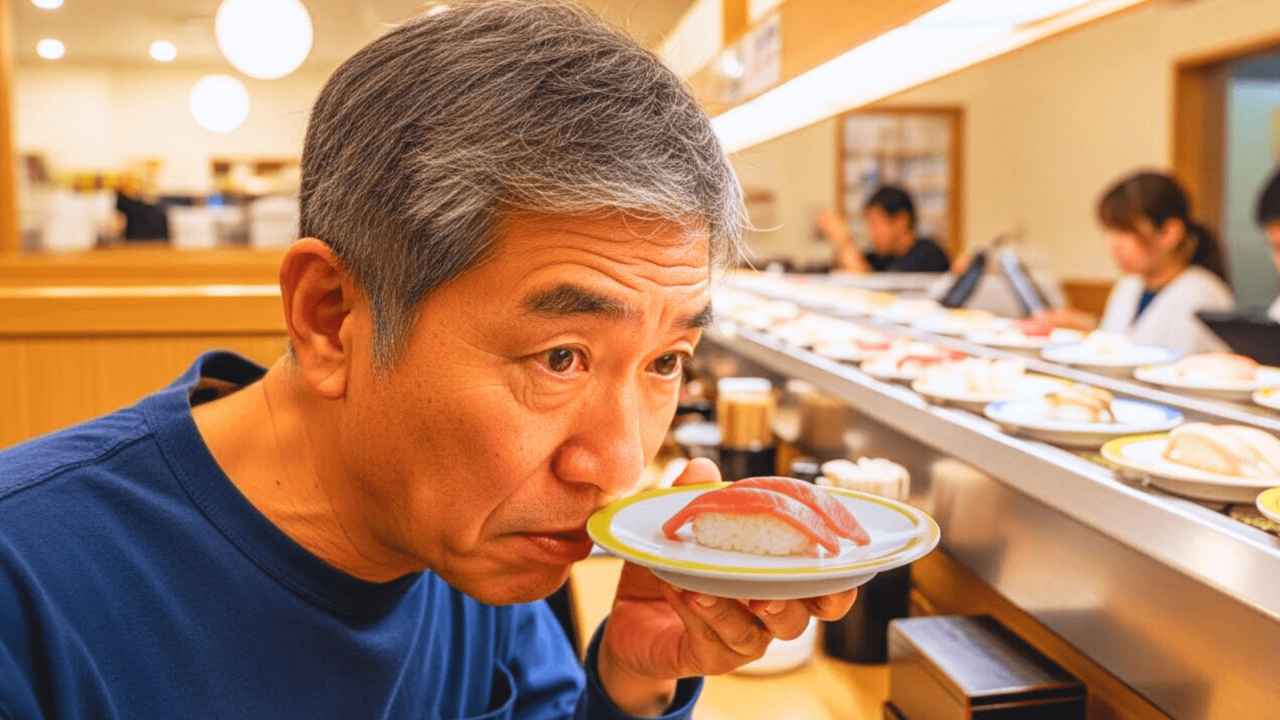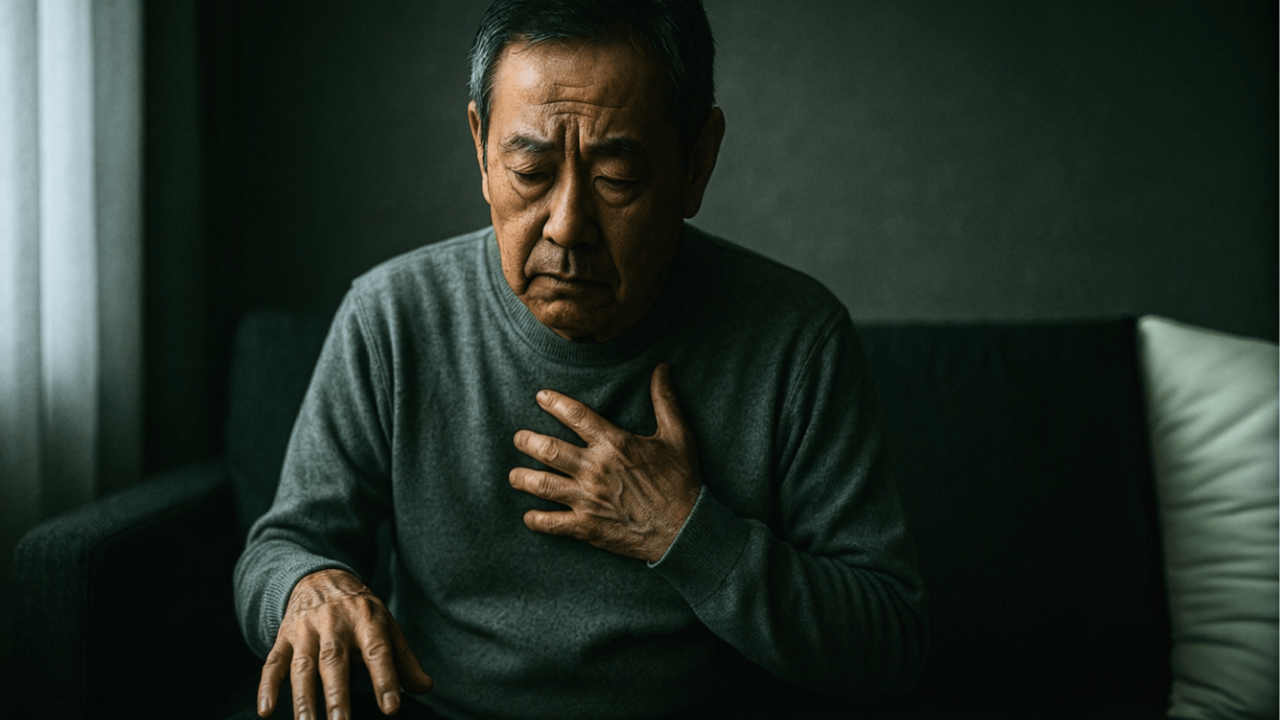診断2 補助診断
パーキンソン症候群との鑑別に用いられる補助診断について紹介いたします。
頭部CTやMRI検査を行うことで、脳血管障害や脳腫瘍、特徴的な画像所見を示す他の変性疾患などの病気の可能性を除外します。
核医学検査として、[123I]MIBG心筋シンチグラフィーと呼ばれる、心臓の交感神経節後線維の状態を調べる検査を行う場合があります。
パーキンソン病の患者様では、この薬剤の取り込みが低下していることが知られています。パーキンの遺伝子変異のある患者様では、心臓交感神経が保たれ、MIBGの集積は正常であったとういう報告があります。
[123I]β- CITシンチグラム、いわゆるドパミン・トランスポーター(DAT)イメージングは、黒質線条体のDATを画像化し、ドパミン神経の脱落の程度を評価する検査です。パーキンソン病やレビー小体型認知症の早期診断や、他疾患との鑑別に期待されます。
認知症を来すパーキンソン症候群としてはレビー小体型認知症、アルツハイマー病、大脳皮質基底核変性症などがあり、脳血流パターンを解析する[123 I]IMP脳血流シンチグラムが、種々の認知機能検査とともに、これらの疾患とパーキンソン病との鑑別に用いられることがあります。
【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…
【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。