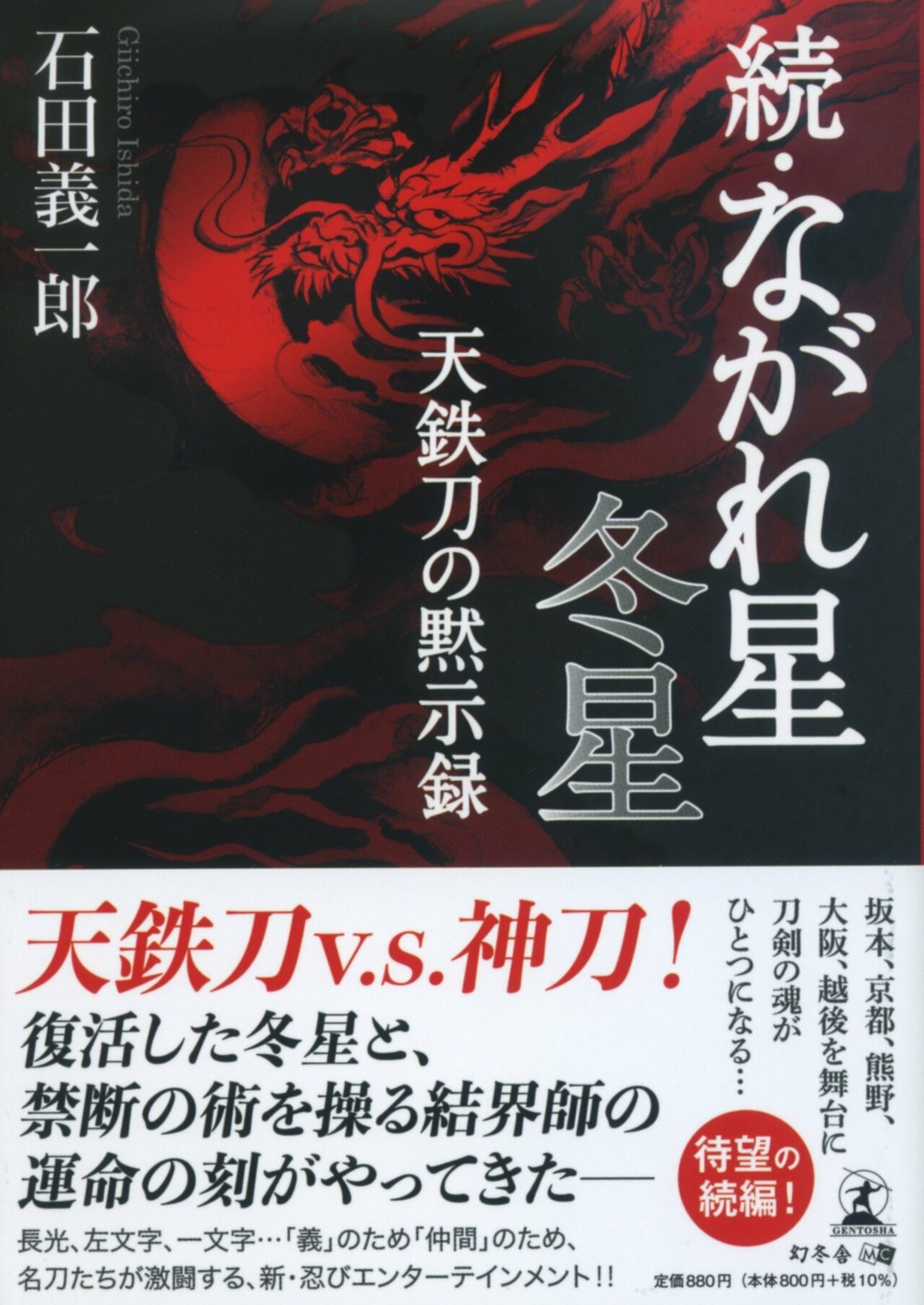「あたいは亜摩利(あまり)。蘇摩利は姉貴だ。姉ちゃんは気が短くて血の気が多いからね。下っ端だとみるとすぐ甘くみる。だからこのザマさ。でもあたいは違うよ」
亜摩利というくノ一は、両手に鉄の毬(まり)、〝鉄毬(てつま)〟を持っていた。その鋭い鉄の爪は肉片だけでなく、骨までも抉(えぐ)り取るような殺傷能力の高い恐ろしい武器である。
しかも通常の鉄毬ではなく鎖につながれており、遠隔にまで投てき出来るよう改良がなされていた。
「小僧、その箱を渡せ。命までは取りたくないが、断れば屍(しかばね) になるぞ」
義近は額にじっとりとした汗が流れるのを感じた。
(どうする。苦無または仕込み刀で戦うか? いやこいつにはまったく歯が立たなそうだ。ならばあれしかないか……)
義近はゆっくりと腰を沈め、くノ一には見えないように足元の石を拾った。
「お、おまえは石で魚を獲(と)ったことはあるか?」
「は、石で魚を? なんだそれは?」
次の瞬間、義近は目にも止まらぬ素早さで石を二個、回転させながら投げた。
一個は亜摩利の頬をかすめ、もう一個は鉄毬の端に当たった。
亜摩利は油断していたこともあり、最初の一投をよけきれなかった。頬から流れる血をみて顔が紅潮していくのがわかった。
「くっ! おのれ小僧! よくもあたいの顔に傷をつけたな!」
亜摩利は鉄毬を勢いよく振り回し、ブンッと音を立てて回転させた。
右手は横回転、左手は縦回転で器用に操り、一直線に投げてきた。