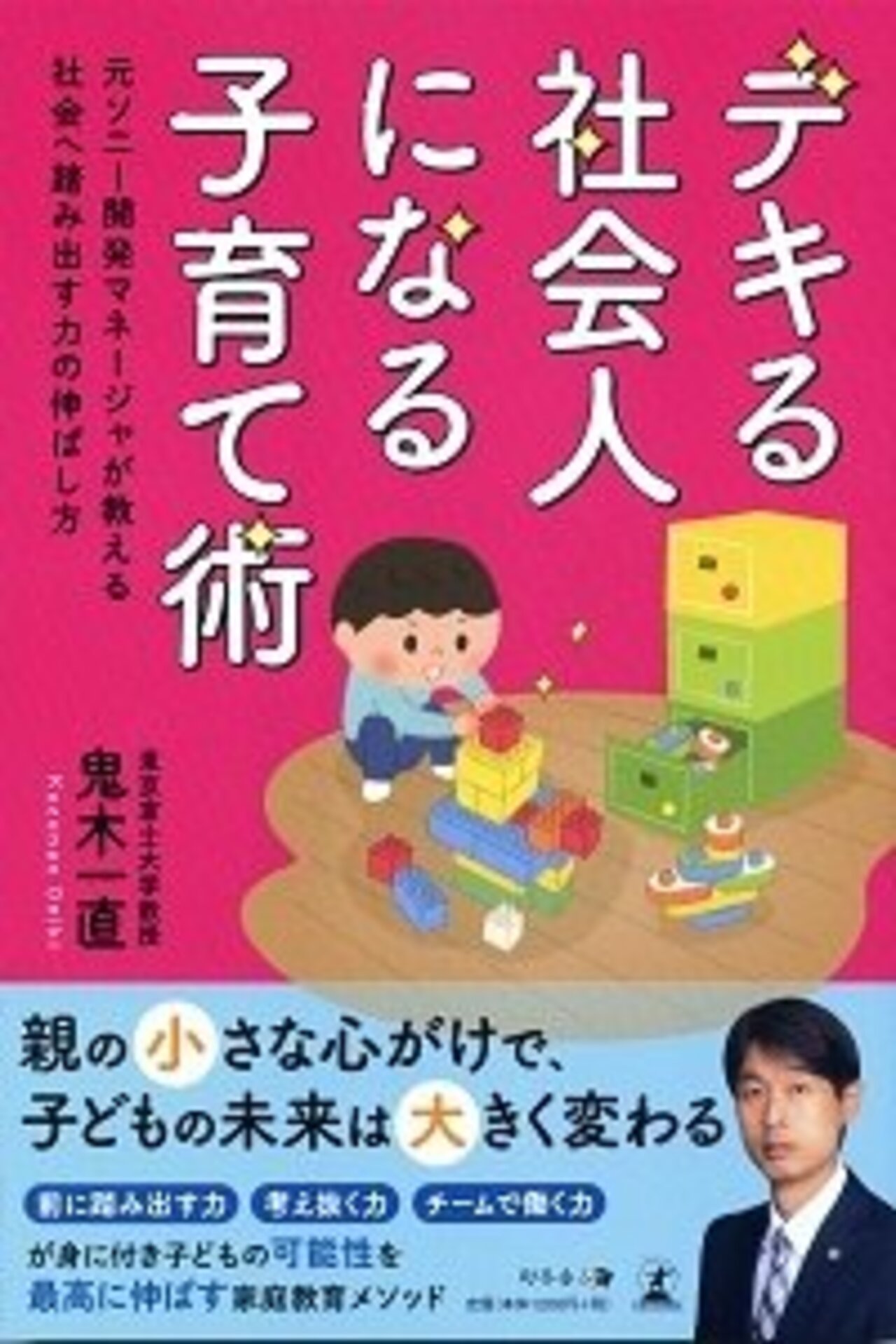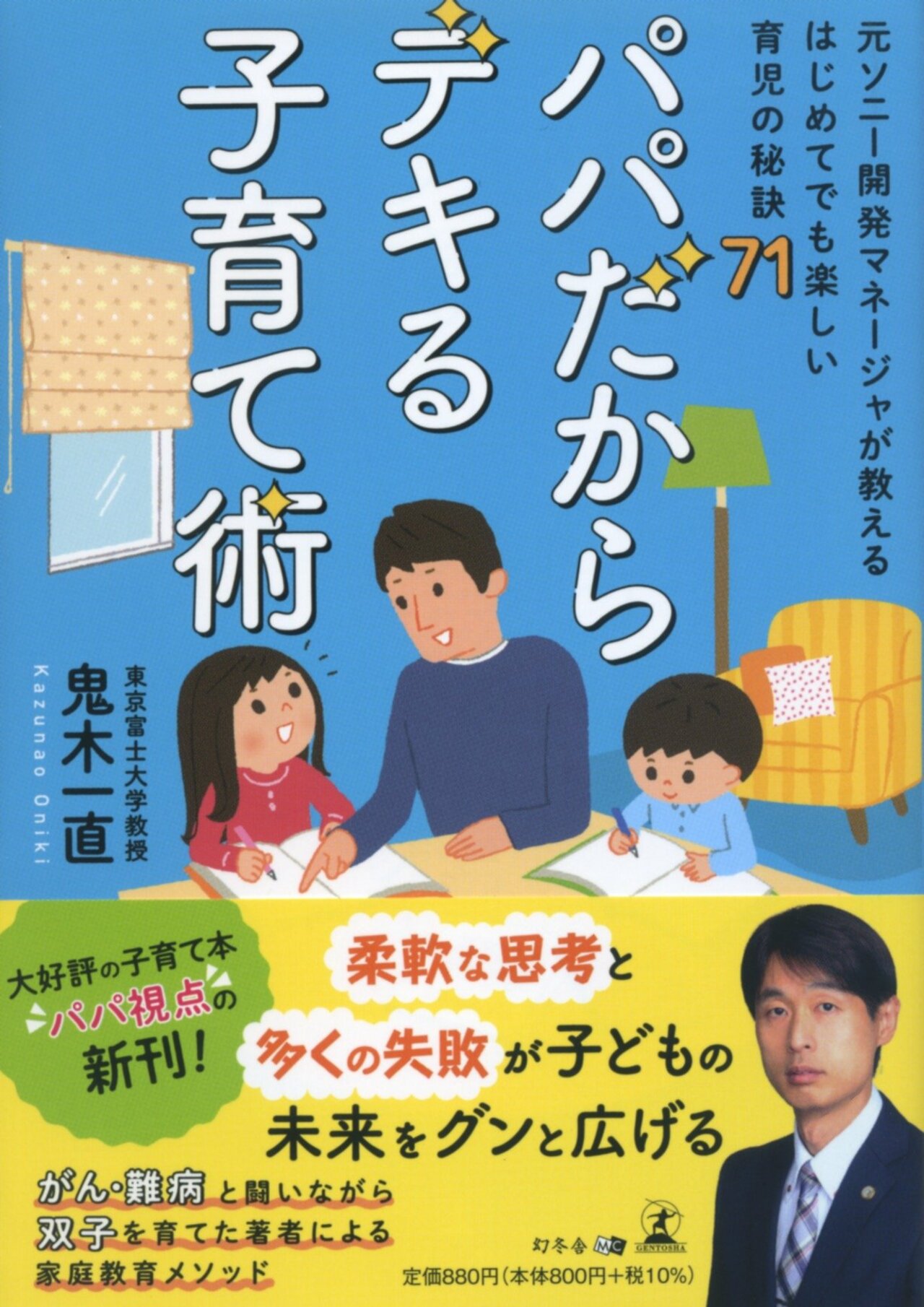ママの育児とパパの育児には違いがある
人それぞれものの捉え方が違う、だから子育ての厚みが増す
主にママが育児をするべきという考え方自体がすでに古くなっているということを記載しましたが、夫婦で協力して行う、あるいは、仕事のスタイルなどによってはパパが中心になって育児を行う家庭が増えてきています。
我が家も私の方が遠隔での業務をしやすく、かつ多少時間的にも調整が利くことから、保護者会への出席、子どもの宿題や持ち物のチェック、子どもの食事の準備、皿洗い、ゴミ出しなどは私が主体的に行っています。
どちらが何をどのくらい担当するのかは、時間の融通や得意不得意など家庭によって異なるのでよく話し合っていただければと思いますが、男女では考え方が違うということも意識するといいと思います。
ママは一般的に友達との会話や食事などでストレスを解消する、心が動かされたことは共有したい、目の前のことをひとつひとつ終わらせたいといった傾向があるようです。
それに対してパパは細かいプロセスより大きな成果を得たい、効率的に事を運びたい、問題をすっきり解決したいという人が多いそうです。必ずそうであるわけではなく、どちらがいいということでもありません。
パパが手料理を作るのもいいですし、ママが日曜大工をしてもいいと思います。大事なのは、人それぞれものの捉え方が違い、興味、価値観が異なるという認識の共有です。
多様性が求められている中、答えは1つではなく、いろいろな考え方があるということ、男女で求めるものが違うということをお互いに意識しましょう。
ここがポイント
パパはこれ、ママはこれ、と従来の価値観で決めつける必要はありません。いろいろなことをお互いやってみることで、発見が出てきます。完璧な育児なんてありませんので、楽しみながら成長していけばいいのではないでしょうか。