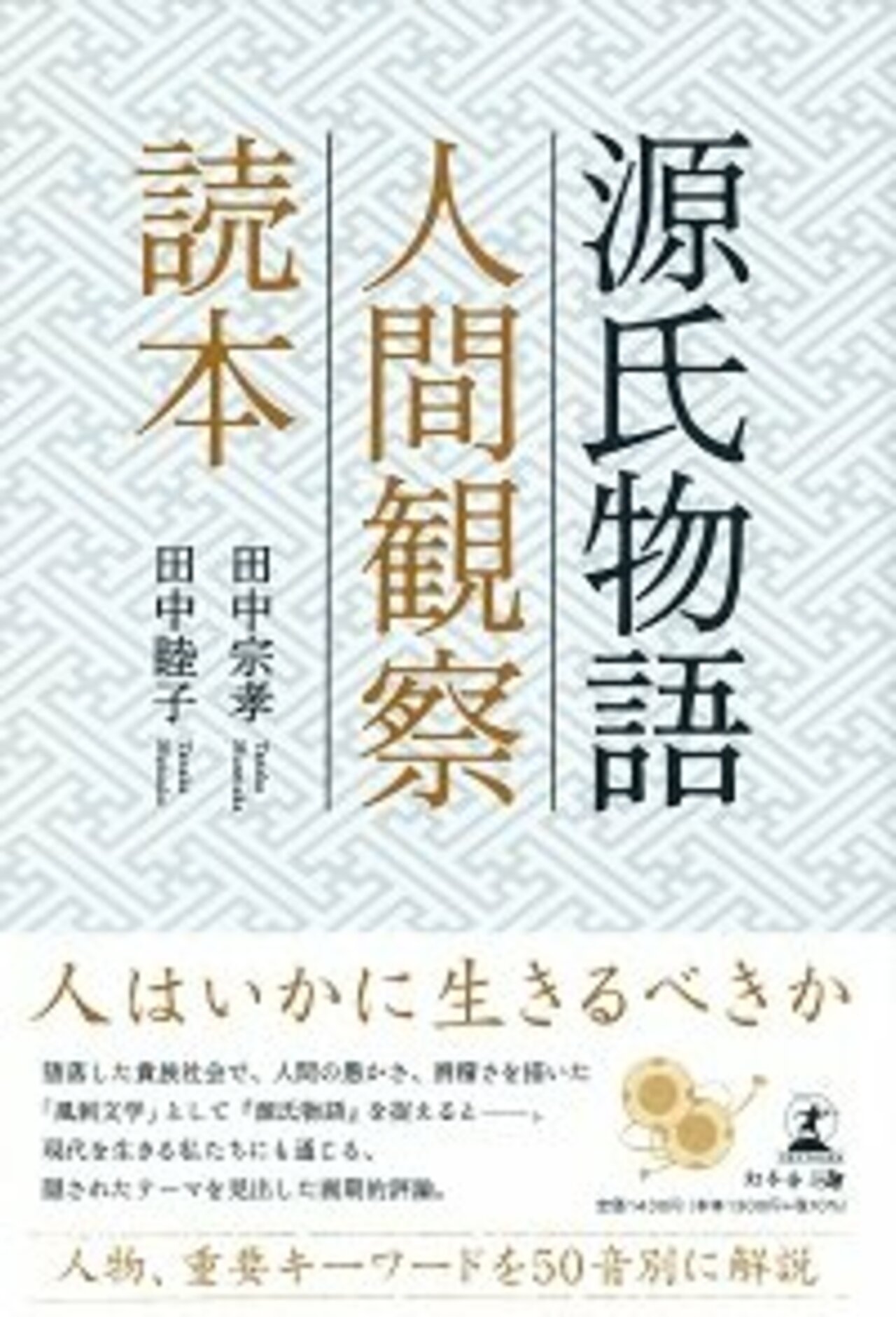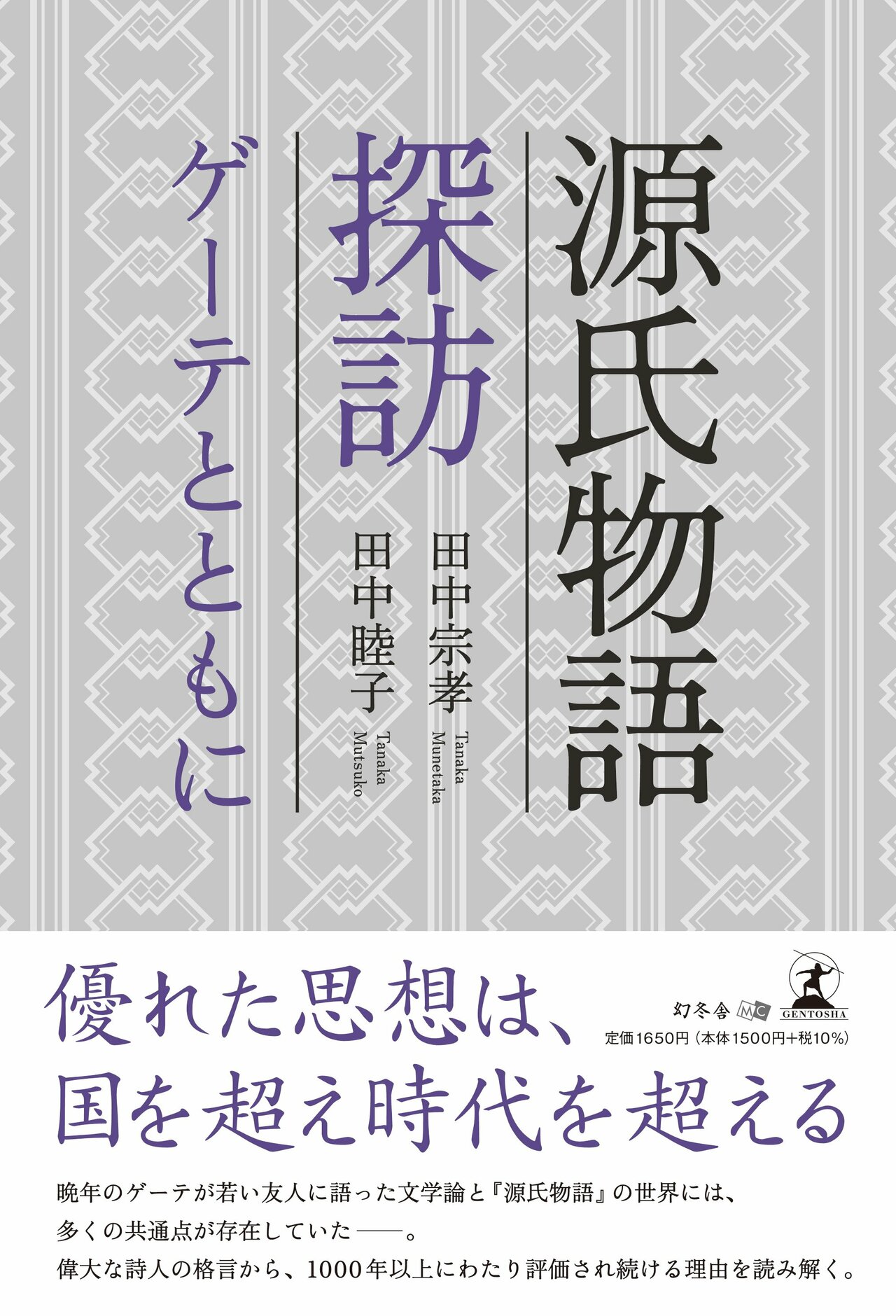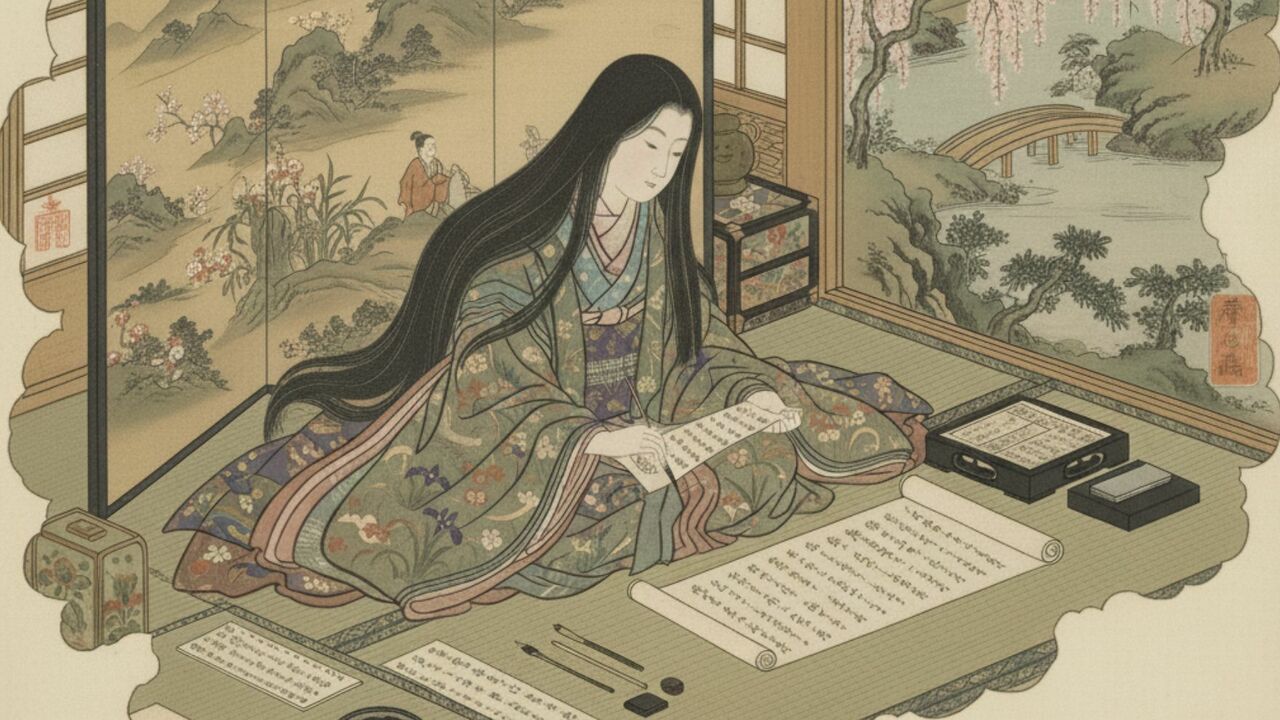出産予定の十二月も過ぎ、藤壺本人もまわりの人びともやきもきしていたが、二月十日過ぎになってようやく男皇子を出産された。この皇子は、表向きは桐壺帝の第十皇子として扱われ、のちに東宮となり、さらに冷泉(れいぜい)帝として帝位に即(つ)かれる。
偽りの皇子が帝位に即くのであるから、貴族社会の腐敗もここに極まったというべきである。紫式部は、平然とそれを物語として書いた。書かねばならないという使命感が、紫式部に書かせたのである。
桐壺帝が思いつかれた企みの影響は、広い範囲に及ぶ。
藤壺は、東宮(後には、冷泉帝)の出生の秘密が世の中の人びとに知られないことのみに汲々として生きることになる。
冷泉帝自身は、藤壺が亡くなった後、夜居(よい)の僧から出生の秘密をお聞きになって驚かれる。光源氏にあからさまに尋ねることもできない。光源氏は、冷泉帝が秘密を知っておられるらしいと感づいたが、真実を告白しようとしない。そのため、冷泉帝は、悩み続けられることになる。
さらに、宇治十帖(うじじゆうじよう)に登場する八の宮は、桐壺帝の第八皇子であるが、不遇な生活を余儀なくされていた。その理由をたどると、冷泉帝がまだ東宮でおられたころ、東宮を廃して、八の宮を擁立しようという動きがあったが、その企ては頓挫(とんざ)した。
このような事情があったので、その後冷遇されたからである。その結果、三人目の姫君を育てる経済的な力のない八の宮は、浮舟を自分の子だと認めることができなかった。浮舟の惨めな境遇の根源は、桐壺帝の思いつかれた企みにあった。
以上のように、「よこさまなるやうにて」の一言に込めた紫式部のエネルギー量に、思いをいたしたい。
【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...
【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。