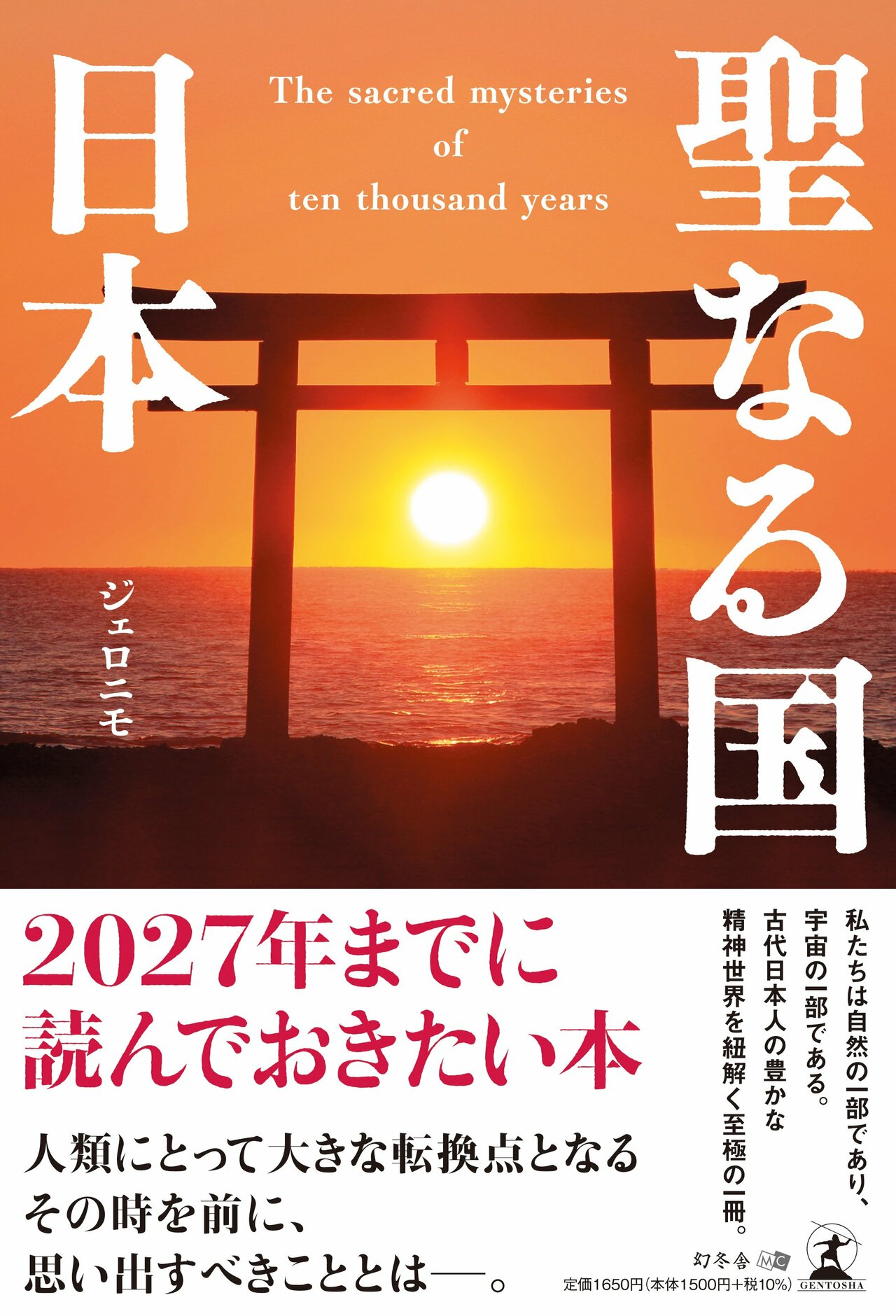古代の母系社会
古代アジアの男権主義は紀元前の中国から強まってきた。「仁義の害」とまで言われた儒教的な常識が蔓延(はびこ)って「貞婦二夫にまみえず」などと女性の貞操が強要され、離婚を悪として、女性の立場は女系社会とは随分と変わってしまった。
中華民族は男系社会(ウル)で、王の世襲も男性の血統が代々継いでいくのに対し、遊牧民族や和国など血統を神聖視する民族は母系社会(ハラ)で、代々女性の血統を大切に守っていく習慣があった。
人間は女性から生まれたという本来のアイデンティティーを大切にしているだけで、子どもを産むことが礼賛されていたという訳ではない。王家にあっても女王の血統が主軸であり、たとえ王が亡くなっても女王はそのままで次々に新たな婿をとり王にしていく。
この習慣は中国以外の古代アジア民族には比較的多かった様で、女系軸はブレずに夫が代わっていった。母が王統であれば父親が誰であったとしても、必ずその子どもは王の血統を継いでいる。そうして代々、血統聖母の様な女性たちが王統を継いできた。
もしも、正当な王統ではなく、簒奪者や新たな支配者や権力者が王位についたとしても、また婚姻し王統をついでいく。そして、遊牧民族はどんなに乱れようとも必ず同族の者を王に立てた。
王家に皇女がいなくなってしまい、王子だけで子を産めなくなると、他の王家から女性にきて貰って家を継いで貰う。婿養子に家を継いで貰うという私達が常識だと思っている世界とは、真逆の世界だ。
婚姻を表す「嫁ぐ」という言葉も「戸継ぐ」ということで、女性にその家の戸主を継いで貰うということだ。母系社会というより、母敬社会と言っても良いかもしれない。今でも「母国」というのもその流れだろうか。
【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...
【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。