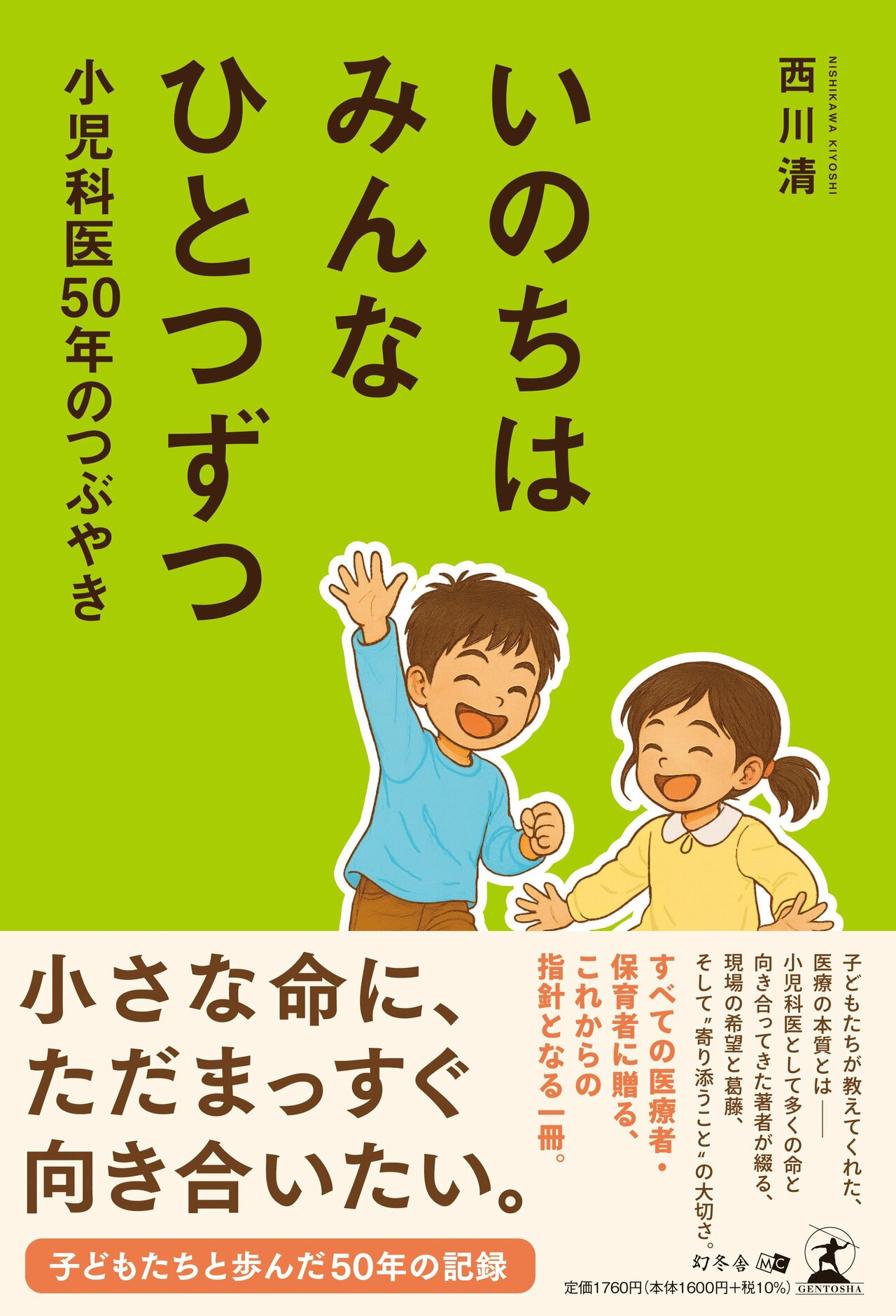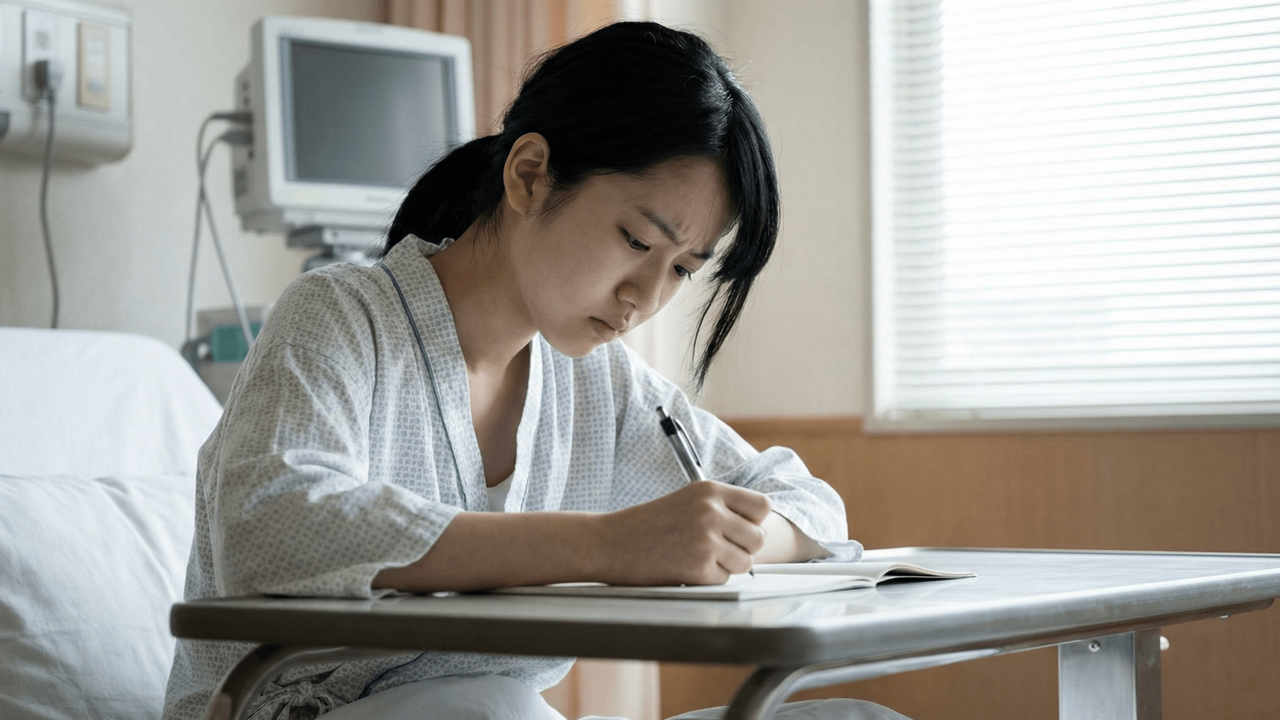そんな子どもにもいろんな悲しい出来事が生じてくるのを思い知ったのは、小児科に入った直後。大学病院で初めて主治医となったのは生まれつき免疫力が低下し、5カ月でまだ2kgにも満たない弱々しい笑顔しか見せない乳児だった。細い腕からたくさん採血をしていろいろな検査や治療をした。そのかいもなく数カ月後に亡くなった。若いお母さんは自分より若い主治医でどんなにか不安だったことだろう。
中学生の予後の悪い貧血の子を、一度だけ車に乗せて私の生まれた山までドライブしたことがある。そのときのうれしそうな顔を私は忘れない。私が大学を離れてしばらくして彼も亡くなったと聞いた。
東京に研修に出たときのこと。苦しい喘息の発作が三日三晩続いたとき、主治医の私も不眠不休でグロッキーとなり、先輩の気遣いにより一晩下宿へ帰って寝た。朝早く急いで病室へ駆けつけると、夕べのままであえいで私の出て来るのを今か今かと待っていて、「ああ、先生」と言ってあえぎながら少しだけ笑顔を見せた。幸いこの子は、今はもう30を過ぎて元気に働いていると聞いた。
いろいろな病気が襲ってきても、子どもはその合間合間に笑顔を見せてくれる。それはまるでわれわれ大人を救ってくれる天使のようだ。
香川小児病院に赴任したのは昭和49年。ここで私はまた当たり前のことに驚かされる。入院児が廊下を走りけんかをし、だだをこね、絵本を読み、歌を歌う。夜にはお母さんを恋しがって泣き寝入りし、おねしょをする。看護婦さんたちは当たり前のように起こして準備をさせ、大声で学校へ送り出す。ここは病院だが長期入院(数カ月~10年以上)の施設で、親から離れて子どもの生活の場となっていた。
病気を診断し、治すことが医師の仕事とばかり考えてきた私には、けんかの仲裁に呼ばれて驚きながら、入院児たちがむくむくと、今までとは違った別の生き物に見えてきた。
それが私の本当の小児科医としての仕事の始まりだった。
【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...
【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。