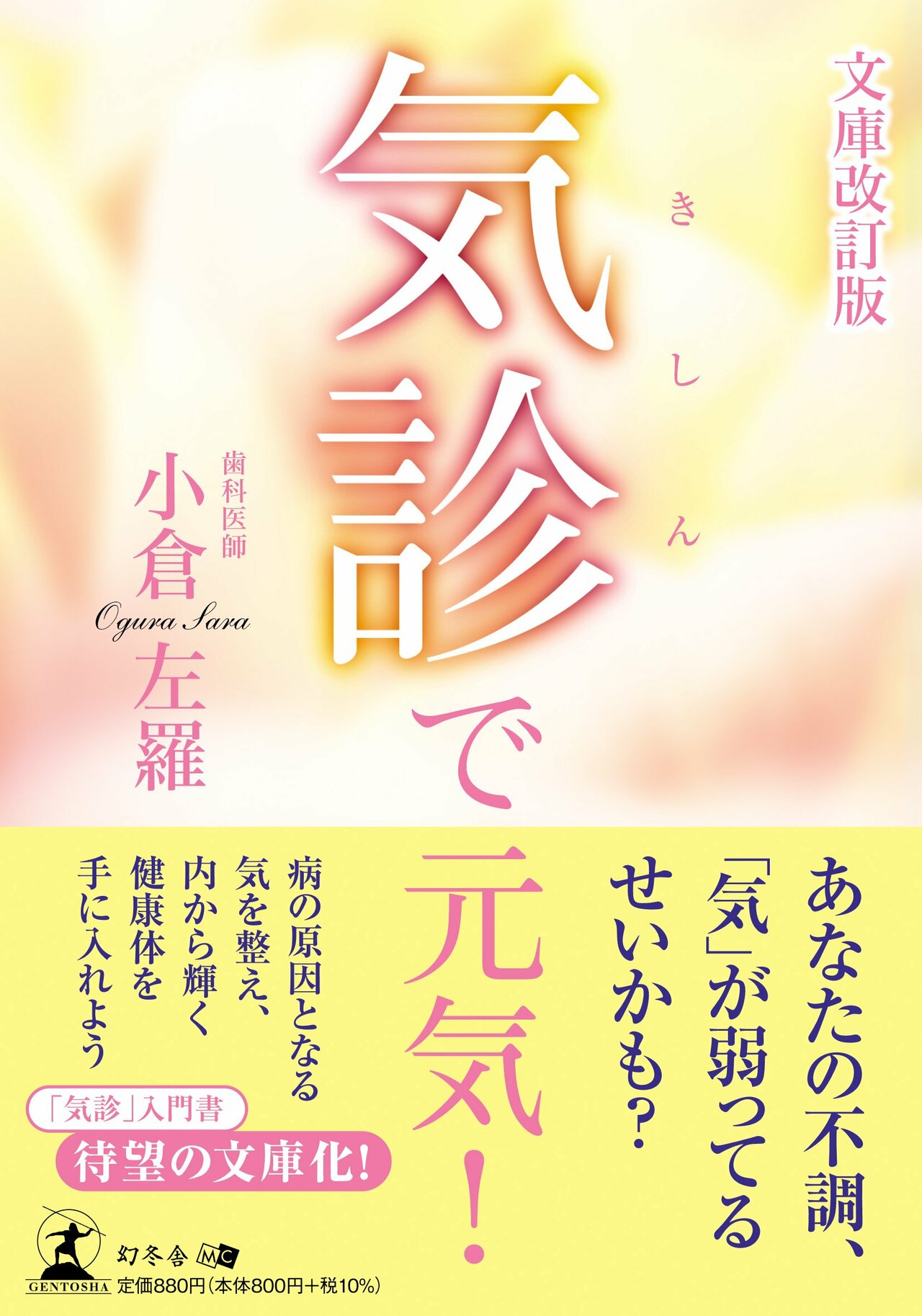【前回記事を読む】「気診」ができるようになるには? 胸鎖乳突筋の検査法と坐禅の呼吸法で自分の気を調える「気診」の鍛錬法を解説!
第二章 気診
四、身体に合うもの・合わないもの
人間の筋肉は、自分の身体に合うものを手に持ったり、口に入れたりしても本来緊張しません。ところが、身体に合わないものを手にしたり、食べたりしますと全身の筋肉が緊張します。さらに、身体の周囲を取り巻く気にも変化が表れます。
身体に合うものの場合は、気はクリアな状態ですが、合わないものを手にした場合は、気がガタガタに乱れてきます。「気診」ではその身体が変化する性質を利用して、気の診断を行います。気がクリアな状態の時は胸鎖乳突筋は柔らかく、気が乱れた状態は硬くとらえられます。
したがって「気診」では手に何か持ち、胸鎖乳突筋の変化を調べ、筋肉が緊張すればそのものは身体に合わないと判断します。すぐに次のものを持ってしまうと、前に持ったものの気が残っている場合があり、わかりにくいので、最初のうちは一旦ものを置いて、呼吸法をして気を調えてから次のものを調べるようにします。
その際、自分の胸鎖乳突筋が柔らかい状態に戻ったことを確認してから次のものを調べるのがよいでしょう。慣れてくれば次々と調べられるようになります。

例えば、タバコですが、手に持って胸鎖乳突筋をつまんでみますと、ほとんどの方が硬くなります。いかにタバコが身体に悪いかということがわかります。
またサプリメントなども、人によって合うもの、合わないものがありますので、合うか合わないかは調べてから飲むことをお勧めします。どんなにその商品の評判が良くても、自分に合わないものを飲み続けていては身体の調子が悪くなってしまいます
特に身体の調子が悪い方は、身体に合う飲食物やサプリメントが一般的に少なくなります。健康な方はそれほど気にすることではないかもしれませんが、身体の調子の悪い方は特に口に入れるものには気を配ることをお勧めします。気を調えることで体質改善ができてきますと、身体に合うものが増えてきます。