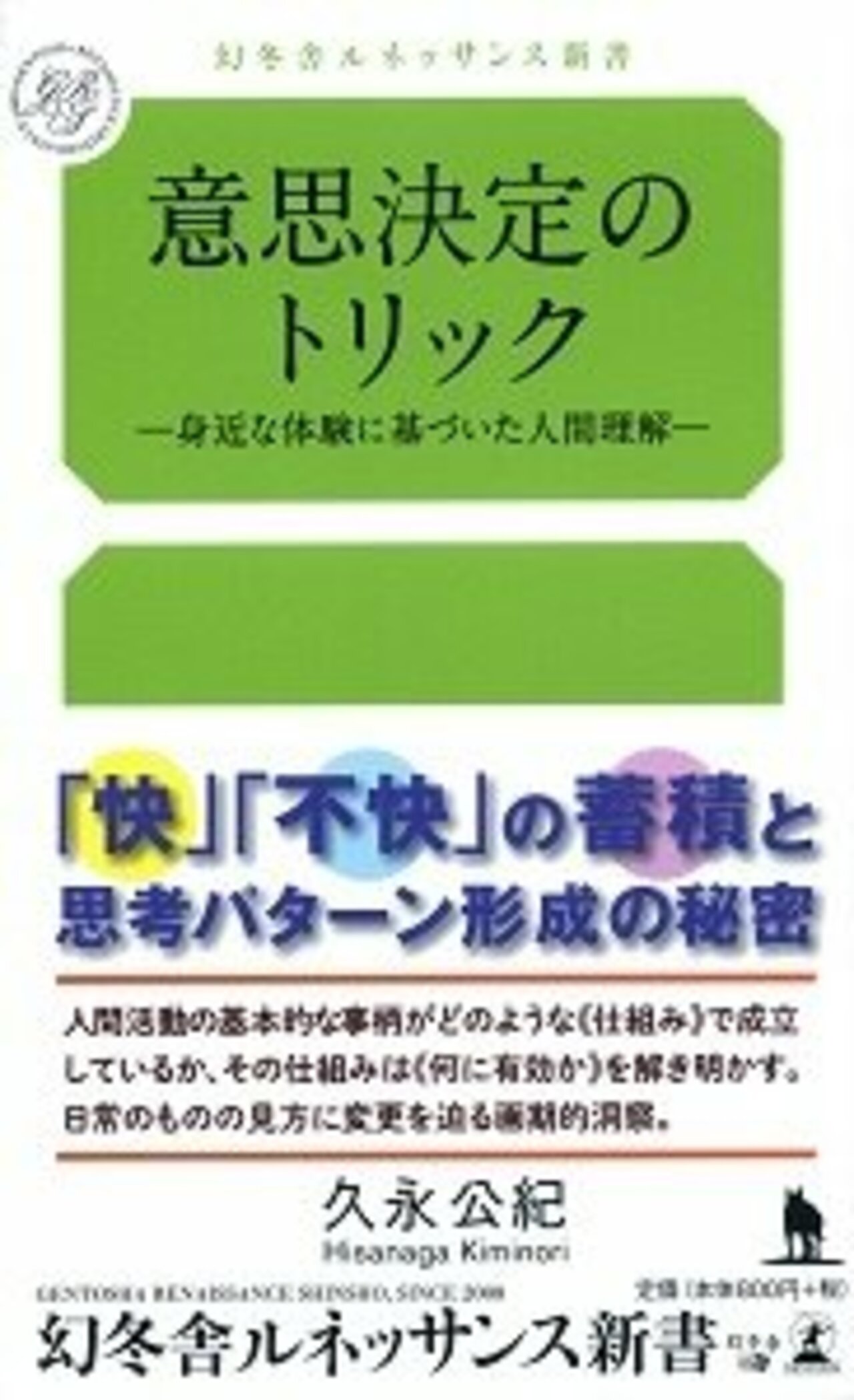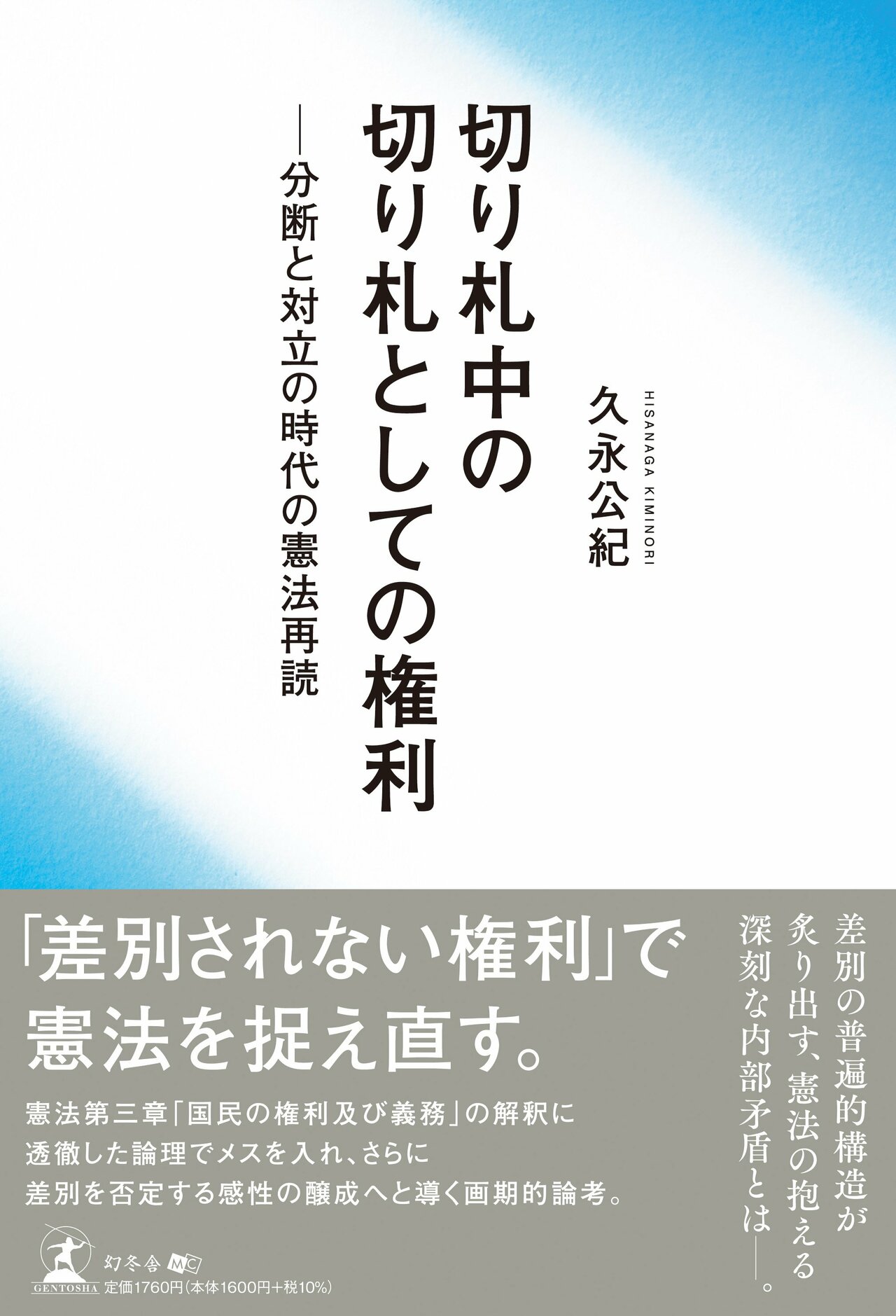このように定義することで、差別されない権利(被差別者の権利)の観点で差別か差別でないかは、差別者の主観を捨象し、客観的に(一般人の目で見てどうかで)判断することができる。
しかしながら、被差別者が心身にダメージがあるとの虚偽の主張をしている場合はどうするのか、さらに、傍目には差別され不利益を被っていると見えるが、被差別者はそれを不利益とは感じていない(あるいは歓迎している)といったマージナルなケースはどう判断するのかと問われるかもしれない。
心身のダメージについて虚偽の主張が疑われる場合は、専門医師による診断を請うのが妥当だろう。問題は、マージナルなケース。
ここで公権力による差別の例ではないが、二つ例を挙げる。一つ目は、運動部の部員が、ミスをしたところ、年下ということで劣位に置かれ、年上の部員から長時間罵倒され続けている状況。二つ目は、ある女性が職場で女性だということで劣位に置かれ、同じ働きをしている男性と比べて給与が低いという不利益を、客観的には被っている状況。
これらの例の二人が、内心でどう感じているかは傍目にはわからない。実は、前者では、上級生に気合を入れてもらうのは、目をかけてもらっていることだと歓迎していて、後者は、男性に比べ女性の給与が安いのは当たり前と刷り込まれているため、彼女の意識では不利益を感じていないとする。
この時、差別は発生しているだろうか。先程の差別の暫定的定義では、被差別者が不利益を主張する場合に、差別に当たるとした。そうすると、これらの例では、客観的には不利益を被っているにもかかわらず、当人たちは不利益を感じていないので、差別ではないことになる。では、それで構わないだろうか。
それでは困ることになる。なぜなら「差別は被差別者の受け止めの問題だから、一概にある行為を差別である、とは言えないよね」という状況が発生してしまうから。
どういうことかと言うと、差別されない権利に期待される機能として、一つは、発生してしまった差別を、差別と判別し、差別を止めさせること、もう一つは、差別の発生を抑制・防止することがある。
前者の機能に関する限り、暫定的な差別の定義でも問題はないかもしれない。しかしながら、後者の機能を考えると困ったことになる。差別はまだ発生していないので、被差別者もいない。被差別者の受け止め次第で差別か否かが決まるとすると、どういう事態が差別か決めることができず、差別の抑止・防止を図りようがなくなってしまう。
ではどうしたらよいか。
【イチオシ記事】添い寝とハグで充分だったのに…イケメンセラピストは突然身体に覆い被さり、そのまま…
【注目記事】一カ月で十キロもやせ、外見がガリガリになった夫。ただ事ではないと感じ、一番先に癌を疑った。病院へ行くよう強く言った結果…
2024年に話題を呼んだ『幸せを呼ぶシンデレラおばさんと王子様』の著者による待望の新連載『夢を叶えた、バツイチ香子と最強の恋男』が、2025年9月5日(金)22時より配信開始!
42歳、バツイチ。途方に暮れた香子が足を踏み入れたのは、「住み込みお手伝い募集」の豪邸。猛アピールから始まった出会いが、彼女の運命を激変させる——。香子の新たな人生と、最強の恋の行方にぜひご期待ください!