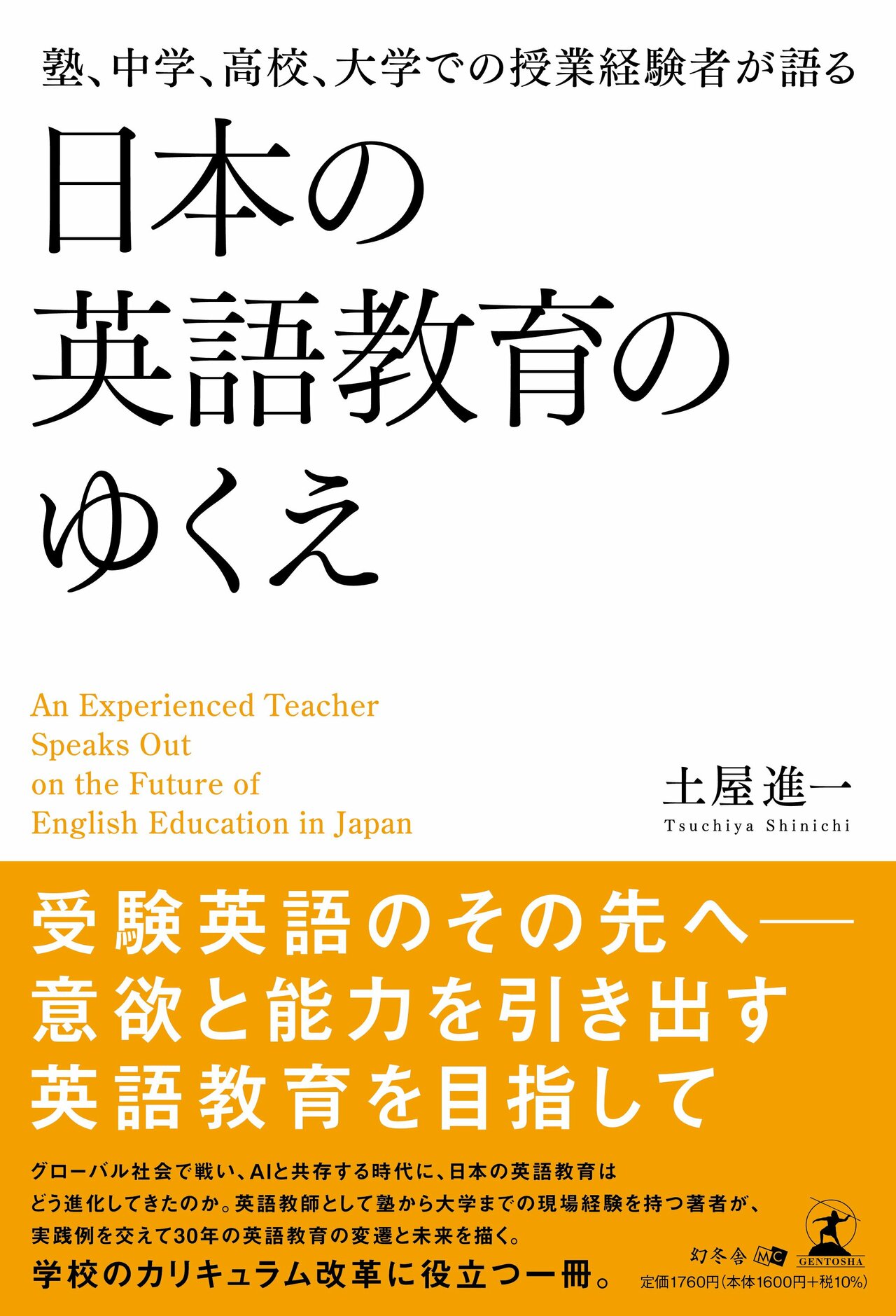第2章 「訳して読んで」音読重視の2000年代前半
2000年代に入ると、英語教育は新たな方向性を模索するようになります。文法訳読法の限界が認識され始め、生徒たちのコミュニケーション能力を高めるための新しい指導法が求められるようになりました。
この時期に注目されたのが、本文をきちんと訳し、内容を正確に理解した後の音読重視の指導法です。
特に、安河内哲也氏と安木真一氏はこの音読重視の指導法において著名な教育者です。安河内氏は、音読を通じてリスニング力やスピーキング力を高めることの重要性を提唱し、予備校を含む多くの教育現場でその実践が行われるようになりました。
彼の指導法は、内容理解と発音練習を両立させることを目指しており、音読を繰り返すことで言語習得の効率を向上させることを目的としています。具体的には、学習者がまず英文を正確に訳し、文全体の意味を把握したうえで、正しい発音や抑揚に注意しながら音読を行うという手法が取られます。
このプロセスにより、学習者は英語の音と意味を関連付けやすくなり、自然に英語に親しむことができるような環境が提供されています。さらに、音読の際には、個々の単語の発音だけでなく、文章全体のリズムやイントネーションを意識することが重視されました。
このような実践を通じて、学習者は発音の精度を高めるだけでなく、英語特有の音声の流れを体得することが期待されています。
一方、安木氏は、高等学校での音読の実践を通じて生徒たちの表現力や理解力を深める方法を研究してきました。彼は特に、大学に職を移してから、音読がもたらす効果についての研究を重ね、音読が記憶の定着や音声の改善に寄与することを示しています。
彼の指導法は、英語教育において音読の重要性を再認識させ、多くの教師がその実践を導入するきっかけとなりました。
このように、安河内氏と安木氏をはじめとする多くの実践者の貢献により、音読重視の指導法は、2000年代前半の英語教育において重要な役割を果たすようになりました。