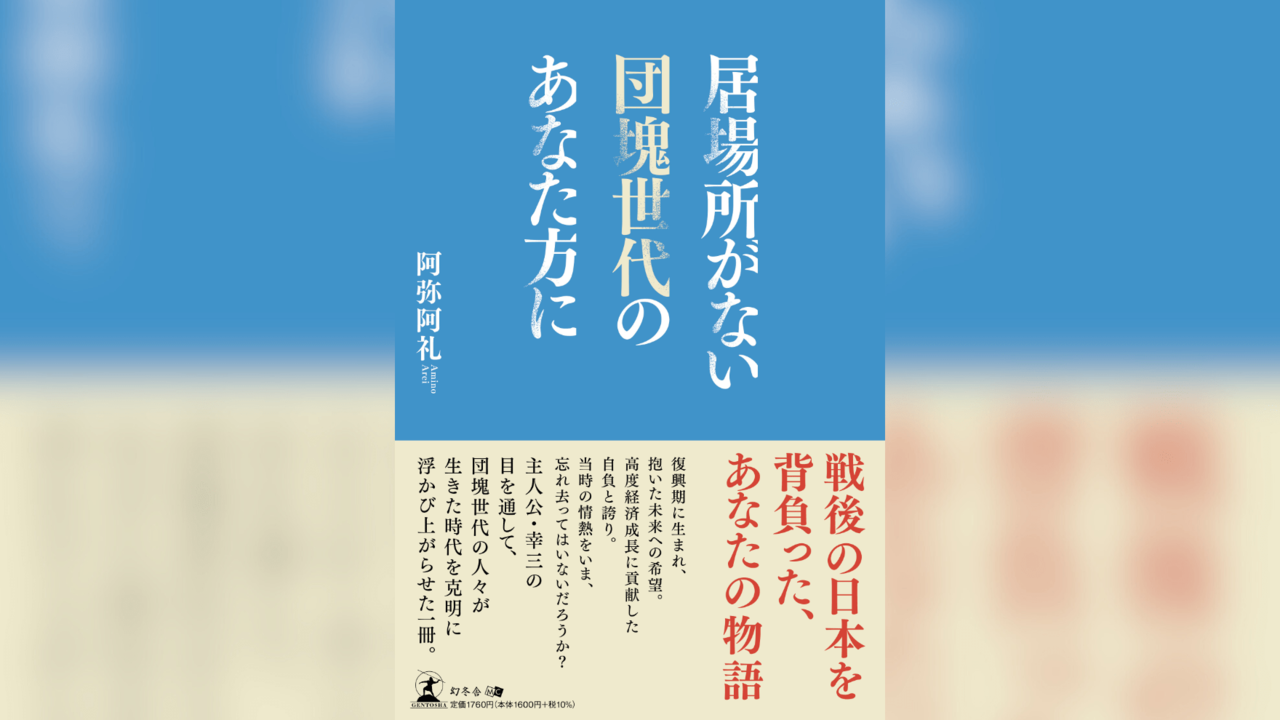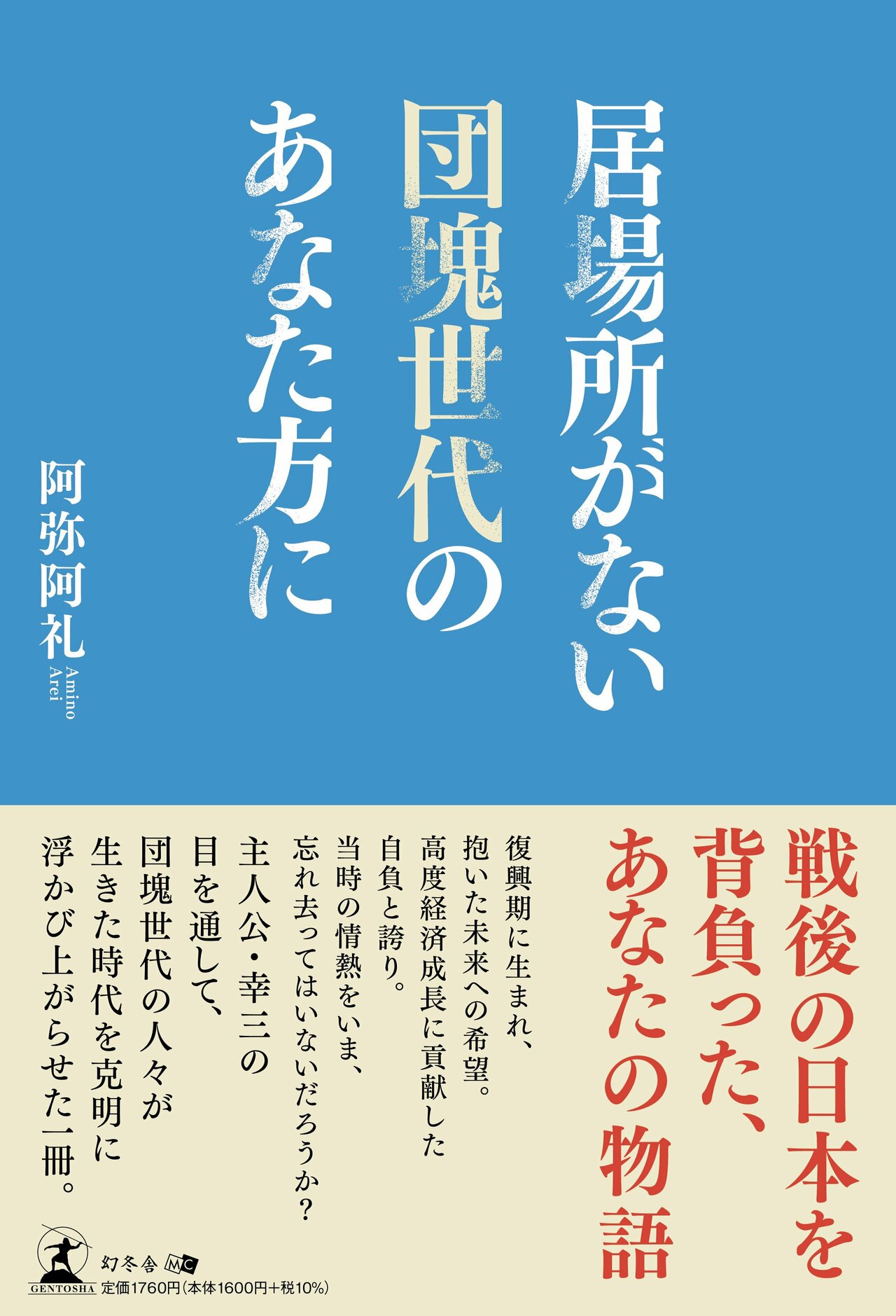【前回の記事を読む】現代の日本の礎を築き、その繁栄の基礎を築いたのは我々団塊世代であった。だからこそ日本の将来に貢献する責任と義務がある
第1章

薄桃色の甘い香りのする小さな花が咲く杏畑を、勢いよく走り抜けた。小高い丘があり、そこは幸三が、この村で一番心が落ち着くお気に入りの場所だった。
ここに来て、清々しい青草の匂いと発酵した甘い土の香りを素肌で感じ、はるか下の谷底を勢いよく流れる渓流が奏でる「ザアーバシャバシャ、ザアーバシャバシャ……」という音、飛び散る水飛沫の音と、谷底から湧き立ち上がる生臭いイオンを、胸が張り裂けそうになるほど、勢いよく吸い込んだ。
子供であれば、誰でも抱く、漠然とした当てのない目標に向かい、「今日も、頑張るぞう!」と目の前に広がる白いコブシの花が点在する橅木山に向かい、鼓膜が破れそうな大声で叫んだ。
早朝の空は、薄青色に染まり、小鳥の囀りがわずかに響く。透明で冷たい空気が満ち溢れ、眼前には金色の朝日に彩られた山々が広がっている。
岡山県と兵庫県の県境の人口700人余りの集落が幸三の住む村だった。
幸三は、戦前に栄養失調のため疫痢に罹り2歳で亡くなった長男勇一、戦後に生まれてまもなく赤痢で亡くなった次男、貞二の弟として生まれた。
平岡家の三男として生を受けた幸三は、両親に跡取りとして大切に大事に育てられた。家は、木造平屋建てで、屋根は茅葺で、部屋が5つあり、縁側に面した南向きの仏壇のある10畳の客間、夫婦の寝室、居間と食堂を兼ねた8畳の部屋と、幸三のための子供部屋と2畳ほどの風呂場があった。便所は、母屋から4メートルほど離れた北側に位置していた。
父雅之は戦後、満州から帰国した。復員後は隣町の製材所で働き、その稼いだ賃金で家計を支え、母美弥は、猫の額ほどの4畝の畑と、開墾された5反の杏畑の手入れで忙しい日々を送っていた。