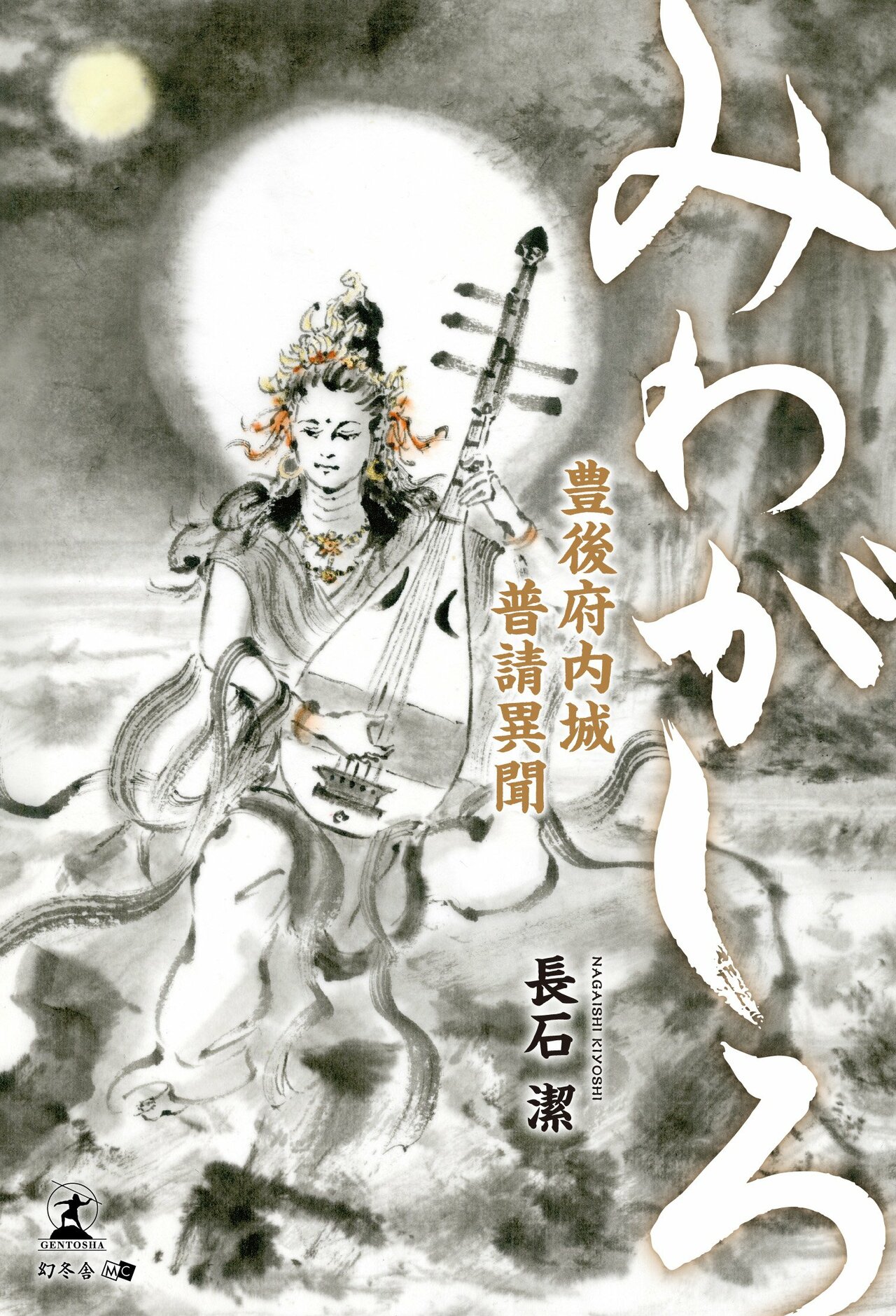年が明けて正月朔日(さくじつ)を迎えたが、雄之助は右往左往していた。年中行事の項目を暗記したものの、それで目の前の現実に対応できるほど事は生易しいものではなかった。とにかく目が追いつかないのである。
東の丸において藩主への新年挨拶と御喰摘(おくいつみ)(正月祝い膳)が藩重席から始まり、部屋替えを挟んで次々と行われていく。雄之助らはその給仕に追われるのである。しかし、そこは太田の約束通り周りの職務に習熟した先輩らに助けられ何とか乗り切った。
家老の息子と良好な関係を築き、無用な軋轢(あつれき)を生まぬよう心掛けるのは至極当たり前のことだが、雄之助については少々事情を異にした。気後れしながらも何かの役に立とうと懸命に気遣う雄之助の誠実さに、誰もが好感を抱き、手を差し伸べた。雄之助はそんな人徳も備えていた。
元日は、その他にも三日の「射初(いぞ)め式」への参加要請を認(したた)めた各方面への回状を配り、日田代官と長崎奉行に年賀挨拶を行うための手筈(てはず)を整えるなど多事多端(たじたたん)であったが、翌日からも、年始の催しが目白押しであった。
二日は、城下各町の代表者、医師、庄屋、宿老(しゅくろう)、組頭らの年始挨拶を藩主が受けたが、それら参列者の通門手配や挨拶の順番の段取りと参列者の紹介など、総合的差配を行う用人役の下で慌ただしく動いた。
また、各方面に「年始御便り」を出状した。各方面とは、御隠居(ごいんきょ)(前藩主)、藩主子息、大奥様(前藩主正室)などの藩主親族であり、また、藩主在府中であれば江戸の藩主へも送ることになるが、それらの文案ひな形も相手ごとに「年中行事」に記載してあった。
三日は、郷中大小の庄屋らの年始挨拶を藩主が受け、それが終わると、「射初め式」が挙行された。夕方には松囃子(まつばやし)が城内で演じられ、これには町人の観覧も許された。
四日は、城下の寺社、山伏らの年始挨拶を藩主が受け、それが終わると、「御乗初(おのりぞ)め式」(馬)が催された。
五日は、由原(ゆすはら)一山の年始挨拶を藩主が受け、それが終わると、「鎗兵法遣初(そうへいほうやらいぞ)め式」が執り行われた。
その後、八日の「御旗差初(みはたさしぞ)め式」を経て、十一日の「孝経御読初(こうきょうおよみぞ)め」を以て一連の年始行事が終了した。