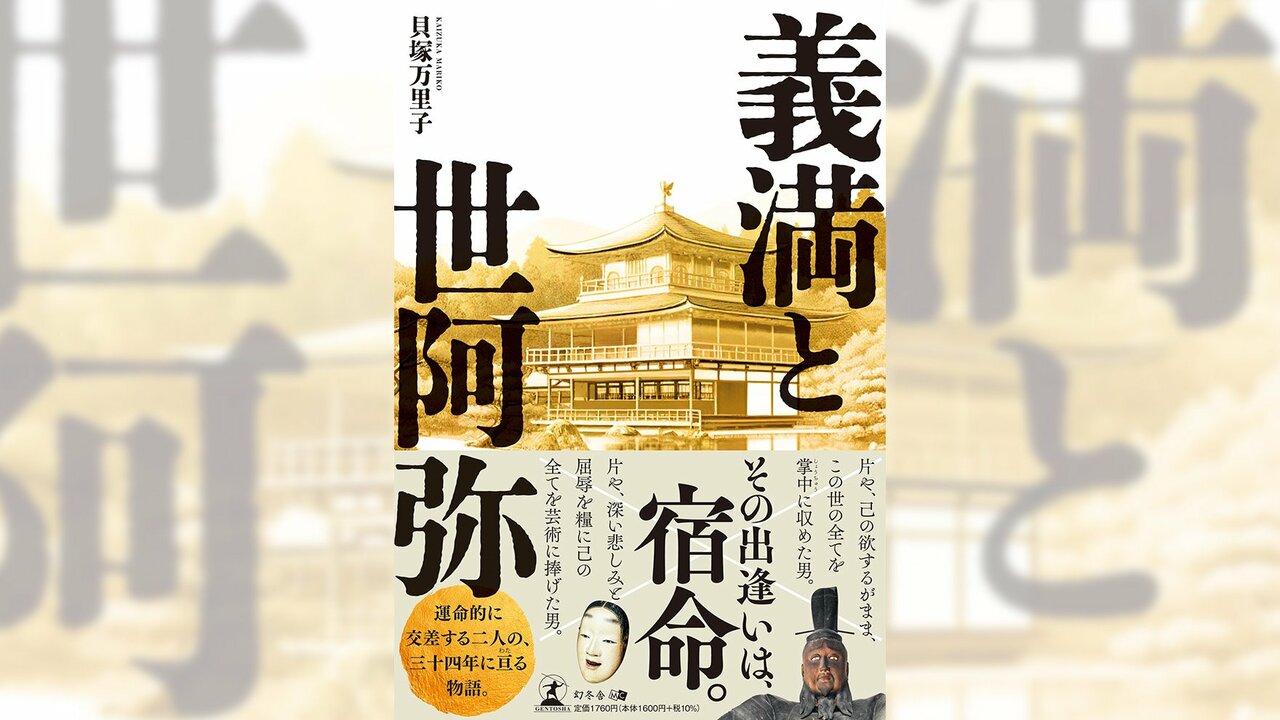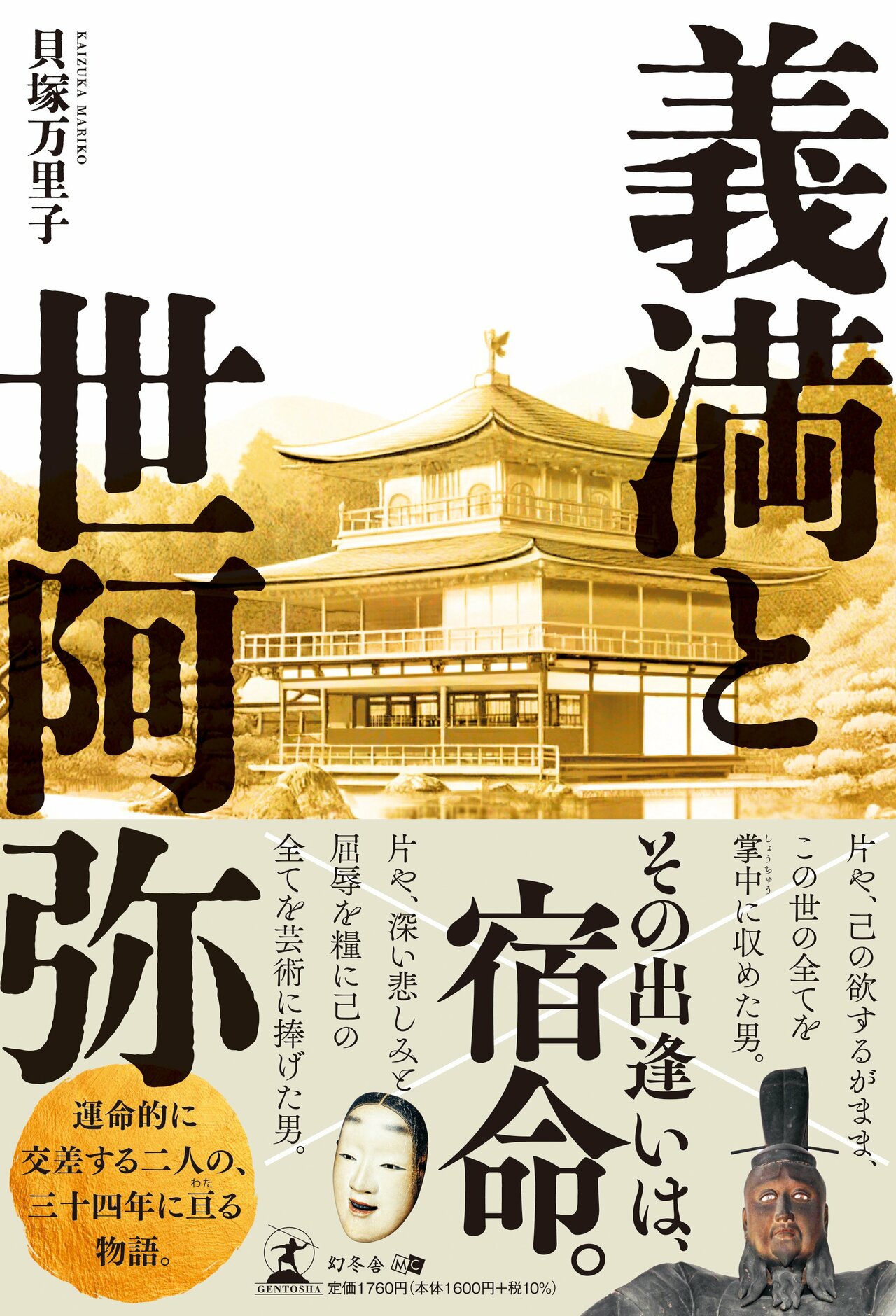【前回の記事を読む】連歌など結局は言葉遊び、虚しい暇つぶしに過ぎない様だ。俺が芸術に求めるのは、もっと違う何かだ
出会い(一三七四年)
世阿弥は、鳥の囀(さえず)る美しい庭園を眺めながら自分の世界に没入してしまった。気が付くともう、二条良基の番である。
「聞く人ぞー 心空なるー ほととぎすー」
ぼんやりと庭を眺める世阿弥に気が付いた人々は大笑いをした。
「確かに垂髪は先程からうつけの様にほととぎすの鳴く声を聞いておられたな。お茶を運んで来たおなごの事でも考えておいでか。それとも、もっと大切な御仁の事を考えておいでかな」
公家の一人が思わせぶりに世阿弥の顔を覗き込んだが、真剣に句を捻る世阿弥は気が付かないふりをした。
二条良基の句は、実は新古今集にある馬内侍(うまのないし)の歌『心のみ 空になりつつほととぎす』を借用したものだったが、気が付いた者は少なかった。ともあれ二条良基は自分の句の出来栄えに満足だった。最初の重い句からは打って変わって軽い句。一座もすっかり和み、理想とする平安貴族的な雰囲気に少し近づいたかの様であった。
ややあって、世阿弥が自分の句を澄んだ高い声で、ゆっくりと朗誦し出した。
「しげる若葉はー ただ松の色ー」
一同はその声に、姿に、若さに、すっかり魅了された。しかも良く良くその句を吟味すれば、極めて技巧的で、二条良基の句以上に貴族的な香りが漂っている。
まず、鳥の鳴き声という聴覚イメージの後に緑の若葉という視覚イメージ、というコントラストが良い。実際に二条家の庭は緑で溢れ返っている。又、松は「待つ」の掛(か)け詞(ことば)であるので、ただ松、とは只待っている、という意味にも読み取れる。
つまり、庭の若葉を描写しつつ、私は只連歌の順番を待っていただけですよ、とも言っているのである。これこそ貴族的な連歌の見本である。皆その見事さに舌を巻くと同時に、本当にこの年若い稚児が掛け詞を分かって使ったのだろうか、と疑った。