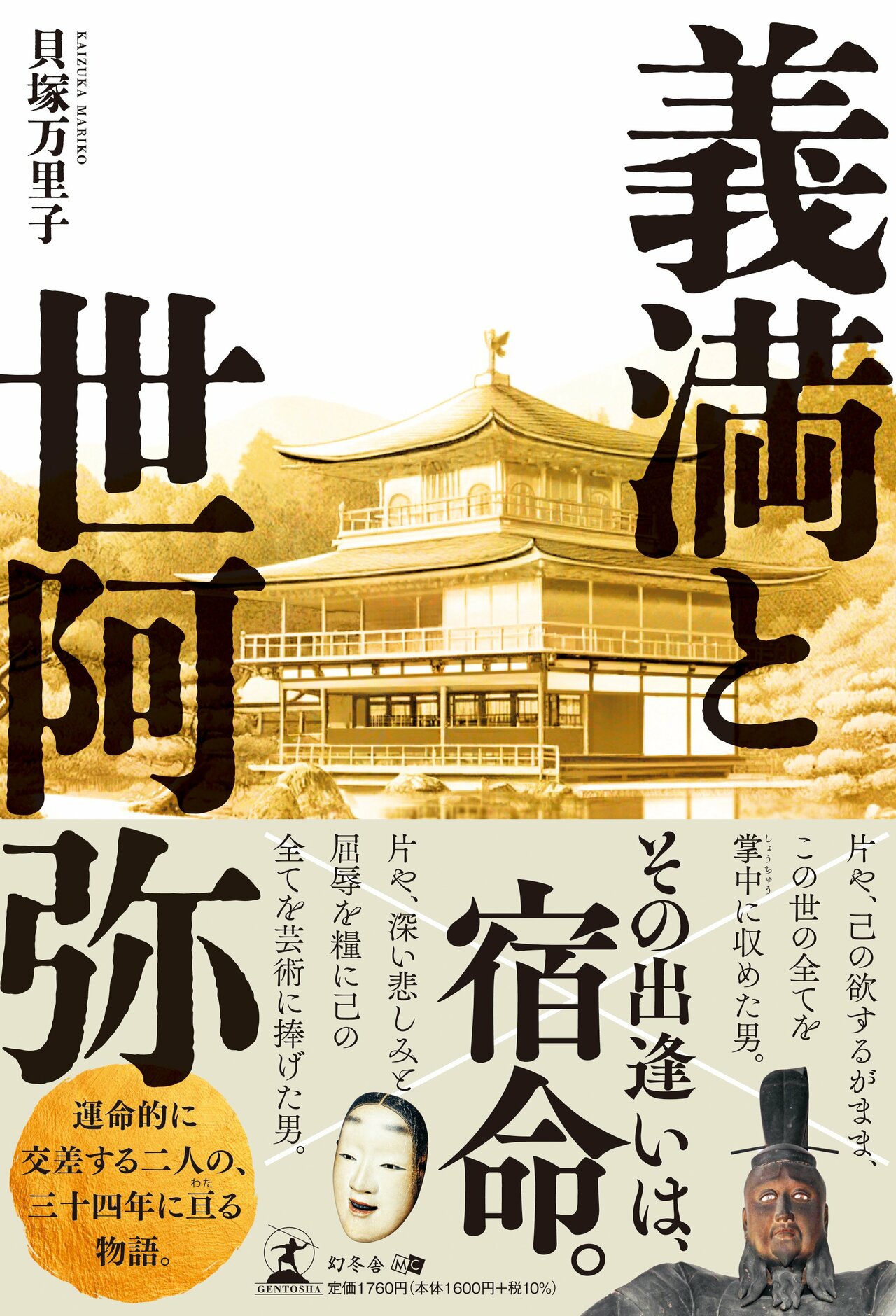「松は待つの掛け詞、私は只順番を待っているだけ、という意味を掛けられているのですな」
皆の疑問を二条良基が確認した。
「左様で御座います」答えを聞くや、絶賛の嵐となった。
「鳥の鳴き声から若葉の緑という流れが素晴らしい」
「何とも古風で雅びな香りが致しますな」
「掛詞がお見事。これは本日最高の句ではありませんか、良基殿」
「如何にも。以ての外の美、とでも申しましょうか」
「以ての外の美、成程、正にその一言に尽きますな」
公家も高僧達も、良基の結論を聞くや、口々に世阿弥の句を褒めそやした。能の世界は観客に受けるか受けないかが死活問題だから、常に有りと凡ゆる技巧を凝らさねばならない。この程度の技巧で大騒ぎする貴族達は何と呑気な連中だろうと、世阿弥は驚いた。そしていつか自分で能を作る時は掛け詞をふんだんに使ってやろうと心に決めたのであった。
義満は一三七八年三月二十四日に権大納言に任ぜられて大層喜んだ。
天下の将軍が何故官位に拘るか。京都では何より官位が重要なのである。幾ら政治上の実権を握っていても、征夷大将軍というのは天皇に任ぜられた武士の棟梁に過ぎず、絶対的に尊敬されていた訳では無い。
公家の中には、こんな若い武士が権大納言だとは呆れた世の中だ、などと日記に書き付ける者もいたが、聡明で公家に劣らぬ教養を備えた義満の出世は、異例であっても当然、というのが一般的な受け止め方であった。因みに祖父尊氏、父義詮(よしあきら)、共に三十歳過ぎて権大納言と成り、それが最高官位であった。