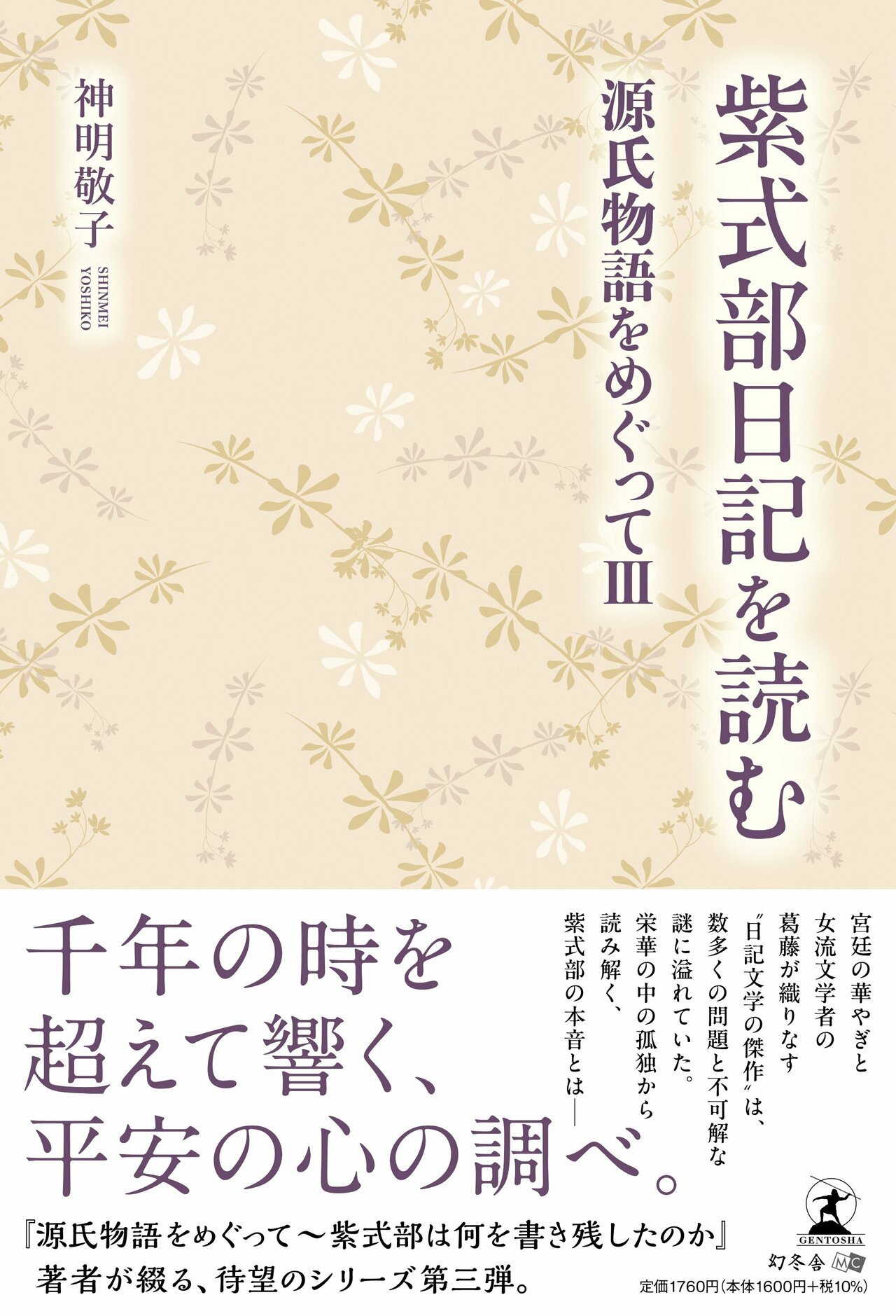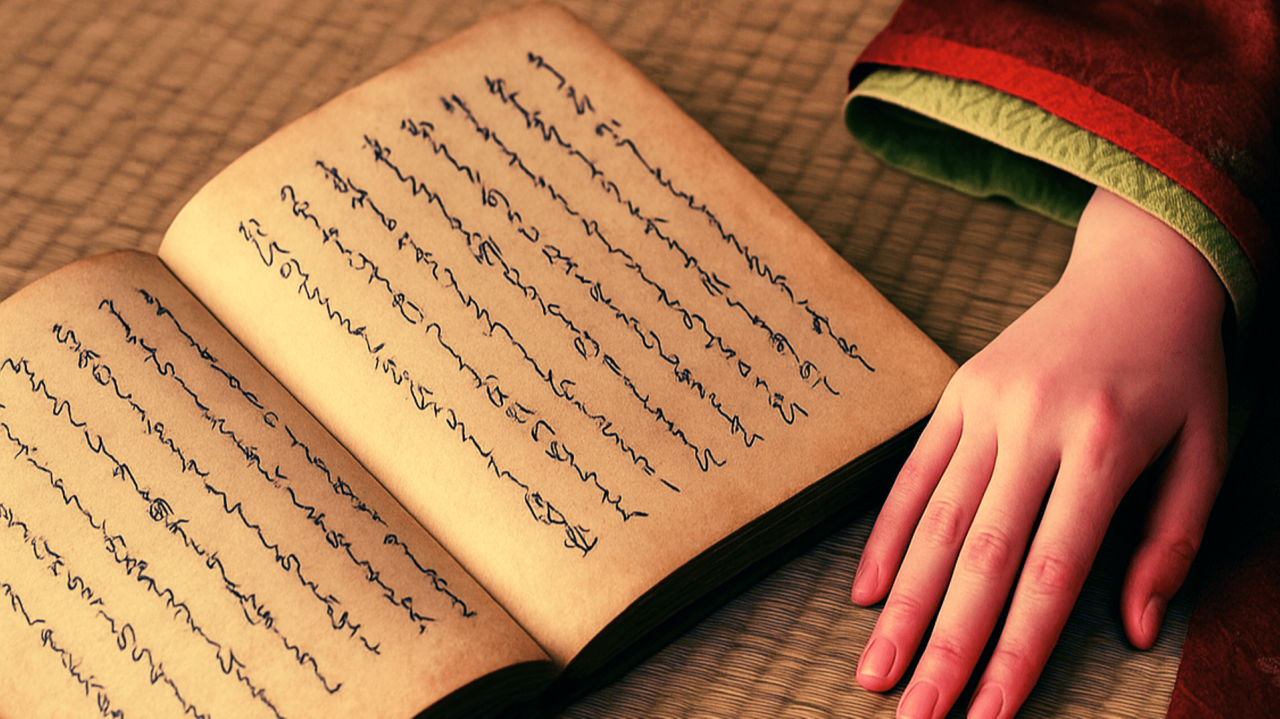二 日記はいつ書かれたか
日記は七回書かれた
寛弘五年八月に書き始められた日記は、寛弘六年正月まで、次のように五回にわたって書かれたと考えられる。
①寛弘五年八月中旬~八月二十六日
②寛弘五年九月九日~九月十九日
③寛弘五年十月十余日~十月十七日
④寛弘五年十一月一日~十一月二十八日
⑤寛弘五年十二月二十九日~寛弘六年正月三日
これらの日記は、八月から毎月書かれ、十二月だけが翌月に及んでいるが、これは十一月の出仕が不規則に二回あったことの影響が及んでいると考えられる。⑤で日記が閉じられ、二回の日記が追加されて、日記は全部で七回書かれたと考えられる。
これらの日記は、出仕して里へ帰って、次の出仕までの間に書かれたと考えられる。それぞれの箇所につい最近の出来事であることを思わせる語句が見られる。
寛弘六年正月に、「今年」と言っている。
ことしの御まかなひは大納言の君。(一八七)
寛弘七年正月に、「今年」と言っている。
ことし正月三日まで、(二一五)
ことしの朔日(ついたち)、御まかなひ宰相の君、(二一五)
二つの正月の記事は、それぞれ、その年に書かれている。
寛弘六年正月の記事として、
をととしの夏ごろより、楽府(がふ)といふ書二巻(ふみにくわん)をぞ、しどけなながら教へたてきこえさせてはべる、(二一〇)
とあるので、彰子への楽府進講は寛弘四年の夏ごろからである。
寛弘六年正月の日記に、
このごろ反古(ほんご)もみな破(や)り焼きうしなひ、雛などの屋づくりに、この春しはべりにし後、人の文もはべらず、紙にはわざと書かじと思ひはべるぞ、いとやつれたる。(二一一)
とあり、「このごろ」反古紙を処分し、雛の家を作ったのが「この春」のことであるという。寛弘六年正月の作者は、十日ごろまで出仕し、その後里へ帰り、一月中旬に反古紙を処分し雛の家作りをして、一月下旬にこの日記を書いていると考えられる。