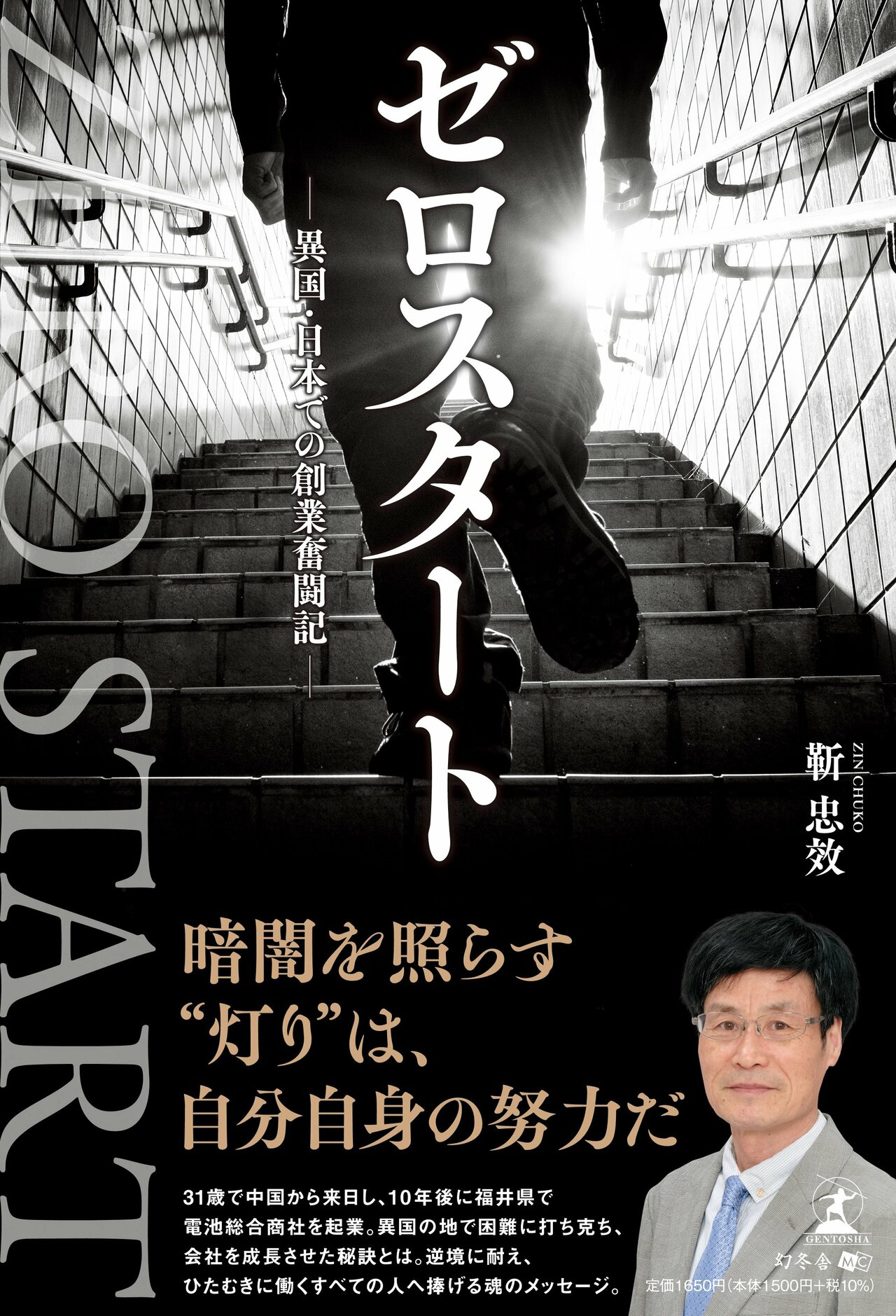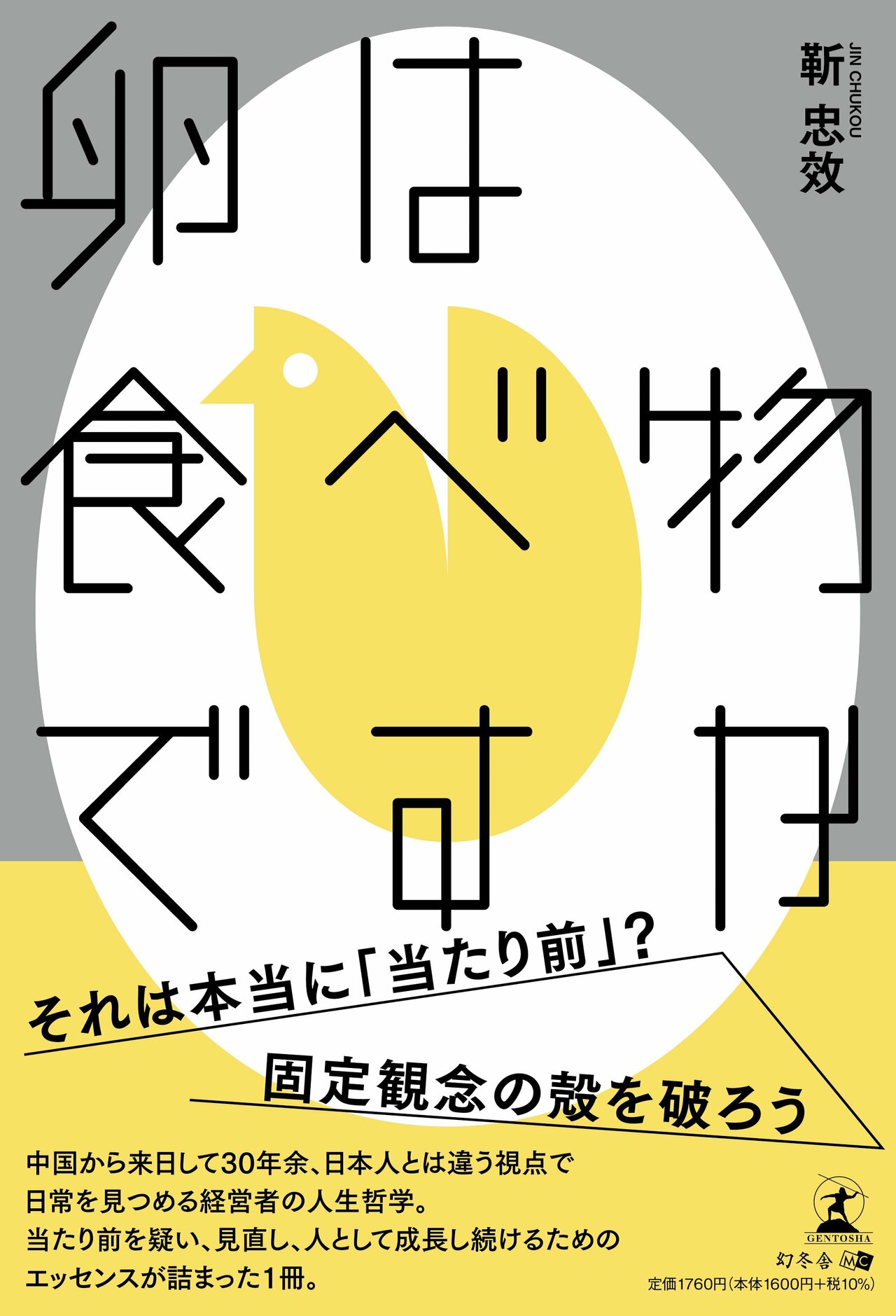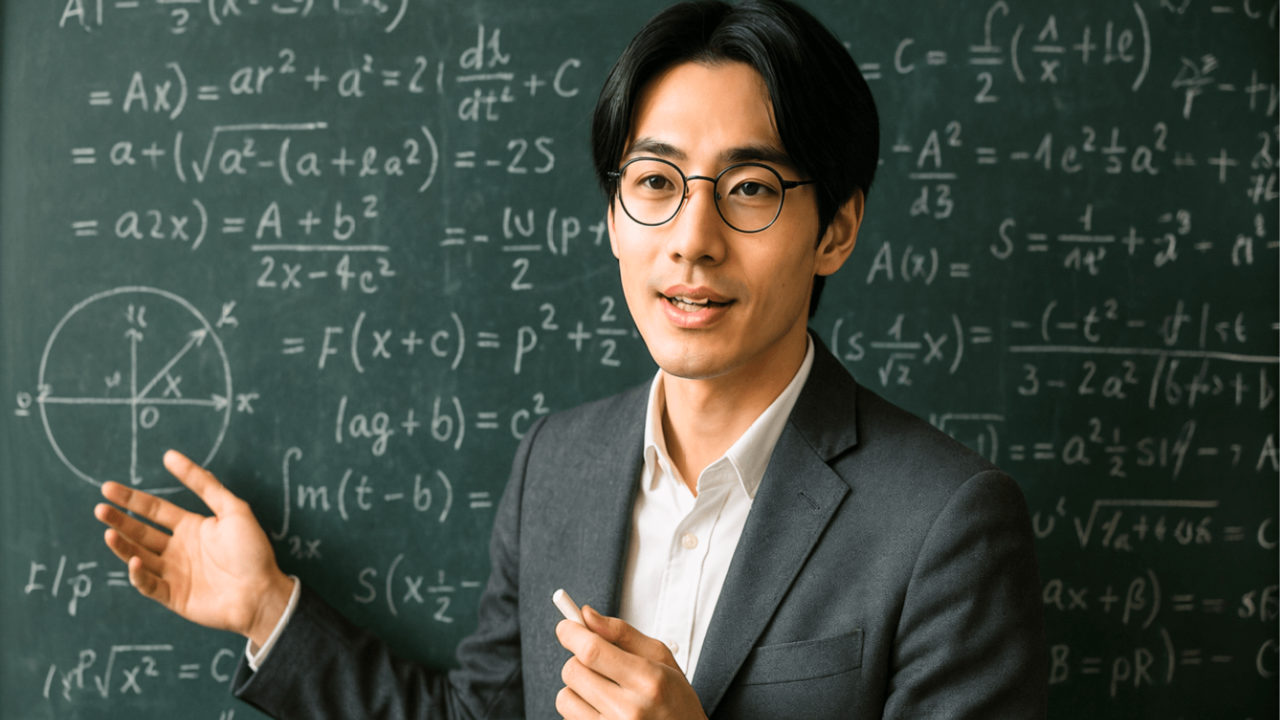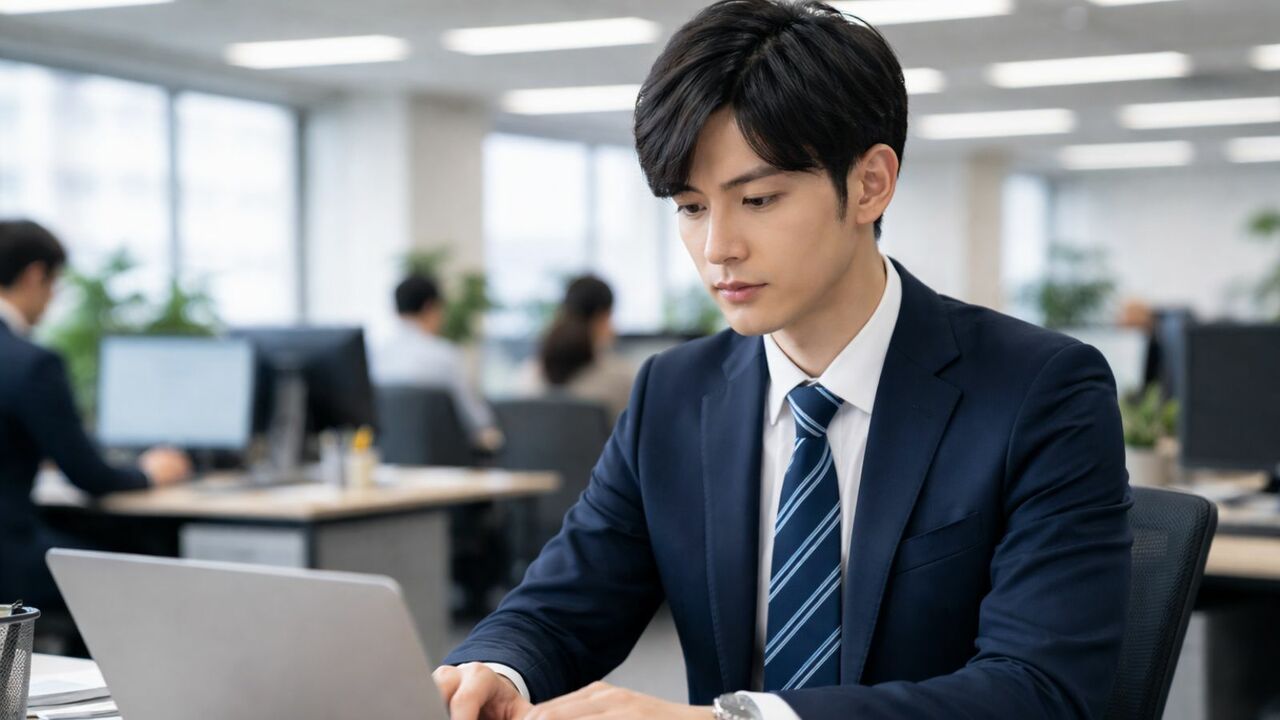上善は水の如しの意味するものは何ですか
水は人類の生存に不可欠な物質の一つでありながら、人生の哲学を説明するのにとくに理解しやすいものです。
たとえば、中国古代の哲人・老子はこういいました。
上善(じょうぜん)は水(みず)の若(ごと)し
水(みず)は善(よ)く万物(ばんぶつ)を利(り)して争(あらそ)わず
衆人(しゅうじん)の悪(にく)む所(ところ)に処(お)る
故(ゆえ)に道(みち)に幾(ちか)し
→もっとも優れた「善」は水のようなものだ
→水は万物を助け、育てて自己を主張せず
→だれもが嫌うような低い方へと流れて、そこに身を置く
→だから正しい道に近いのだ
老子は人生を水にたとえて、人生の運行は水のように滑らかで、控えめであるべきだといっています。柔軟で、争わず、流れに任せ、謙虚で寛容で自然な生き方を提唱し、人生、道徳、政治に関する深い考えを伝えました。
豊臣秀吉の家臣として日本の戦国時代に活躍した武将、黒田官兵衛(くろだかんべえ)は、知的な軍略家として知られています。
黒田官兵衛はさまざまな功績を挙げましたが、とくに有名なのは、秀吉の朝鮮出兵や、関ヶ原の戦いにおける活躍でした。彼の戦略的な才能や軍事的な功績は、日本の歴史において重要な位置を占めています。
黒田官兵衛は中国の古い文書、なかでも「老子」の水に関する文をよく読み、その内容を吟味したことで知られています。それをもとに官兵衛は、人生の指針として「水五訓」をまとめました。