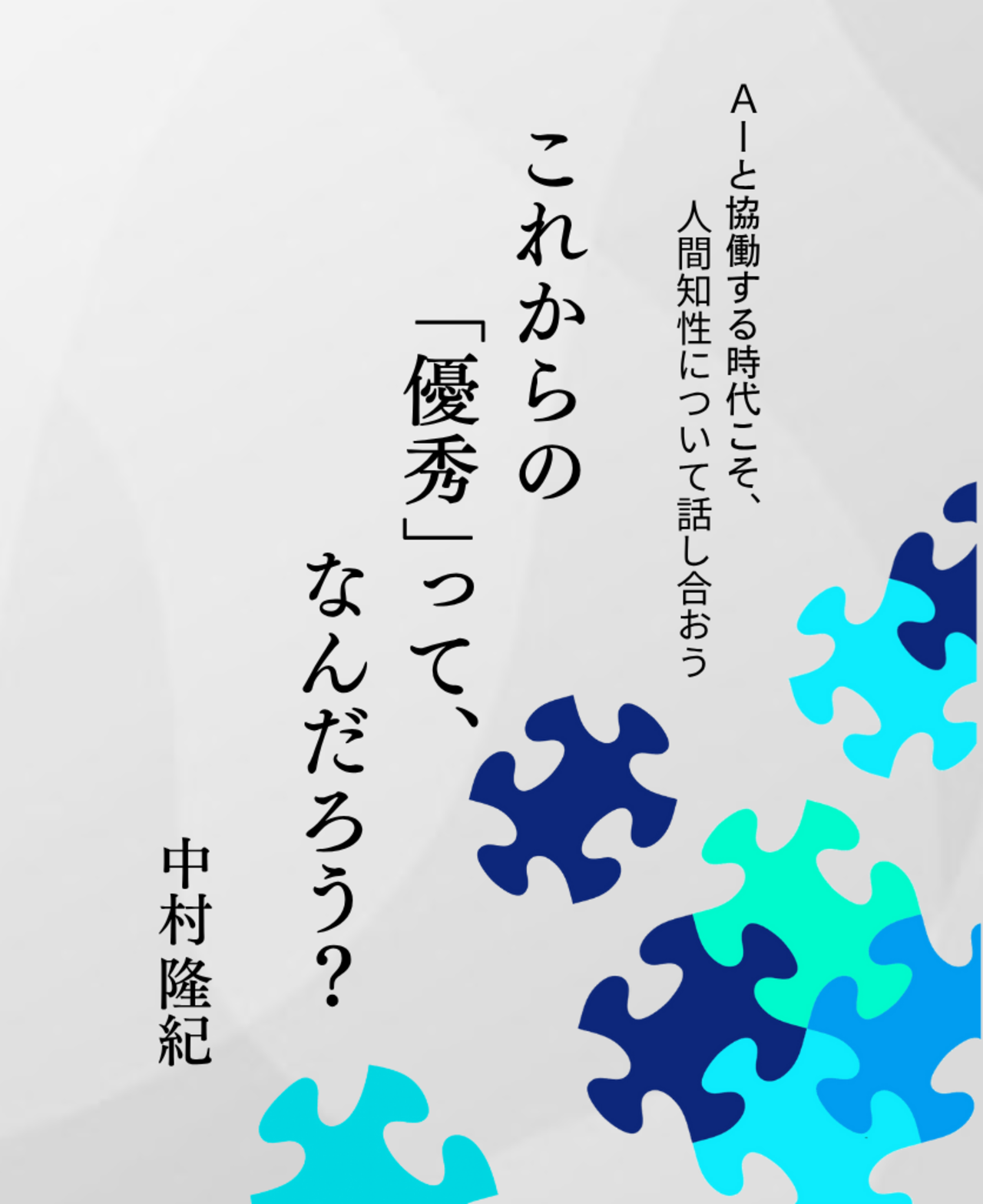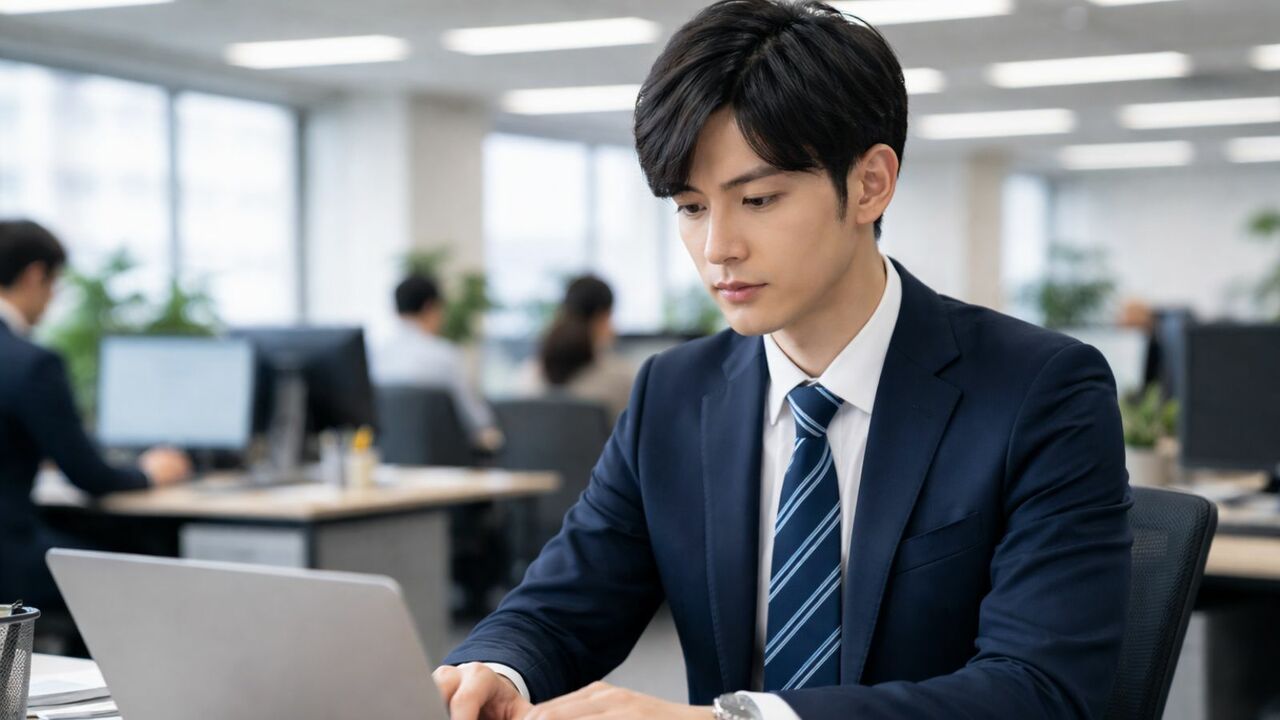「我々がはじめた改革は、組織と人間の信頼関係を、もう一度つくり直すという意味もある。みんなでどう楽しく働き合えるか、中心は気持ちの〈質〉だと思う」
「梶原さん、そこが根元ですね。まだまだ世の中は、効率主導の文脈で、経営と人間を計画経済のプラモデルように考えていそうですが。熱い〈質〉にしていきましょう。わははは」
石橋さんは、ちょっと面食らっていた。わたしたちが職務の新しいオペレーションだと思って勉強していることを、上層部は平然と解釈を変え、飛び越えていく。そして、ひとのことを想っている。
「吉岡くん、そのセンセの企画、〈パートさん合コン〉に似ているじゃないか」
梶原さんが、言う。
「あはは、みなさん〈合コン〉って覚えているんですね。毎日の出来事に目を凝らして、耳を澄ませ、立場を越えてフリーに話すところは……たしかに、あの井戸端会に似ています」
「感づき合いというのかな。そうした場づくりが、職階・職能を軸とした人財開発のルーティンかといわれれば……みんな、そこのギャップで悩んでくれたんだと思うけど。しかし、そもそも企業における学びとはなにか、この際、ちゃぶ台をひっくり返してもいいんじゃないか?」
和田さんが応える。
「創造的人財育成は、『研修受けたら、はい、できました』というたぐいのものではないですね。短絡的な学びだけではないことに、提供する側も受ける側も、目をつぶってきたのかもしれません」
「創造性は、全員で、ずっと磨くべき土台だ。営業も、本社筋だって、他人ごとにしてはいけない。DX推進もみんなのおかげで軌道に乗ってきたことだし、改めて創造性のアクセルを踏もう。まずは、今後のはじめ方だな」
梶原さんは、窓の外を眺めて考えた。本社18階のかなたには、白く輝くソリッドな入道雲が湧いている。最近は、初夏も夏も、一緒くたにやってくるな。
「これは、単なる人事領域の問題じゃない。私は、社員だけではなくて、学生も生産者も、創造性の豊かなステークホルダーが当社に集まってくれるようにならなければ、数字を利口につくったところで、先がないと思っている。
本当に変えたいのは、ドライな経営が苦手としてきた、会社の文化風土だ……この件は、人財開発からちょっとはみ出して、ふくらませてみようか。というか、私のところで直轄プロジェクトにしよう。一緒にやろう」
どこかで経営学の導師が言ってたな。イノベーティブな経営案件は、トップが直接指揮を執るべきだ。新しい仕事は、現存するセクターではなく、新しいセクターで執行すべきだ。
次回更新は8月27日(水)、11時の予定です。
👉『これからの「優秀」って、なんだろう?』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...