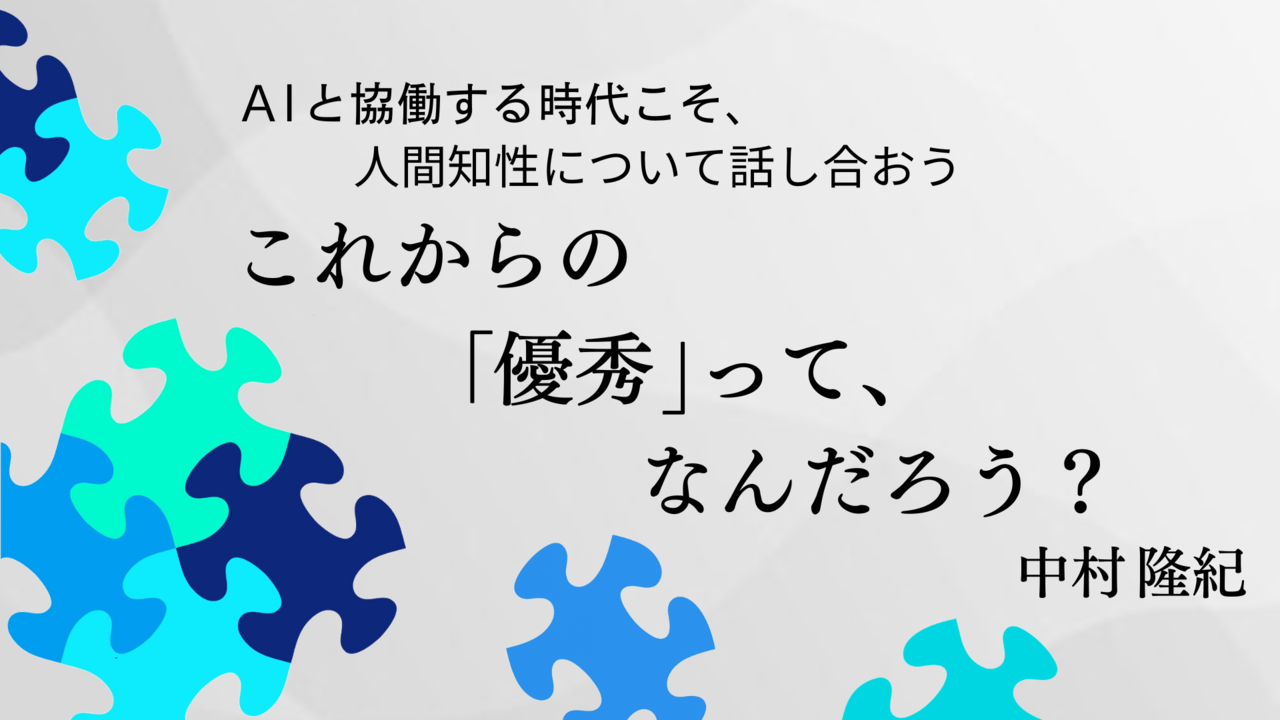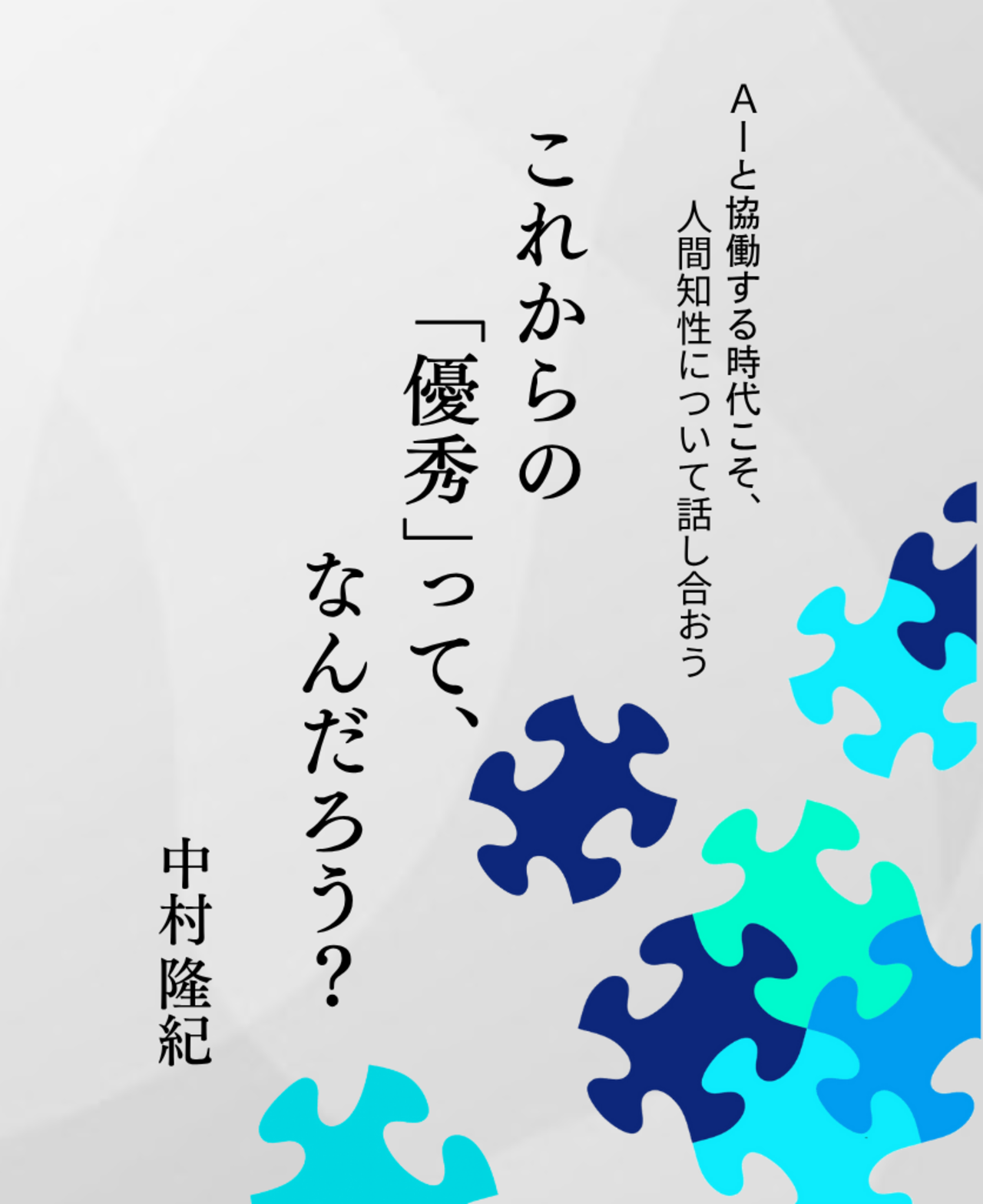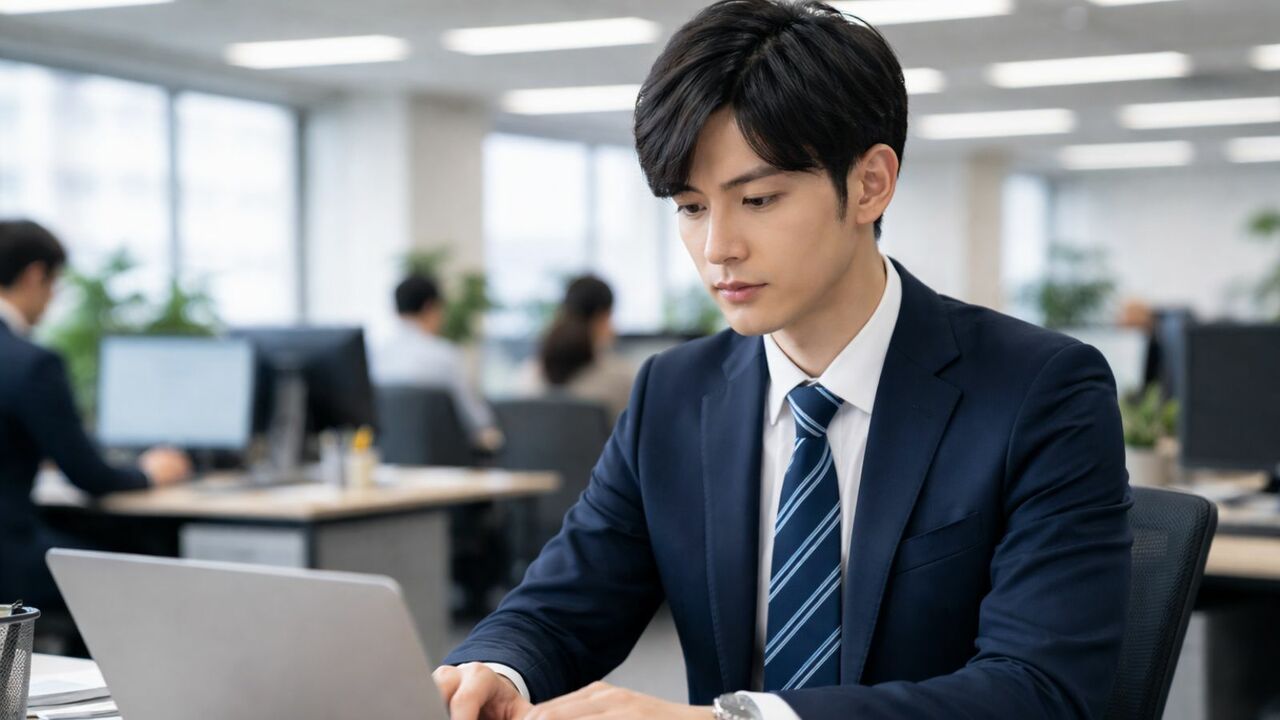【前回記事を読む】「アンドロイドとつき合う方が合理的にしあわせ」――恋愛に50ぐらいのパターンしかないなら、ハプニングだらけの恋をするより…
第一章 知覚センサー、機能不全
「23年度から人的資本経営の開示がはじまりましたが、まだ各社、周縁のバズワードを横並びで整理しているところでしょう。エンゲージメント、ウェルビーイングといった概念や、女性活躍、男性育休、健康経営、キャリアパス多様性などの制度とか。経営戦略に合わせて、育成の内容を独自に磨き抜いていくのは、当社も含めて、どこも山登りの一合目です」
「会社から見れば、人財は成長のための資本だが、我々みんな、血の通った人間だ。工場監査のマニュアルみたいに、人間を機能視しすぎた評価測定はしたくない。特に創造性は」
「わかります。〈組織改革〉が、お題目を並べ替えた〈書式改革〉になってはいけませんよね。いつもの絵に描いた餅になってしまいます。今回は、経営管理があんまりそっちへ行き過ぎると、教育にもROIを求めるような、逆にひとが萎えることになる懸念も持っています」
「とにかく社内のみんなが、関心と期待を持ってほしいね。達成指標ばかりじゃなくてね」
——バブルの頃は〈24時間働けますか〉的な量的エネルギーの時代、その後は長引く停滞の中でリスクを恐れる萎縮の時期が続き、働き方改革で効率が主流となった。その〈失われた30年〉といわれる間に、なにより働くモチベーションが、失われてしまったような気がする。
いま、効率から価値創造へと、時代がまた変わりはじめた。価値創造は、効率の方程式では生まれない。みんなで、ああだこうだ揉み合える組織にならないと、新しい価値は芽生えないのだ。
——変化に対する危機感の共有は、じつに難しい。