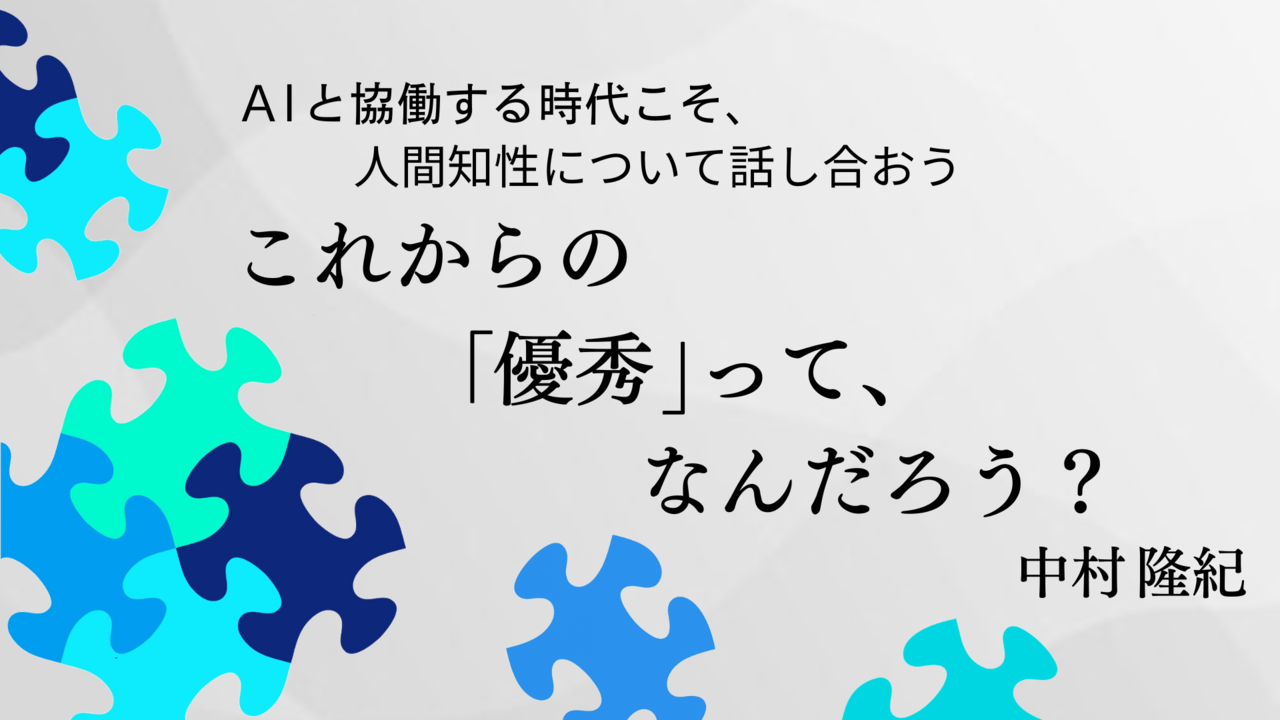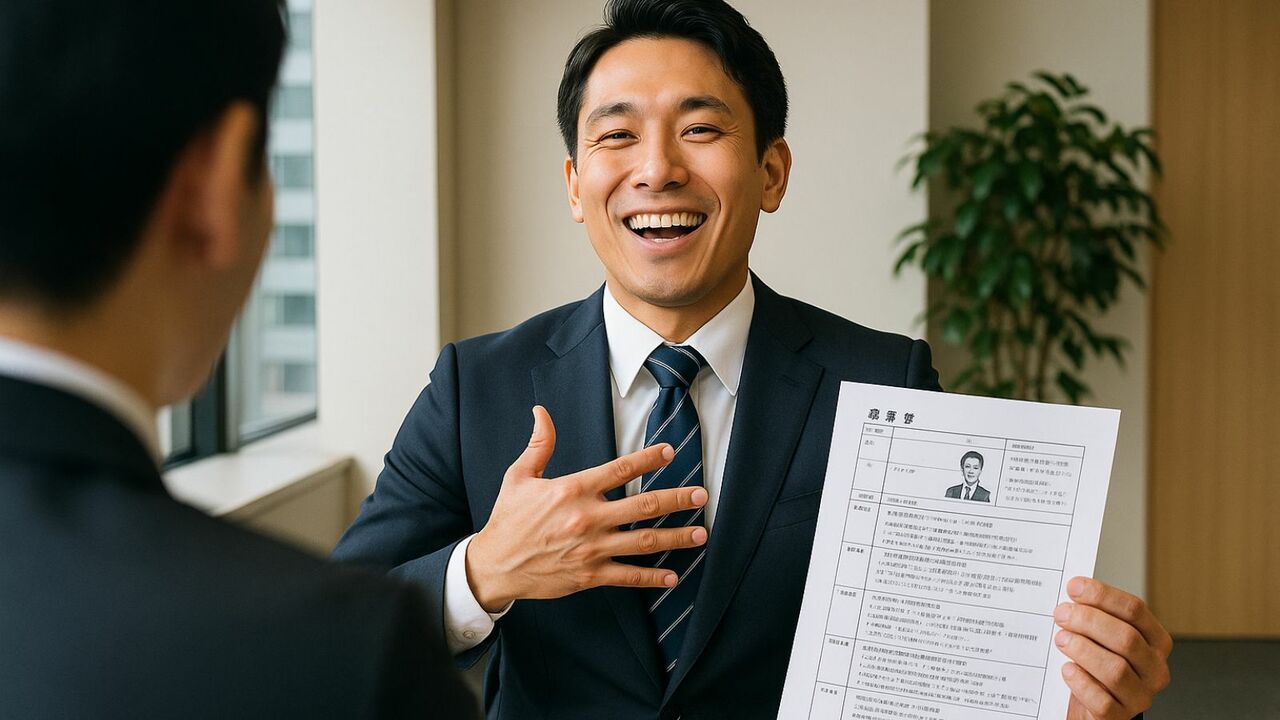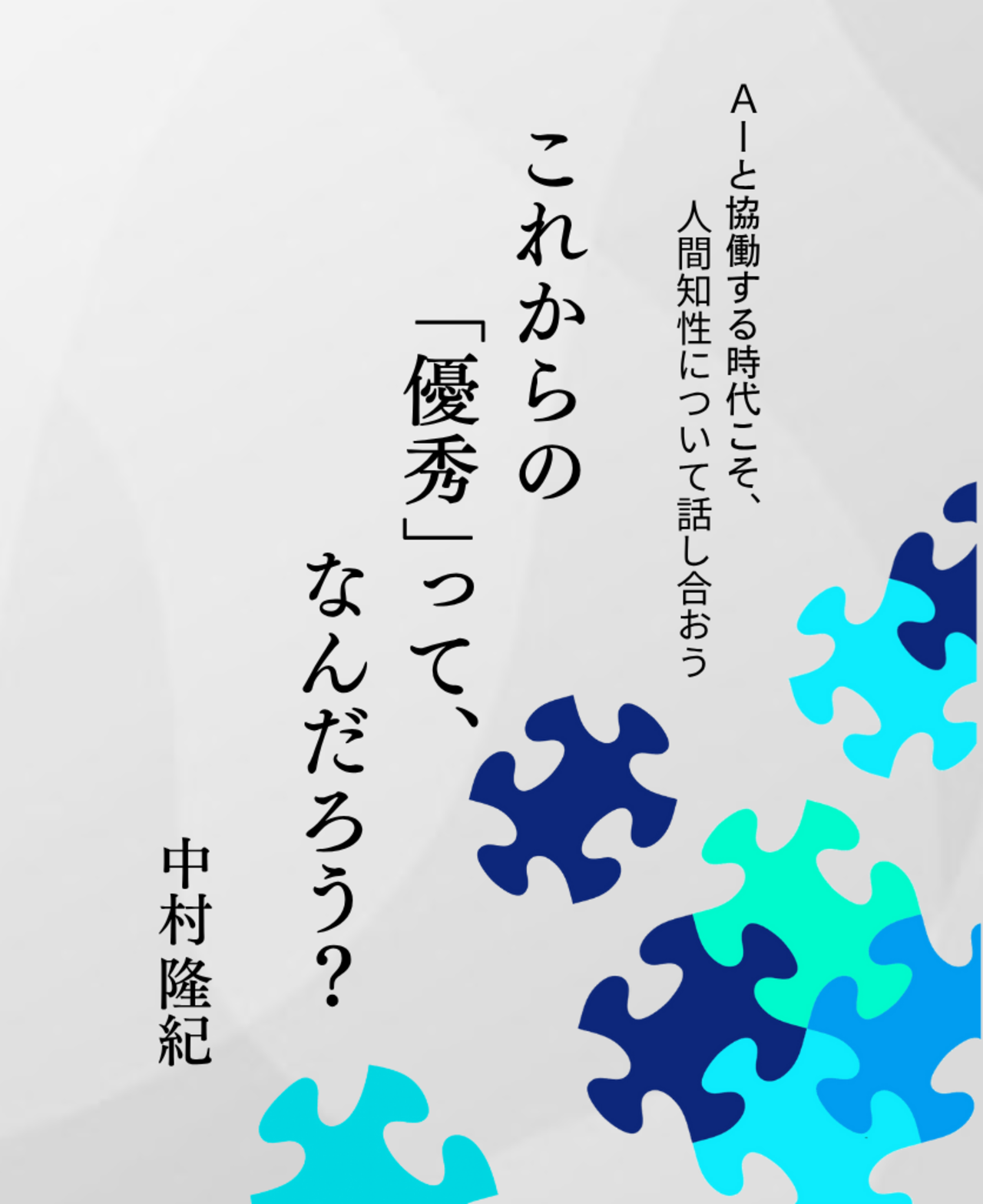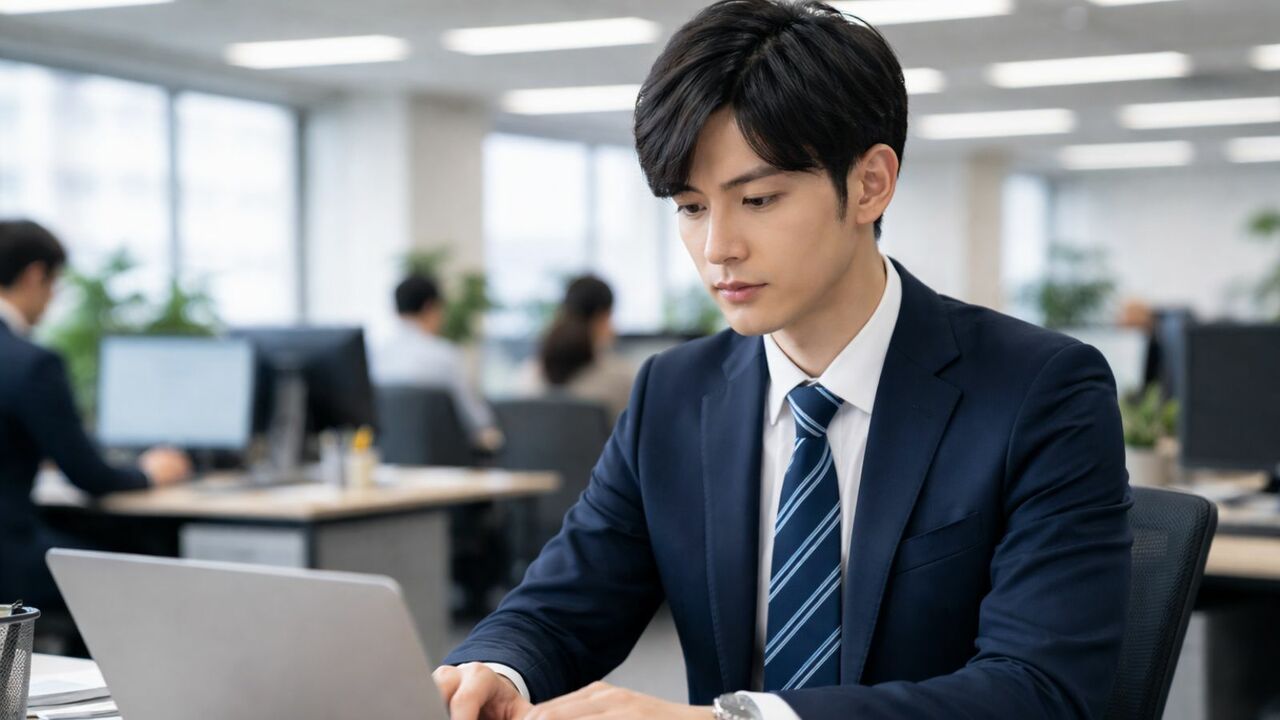【前回記事を読む】経営は、スキルではない。あらゆる学びによって磨かれていくものは、結局、人間ひとりひとりの芯にある、感性や想いなのだ
第一章 知覚センサー、機能不全
【クマくんの、もうちょい検索メモ】
[① 創造性の源泉、日常生活] アルフレッド・シュッツ(1899~1959)
『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』エドムント・フッサール著
『生活世界の構造』アルフレッド・シュッツ、トーマス・ルックマン著
『アルフレッド・シュッツ』ヘルムート・R・ワーグナー著 より引用編集
■シュッツの師のひとりであるフッサールは、第一次世界大戦により、科学的客観主義への危機感をいだいていた。
「十九世紀後半には、近代人の世界観全体が、もっぱら実証科学によって徹底的に規定され、また実証科学に負う『繁栄』によって徹底的に幻惑されていたが、その徹底性たるや、真に人間性にとって決定的な意味を持つ問題から無関心に眼をそらせるほどのものであった」
「単なる事実学は、単なる事実人をしかつくらない」
シュッツは、フッサールをはじめ、哲学や社会思想などさまざまな叡智に触発され、晩年まで銀行に勤めながら、現象学的社会学の道を拓いていった。
■シュッツは、科学よりも「日常生活世界」を至高の現実として中核に据えた。
■「日常生活世界」の周囲に、自然科学的な認識にもとづいた「自然的世界」があり、社会科学的な認識にもとづいた「社会的世界」がある。
■人間の現実は、「日常生活世界」を中核として「自然的世界」と「社会的世界」が相互に影響し合う「多元的現実」である。「日常生活世界」は思考のセンターであり、問いや研究を引き出し、さまざまな科学のゆりかごとなる。
■知識集積とは、論理的に統合されたシステムではなく、「日常生活世界」の主観的経験が沈殿したその全体のことである。その沈殿に「さらなる気づき」が生じるまで、私たちは世界を解釈しなおし続ける。