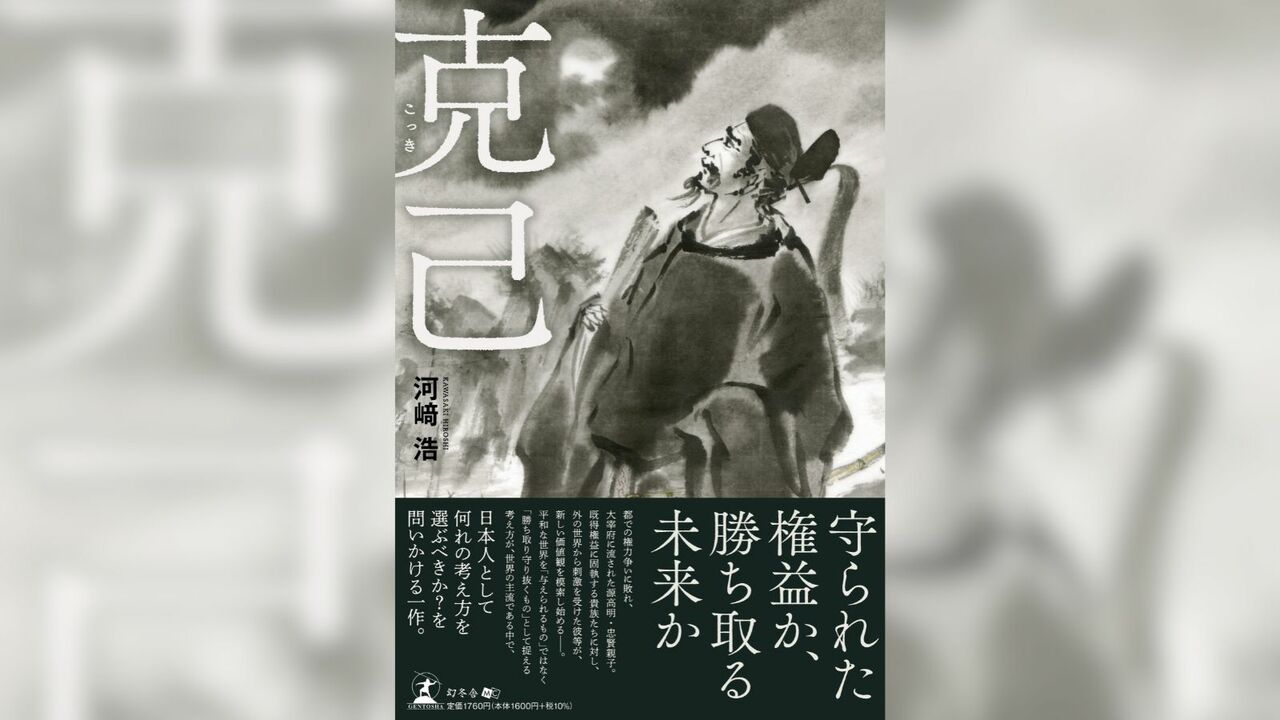【前回の記事を読む】戦闘で折れた敵の大刀を妻の包丁にするため、刀工へ研いでもらうよう頼む。作業場にいたのは美しい娘とその父であった。
刀工とは
自身が身に装(す)る“太刀”は、斯様にして生み出されている事を知識(経験則)として、身につける事は、彼等の好奇心を満たしていた。
湧水から、かけ流しで小屋に溜まる水桶に、赤く熱し、火花を散らしていた包丁が浸かる度に湧き上がる“湯気”が、室内を程よく潤し、彼等の額の汗は、借りている冠に、瞬く間に吸い込まれていったが、百足とマムシの被る晒(さらし)は、もっと効率よく、彼等の汗を吸い取っていた。
百足の胸元の汗が、彼女の乳房の根本に吸い込まれる様は、都の、自身の身の回りに居た、高貴な衣を纏う女共とは、別の、若い忠賢には、気の毒な“様(さま)”でもあった。朝から昼時まで延々と続く単調な作業ではあったが、この様は、彼等を離さなかった。
しかし、百足とマムシの体力は、そろそろ限界に達しつつあった。
その頃合いを見計らって、湧水を引き込んだ井戸でよく冷やした“瓜”と、その湧水で、よく冷やした白湯を甕に入れて持って来た女房が『そろそろ一息(ひといき)付けなされ』と言って、皆に声を掛けた。
各々が小屋を出た時、横にあった太陽は彼等の天頂から熱い日差しを容赦なく浴びせかけていた。
百足は、そのまま上半身を開(はだ)け湧水が湧く泉に向かい、頭の手拭い(晒)を解き、湧水を絞って体の汗を拭っていた彼女の、若い女性独特の背中は、神々しく、若い忠賢には映っていた。
マムシは、高明と千晴の、上等な設えが施されていた太刀を見遣った。
その様を見て千晴は
「構わぬ」
と彼に許諾を出した。マムシは恐る恐る、千晴の太刀を鞘から抜いて、お天道様に翳して診(み)た。
「如何思う?」