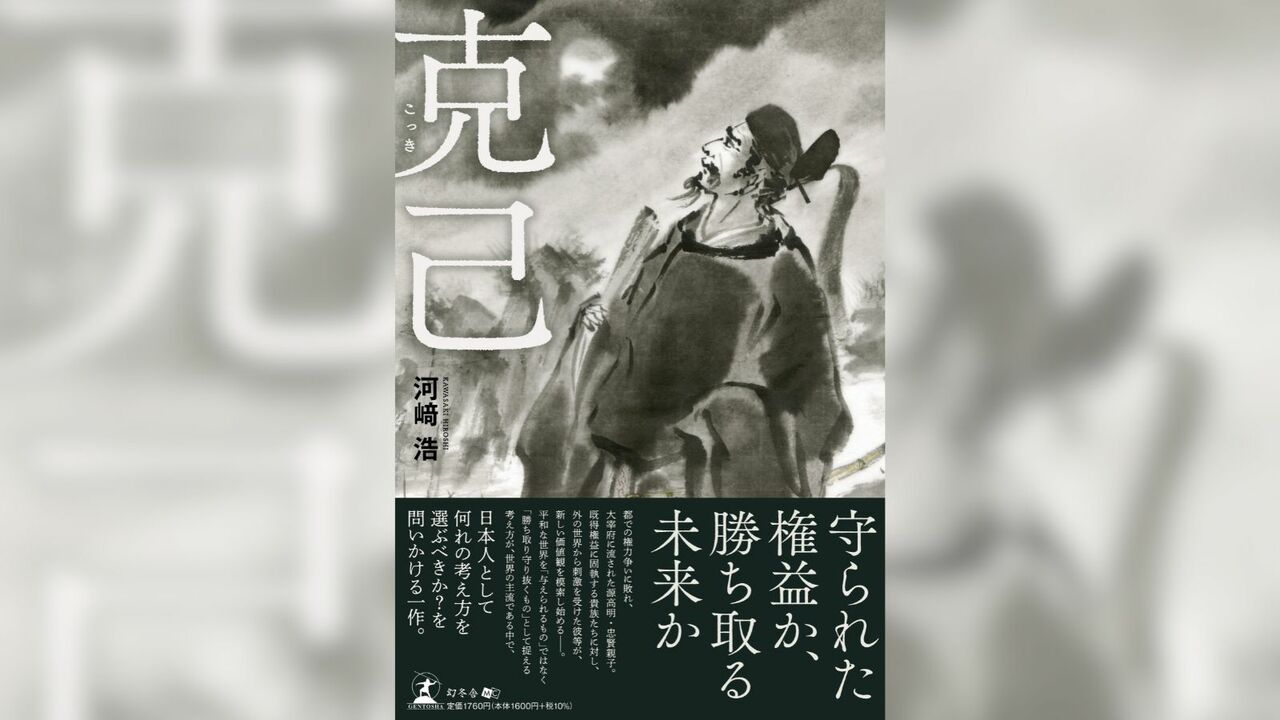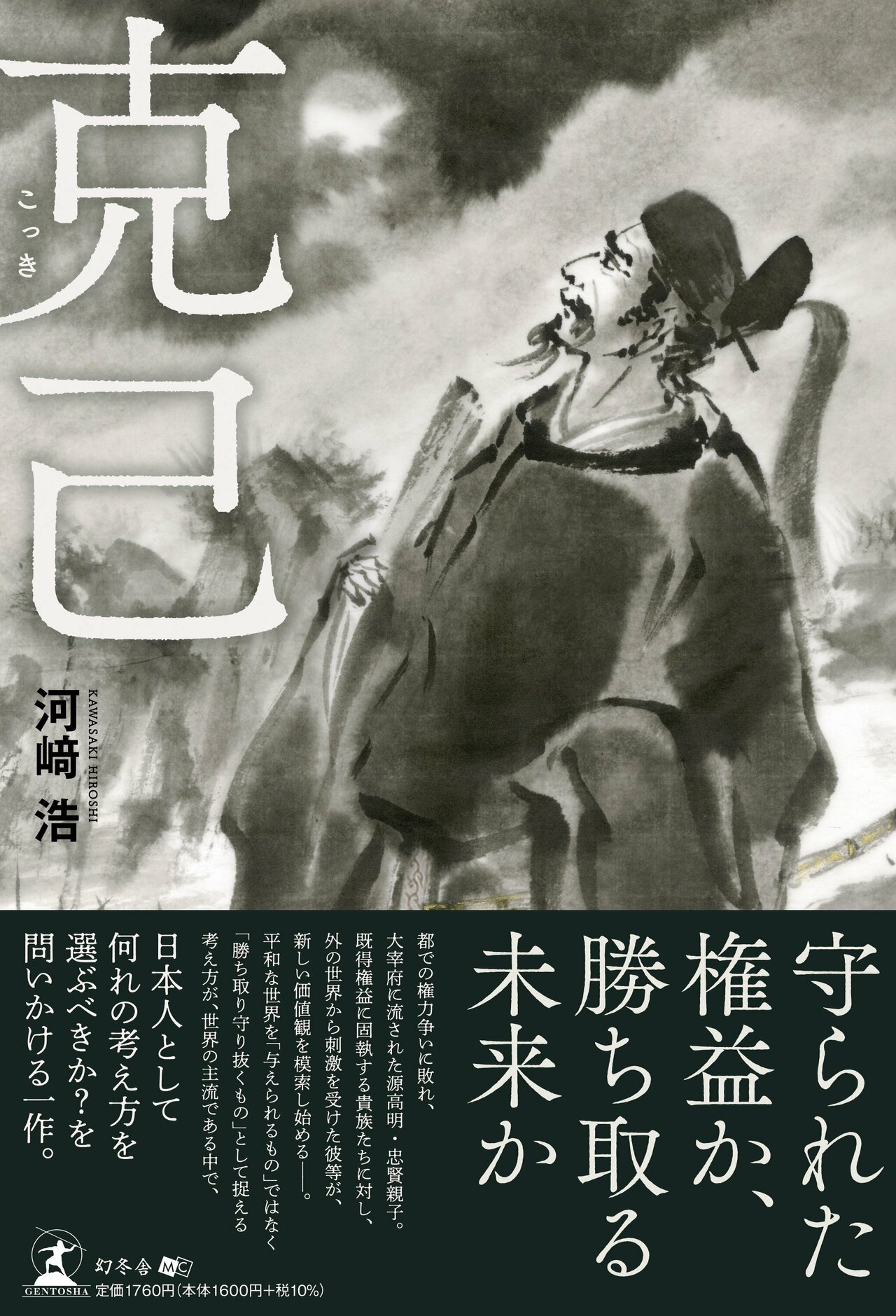【前回の記事を読む】「私が手を掛けて、一からとなると、最低半年か一年は――」だが、良質の玉鋼が入手出来なければ不可能であった
始まり
高明親子は、藤原北家の荘園を後にして、七日後、赴任地の大宰府に到着した。勿論一行の中に、マムシ親子がいた事は言うまでもなかった。
道中、彼等は、マムシに対し、彼が受けた、敵の武器に関する見解を多角的に質した。
結果、敵の持つ大太刀は、鍛えたモノでは無く、鋳込んだ金属に刃を付けた物に過ぎず、その用途としては、自重の重さにより相手を叩きのめし一撃を喰らわせる為の物であり、切ったり、突き刺したりという攻撃、特に、敵のほぼ鞣革(なめしがわ)で出来た防具では、当世の彼等の持つ切っ先が鋭く、柔軟且つ強度の高い武器(刃)の前では“敵”ではなく、急所となる部分には、隙間なく鉄(鎖)を織り込んである、今様の兜や大鎧には、敵の武器では、“余り”歯が、立たないのでは?と云う判断を高明父子は得ていた。
百足は、その道すがらの、全ての川や海岸での砂鉄収集や、(植生)木材の材質吟味に、余念がなく、高明親子や、実父との会話に口を挟む事は無かった。
着到後、大宰府近辺の散策に百足は、早速向かい、木炭に適した木の生えている森林や、清水や、泉の有無、川の水質の調査を始めた。
彼女の護衛という名目で、高明の郎党数名と、其の総大将として嫡子の忠賢が、父、権帥の下命で付いたが、これは父の気配りでもあり、彼にとっては、今風に言えば、ピクニックの様な日々が数日続いた。
「しかし、この女は“疲れ”と言う言葉を知らぬのか」
が、高明の百足に対する、第一印象であった。故に、彼女に付き添えるのは、我が嫡男以外に、思い浮かばなかった、と言うのも事実であった。
その間、大宰府の郎党や、高明の郎党が、総がかりでマムシの為の作業場と炉の選定、それに伴う建設が開始されていた。最適地として選ばれたのが、古からの城壁が残る、大城山の麓にある、水が湧き出ている場所であった。
此の作業場で陣頭指揮を執ったのがこの地の地侍筆頭である、若き大蔵種材であった。彼は、元々が百姓であった事もあり、土地をどのように生かすかという見識を持ち合わせていたが、地侍と呼べる程度に、武威に関しても、後々、眼力ある高明が認める程度の、能力があった。
故に、彼は、噂に聞くマムシの持つ小太刀の凄さや、戦闘力に関しては、一目を置いていた。
と云うより彼は、本来の大宰府が司る、仕事。要は、宋や琉球との交易に関して興味が湧かなかった。
依って、此の下命は“勿怪の幸い”でもあった。