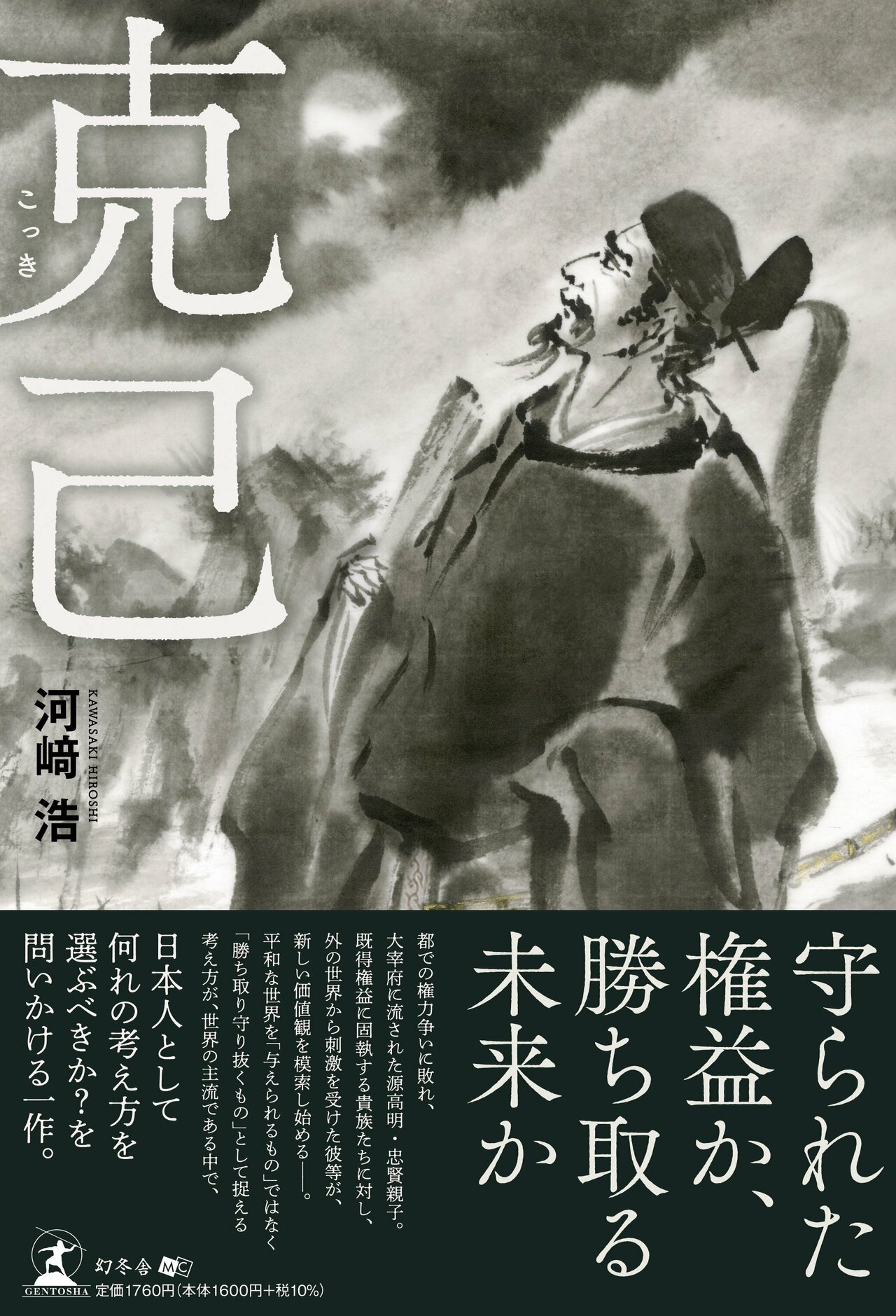お金のかかる“設え”や“防御線(土塁)”の構築に、直ぐに取り掛かる事は“愚の骨頂”で在り、今は、九州各地の百姓や地侍、大宰府の舎人と言う、マンパワーの強化と、関係性の構築・強化が、最も手早く、安上がりに、今、直ぐ、出来る効果的な“防御手段”であった。
故に、彼等父子は、都からの貴人や、天皇の息子(孫)という“体”を着任早々、一切かなぐり捨てたのだった。
彼は、当時、日本で唯一と言って良い、外に開かれた玄関口と言う大宰府の地の利を活かし、対外情報の収集、集積、分類、解析に努め、今で言う“インテリジェンス”関係を扱う役所の部門の強化にも勤しんだ。
当然、その結果は、自身の元に集約され、高明の解釈の下、大宰府に集う、役人や舎人等、実力部隊・関係者達に、公平に、結果を酒席や宴席を通じて説明し、認識させていった。
故に、彼は、関係各位、特に百姓や、舎人・地侍等との会食や宴、祭りの場に“頻繁に顔を出す”事となった。
彼は、妻帯していたが、彼の後妻は、当時九条右大臣と呼ばれた藤原師輔(ふじわらもろすけ)の娘であり、都の“雅(みやび)な”貴女でも在ったので、この様な事柄に、斯様な女を饗応役として供する事は、相応しくはない、という冷徹な判断の下、彼は妻(忠賢の母ではない)や、その子達は、都に置かれ(呼び寄せる事をせず)、地元の女と、嫡子を傍に侍らすようになった。
その様な実情もあってか、地元で台頭しつつある荘官や田堵(たと)と呼ばれた、都の貴族の所領(荘園)を預かる、農民や、官位が低い者・地元出身の有力下級貴・豪族や農漁民は、高明の普段の行動を見て、彼の着任から、そう、間を置かずこぞって、自身の娘や親族を高明の寝所や住居に遣わす様になって行った。
【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…
【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。