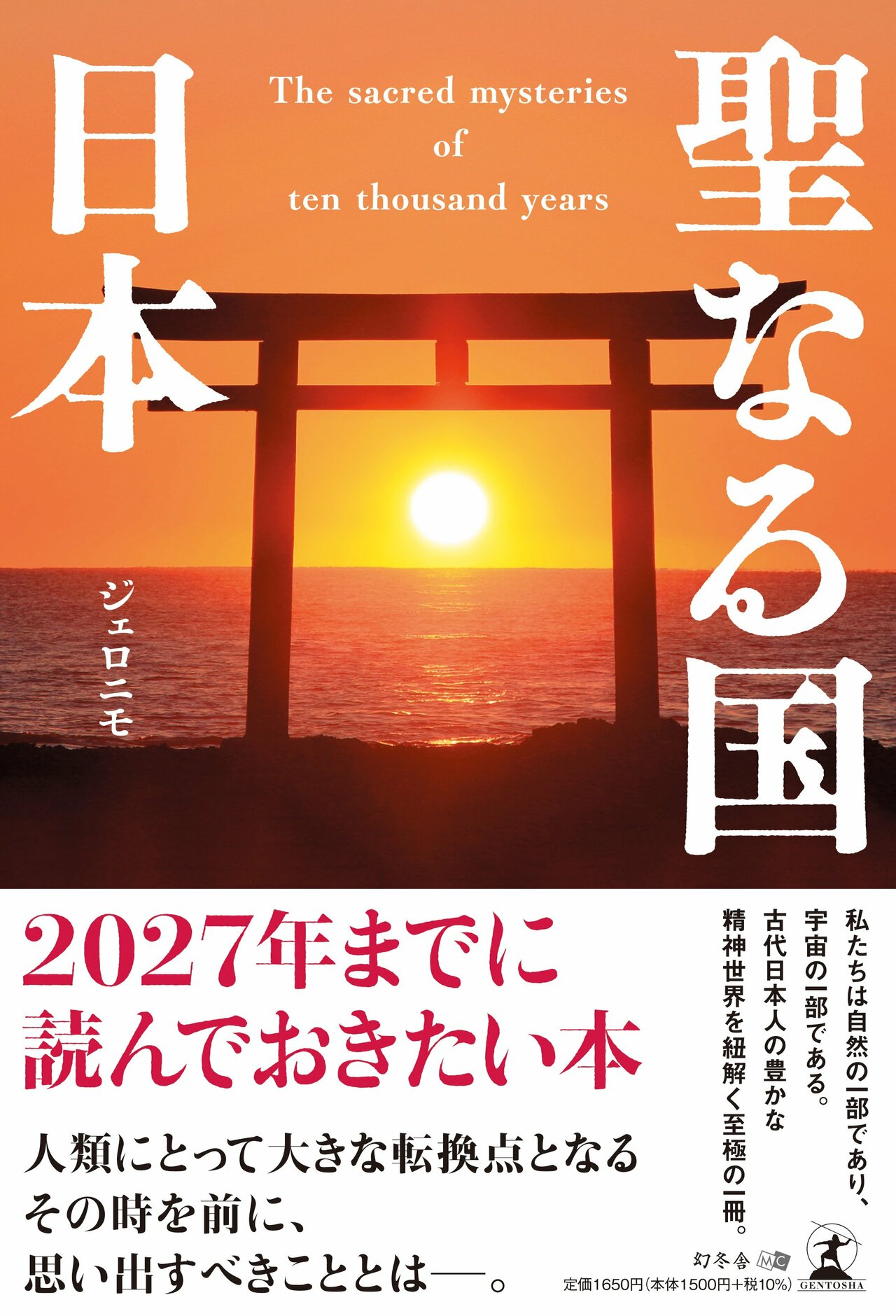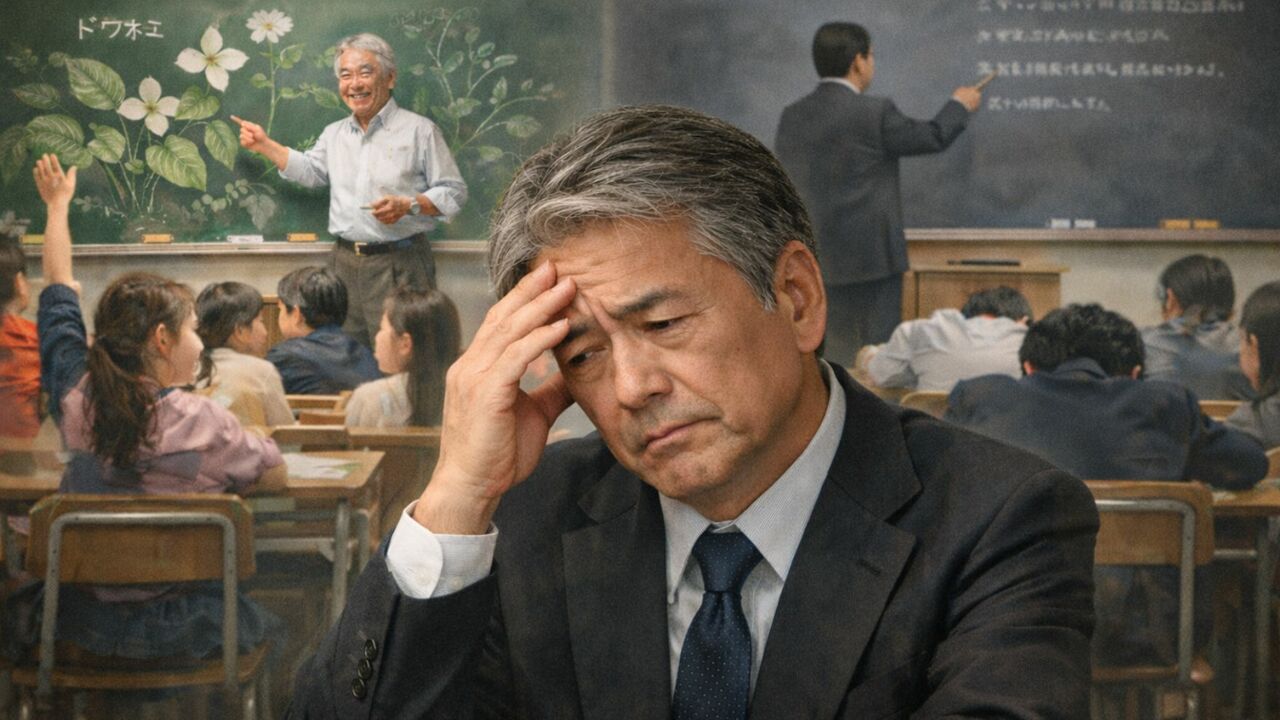第I章 女性は神々と繋がる神聖な存在
子宮とお宮
子宮には「宮」という字が使われている。日本の神社の中でも特に皇統・皇室に関わりのある神社などにも神社でなく「神宮」という尊称が用いられ「宮」という字が使われている。
神社という名称で祀るのは日本独特だが、宮・社・堂・廟など祀る場所の名称は、日韓中ほぼ共通で、宮はその中でも神聖なる存在、王や神、高貴なる者の特別な存在の坐す所だ。
明治神宮、八幡宮、伊勢神宮、阿房宮、故宮、天后宮、ポタラ宮、景福宮と日韓中ともに「宮」という字は全て特別な存在の居場所に対して使われている。当たり前のように慣れ親しんでしまっているが、「子宮」という言葉に貴種の居場所を示す「宮」という字が使われているのはなぜだろうか?
それは、聖なる存在=子どもという貴重な存在を宿す大切な「宮」だからだ。
ただ子どもを宿すだけの臓器ということであれば「胎臓」という言葉で事足りる。だが子どもはみな神の子であり、神の子を宿すからこそ「子宮」と言う神聖な存在を宿す言葉となる。現代人には思いもよらないほど、古代では神の子を宿す女性は神聖な存在として敬われていた。至極当たり前のことだが、人間は皆女性から生まれてくるからだ。
大きな命の円環の中で、「神の宮」と「神の子を宿す宮」=子宮は存在している。宮という字の「呂」は部屋が二つ繋がっている状態を表すらしいが、呂という字には「大切なもの・貴重なもの・人の根幹を成すもの」という意味があるそうで、そう考えると「呂」という字も、部屋ではなく母と子が繋がっている妊婦さんにも見えてくる。
「うちの子」という言葉も現代の私たちは当たり前に使っているが、遥か古代において子どもはうちの子ではなく、全て「神様の子」だった。親たちは、神様の子を預かって育てていたのであり、子どもは親や家に属する存在ではなかった。
考えてみれば、男性が「うちの嫁」と言うのも失礼な言い方で、決して所有物の様に思っている訳ではないだろうが表現としてはそういう意味にもとれる。子供に対しても同じ様な意味合いで『子どもの人権宣言』では「供」という親に供われ従う存在という表現をせず、「子ども」とひらがな表記になっている。
嫁=女の家は、女性を主人として迎えた家であり「家の女」という家に属する存在の様な意味ではない。
古代では、男性の通い婚が常識で「女の家」に男が通う。そして子どもは里で大切に育てられ、女系社会では必ず戸主や首長は女性がなった。婚姻し相手の姓になる時も母方の姓を継ぐ。そもそも「姓」と言う字は、どの女性から生まれてきたかを示すものだ。