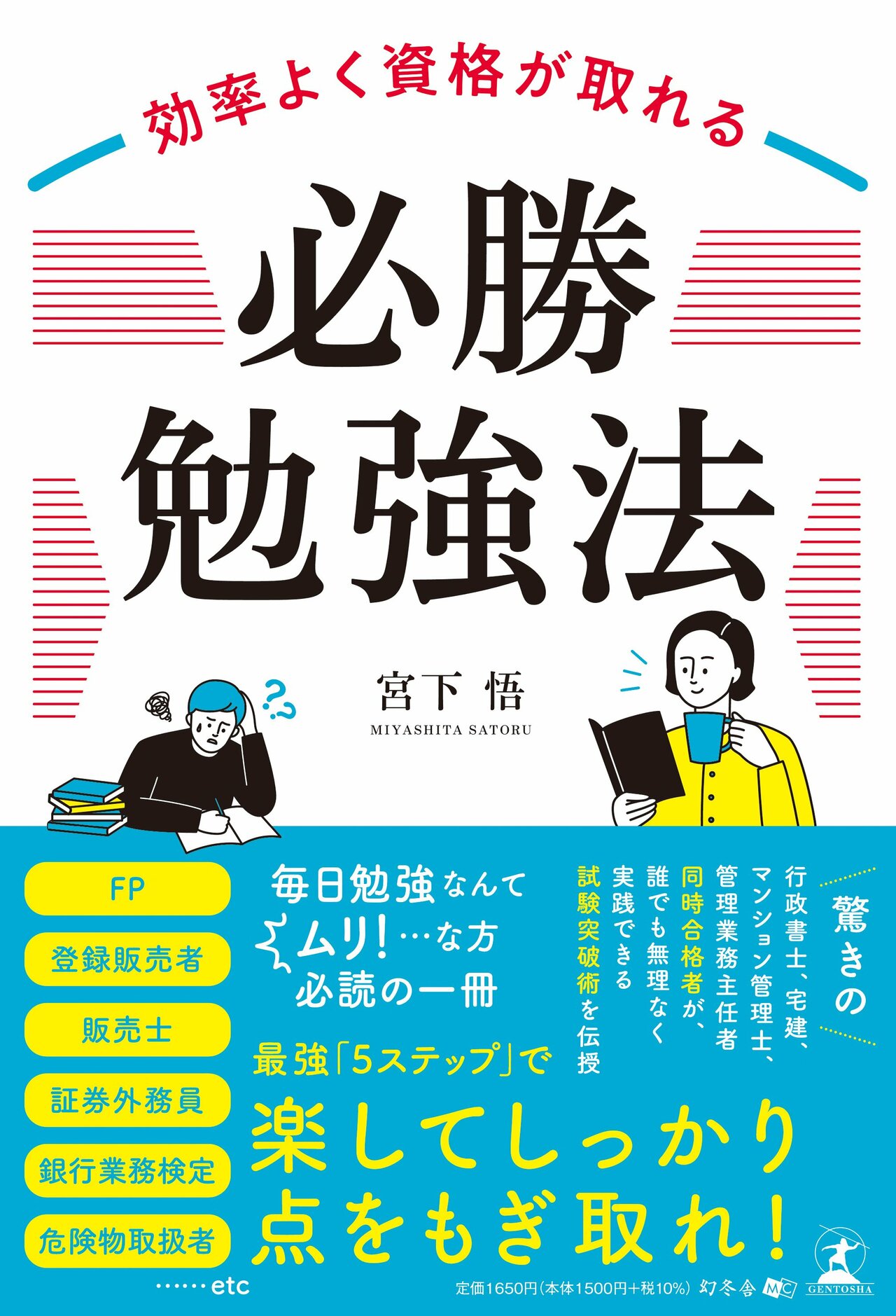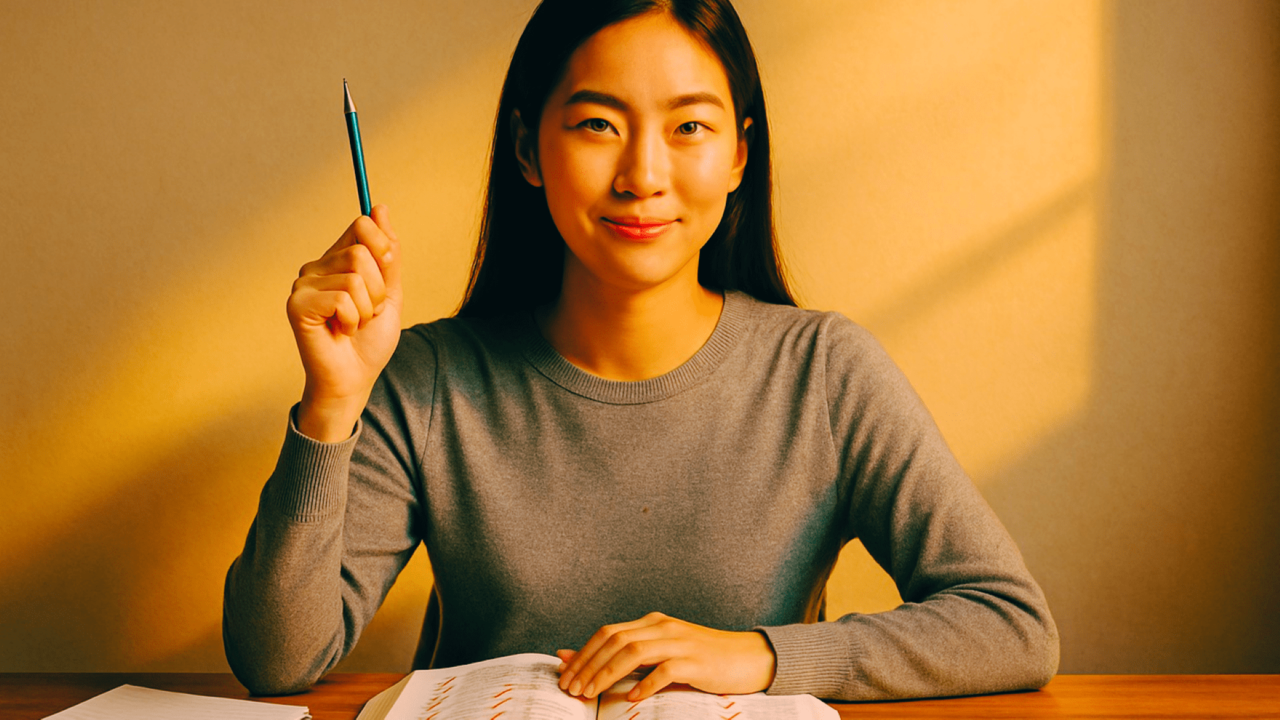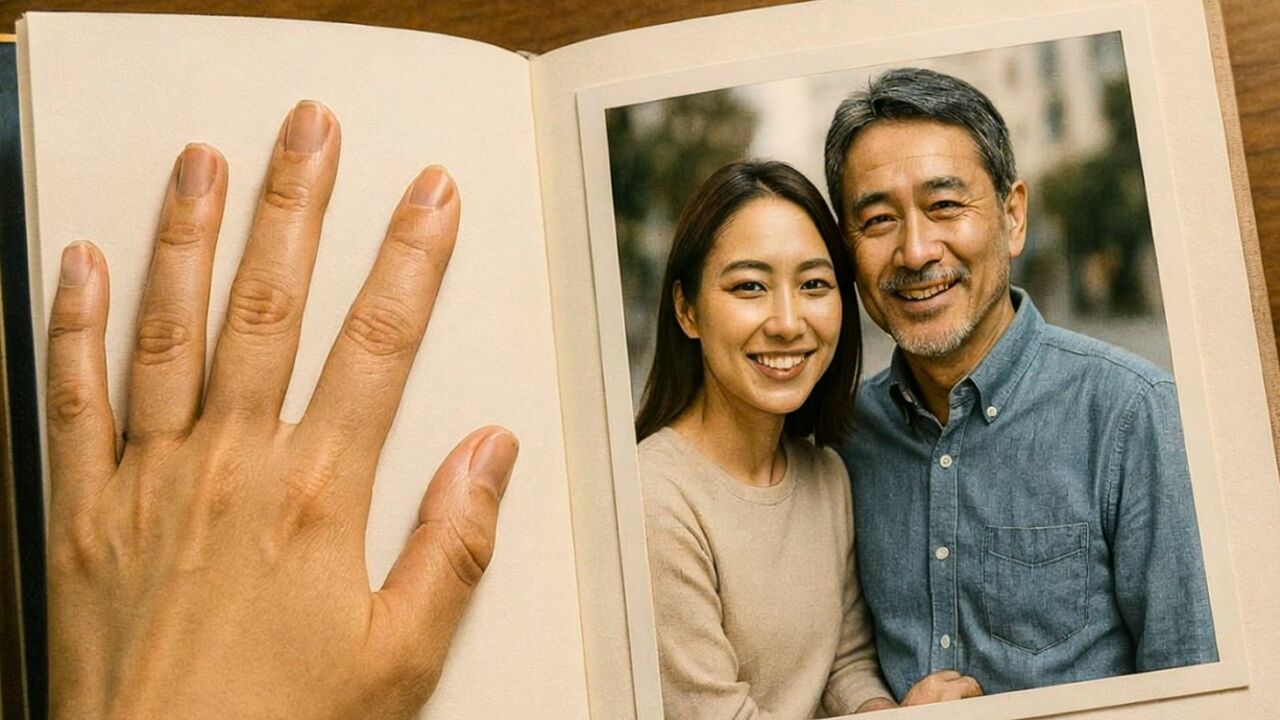2 私と資格との縁
そもそも、私が資格を取得する動機や、資格に興味を持った経緯を記したい。少々長くなるが、ここで記す経緯を読んでいただき、資格勉強法がどのように確立されたかを知っていただければと思う。
資格については、高校時代より興味があった。それは、周りの人から「手に職をつけたほうがよい」というアドバイスをもらい、サービス産業が中心の日本において「手に職」といえば、それはつまり「資格」ではないか、と漠然と考えるようになったからである。
大学一年次(二〇〇〇年)に、行政書士を受験した。大学入学直後から勉強を開始し、「十代で合格し、社会保険労務士の受験資格(行政書士保有)が得られればいいな」と思ったものの、結果は不合格。当時、行政書士は一四〇点満点中の六割正解(八四点)で合格であったが、私はなんと八三点、つまり「一点差に泣いた」のであった。
「一点の違いで、先に進めるか、改めて一年勉強し直すかの分かれ道がある」
このとき程、「一点の差」が身に沁(し)みたことは、人生で後にも先にもない。それ程、悔しい思いをしたのである。
翌年(二〇〇一年)、行政書士のリベンジを期し、再度勉強に取り組んだ。
その年は、偶然にも大学の「課外講座」という形で、大手資格予備校の「宅建(宅地建物取引主任者、現在の宅地建物取引士)講座」が行われることになった。当時、13万円程かかるコースが課外授業で受けられる、ということに魅力を感じ、行政書士と宅建のダブルで取得することを目指した。
基本は行政書士の勉強、特に過去問を繰り返し解くことを中心とし、宅建については授業を聞き、こちらも過去問を中心とした資格予備校オリジナルの問題集を繰り返し解くこととした。学生の身分であったものの、大学の授業と行政書士、宅建の勉強を並行して進めることは大変であった。そこで役立ったのが、「復習のタイミングの取り方」であった。
行政書士試験を前年に受けた経験があったとはいえ、勉強する範囲が倍近く広がることになるため、「効率よく勉強すること」がダブル取得の肝であると考えた。結果的に勉強法の効果もあり、両方に合格することができた。
👉『効率よく資格が取れる「必勝勉強法」』連載記事一覧はこちら