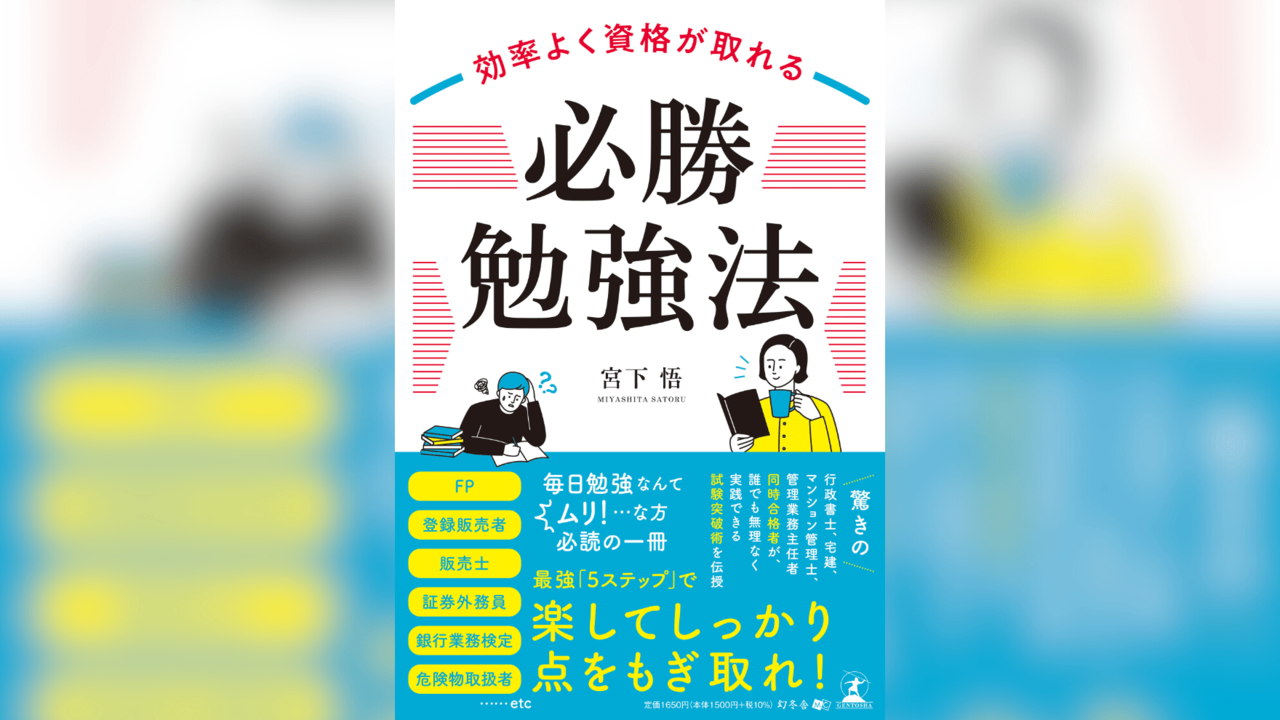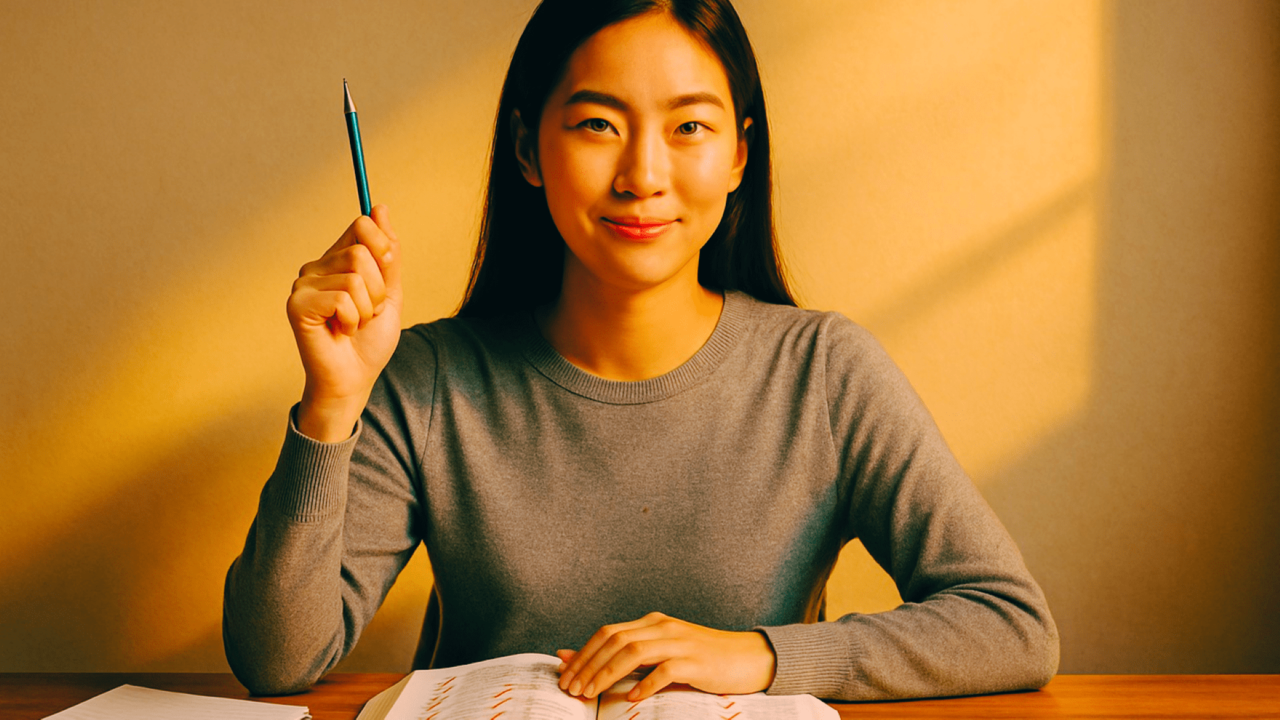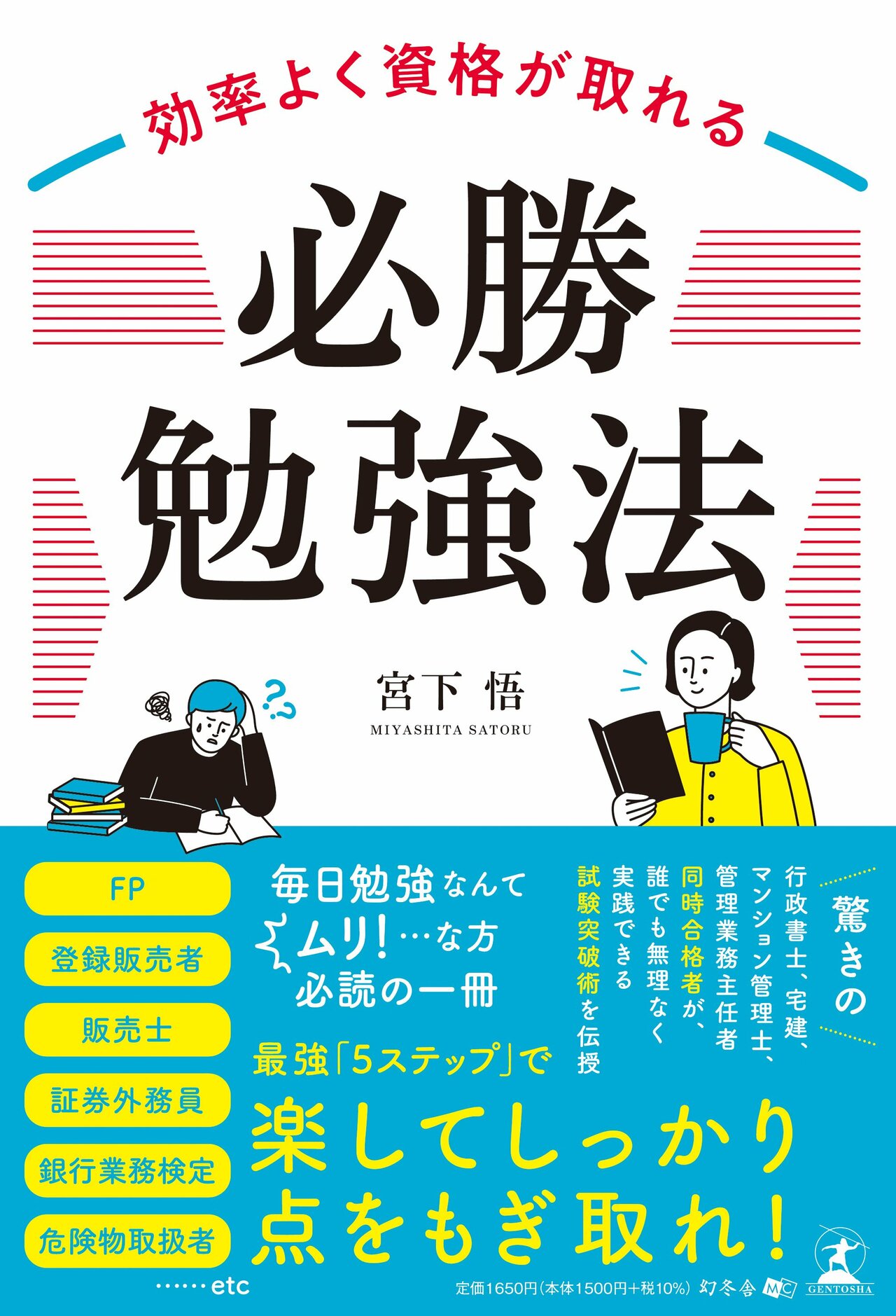【前回の記事を読む】過去問を読んだ後に必ず実践したい、得点力を着実に伸ばし合格力を高める勉強法とは
第3章 具体的な勉強方法
3 三回目:選択肢の正誤判断と、間違えた箇所の確認
三回目の勉強(二回目の復習)は、二回目の勉強(一回目の復習)から十~二十日後を目安に行う。
なぜ一回目よりも間隔を空けるのかというと、「既に二回の勉強をしたことにより、徐々にでも記憶の定着が始まっている」と考えられるからである。少なくとも、「勉強した記憶が全くない」ということはないだろう。もしほとんど記憶に残っていないのであれば、一回目の復習と同様、勉強間隔を前倒しする。
また、三回目の勉強を行う時点で、他の分野や項目の一回目の勉強と、二回目の勉強も合わせて進める必要がある。そうなると、先程書いた通り、三回目の勉強はできるだけ間隔を空けたほうが、全体的に勉強に余裕ができる。
では、三回目の勉強は何をすればよいか。
まず、一度問題の選択肢を読み、正誤判断をしてから解答・解説を読む。選択肢を読む際に「なぜ正しいか」、逆に「なぜ間違っているか」を検討する。そして、根拠が答えられなかった場合、選択肢の左側に斜線(/)をつける。また、解説を読み、間違えた箇所や気になる箇所は、シャープペンシル等、消しゴムで消せる筆記用具で書き込む。
なぜ「消せる筆記用具」で書くのか。それは、この段階ではまだ、該当箇所が「弱点」なのかどうかの判断までには至らないからである。
例えば、間違えた箇所を蛍光ペン等でマーカーするとしよう。この先、四回目、五回目の勉強を進めていくと、「記憶の定着」により正解できる問題は増えていく。逆に、それでもできないところが「弱点」であり、その箇所こそ蛍光ペンや色つきのボールペン等で印をつける、または重要ポイントを書くべきところである。
早い段階で消せない筆記用具で書いてしまうと、かえって「弱点」の箇所なのか判断がしにくくなる。
また、選択肢の正誤判断で間違えたところは、重点的にテキストの該当箇所を確認する。
テキストで確認する作業は、これで二回目となる。テキストに書いてある量はかなりのボリュームであるが、実際に試験で問われる部分は、テキストの中でもある程度限定されていると実感できるのではないか。
テキストは、基本的に試験要項に書かれている範囲を満遍なく記載している。中には、「テキストを『隅から隅まで』読んでも、なかなか頭に入らない」と悩む人もいるだろう。ここでは、テキスト全てを「暗記」する必要はない、ということをお伝えしたい。